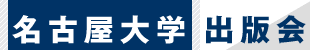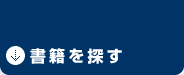2023年度書評一覧
『内陸アジア史研究』 [第39号、2024年3月] から(評者:宇野伸浩氏)
カーシャーニー オルジェイトゥ史
イランのモンゴル政権イル・ハン国の宮廷年代記

大塚修・赤坂恒明・髙木小苗・水上遼・渡部良子訳註『カーシャーニー オルジェイトゥ史』が、『内陸アジア史研究』(第39号、2024年3月、内陸アジア史学会発行)で紹介されました。モンゴル帝国を構成する政権の一つ、イル・ハン国に仕えた歴史家カーシャーニー。その手になるオルジェイトゥ治世の年代記は、『集史』以降の時代を扱い、大帝国の実像を伝えるとともに、ユーラシア各地の貴重な情報をも記録した第一級の史料である。詳細な解題・訳註を付した、ペルシア語史書初の日本語全訳。
大塚 修・赤坂恒明・髙木小苗・水上 遼・渡部良子 訳註
税込9,900円/本体9,000円
A5判・上製・516頁
ISBN978-4-8158-1105-1 C3022
在庫有り
『アジア経済』 [第65巻1号、2024年3月] から(評者:金子文夫氏)
「満洲国」以後
中国工業化の源流を考える
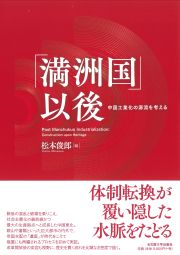
松本俊郎編『「満洲国」以後』が、『アジア経済』(第65巻第1号、2024年3月、アジア経済研究所発行)で紹介されました。戦後の混乱と破壊を乗りこえ、社会主義化の最前線かつ最大の生産拠点へと成長した中国東北。鞍山や瀋陽といった巨大都市の内外で、帝国支配の「遺産」が時代をこえて幾重にも再編されるプロセスを初めて実証。改革開放後の変容も視野に、歴史を貫く流れを比類なき密度で描きます。
松本俊郎 編
税込6,380円/本体5,800円
A5判・上製・358頁
ISBN978-4-8158-1114-3 C3033
在庫有り
『経済学史研究』 [65巻2号、2024年1月] から(評者:服部茂幸氏)
中央銀行はお金を創造できるか
信用システムの貨幣史
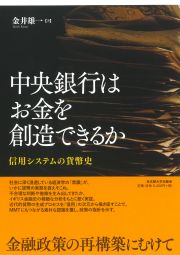
金井雄一著『中央銀行はお金を創造できるか』が、『経済学史研究』(65巻2号、2024年1月、経済学史学会編)で紹介されました。社会に深く浸透している経済学の「常識」が、いかに貨幣の実態を捉えそこね、不合理な判断や施策を生み出してきたか、イギリス金融史の精緻な分析をもとに鋭く実証。近代的貨幣の生成プロセスを「信用」の次元から描き直すことで、MMTにもつながる素朴な認識を覆し、政策の指針を示します。
金井雄一 著
税込5,940円/本体5,400円
A5判・上製・234頁
ISBN978-4-8158-1125-9 C3033
在庫有り
『経済学史研究』 [65巻2号、2024年1月] から(評者:江頭進氏)
経済学のどこが問題なのか
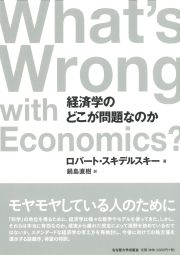
ロバート・スキデルスキー著/鍋島直樹訳『経済学のどこが問題なのか』が、『経済学史研究』(65巻2号、2024年1月、経済学史学会編)で紹介されました。モヤモヤしている人のために ——。「科学」の地位を得るために、経済学は様々な数学やモデルを使ってきた。しかし、それらは本当に有効なのか。現実から離れた想定によって視野を狭めているのではないか。スタンダードな経済学の考え方を再検討し、今後に向けての処方箋を提示する話題作。
ロバート・スキデルスキー 著/鍋島直樹 訳
税込3,960円/本体3,600円
A5判・上製・288頁
ISBN978-4-8158-1088-7 C3033
在庫有り
『経済学史研究』 [65巻2号、2024年1月] から(評者:寺尾範野氏)
社会をつくった経済学者たち
スウェーデン・モデルの構想から展開へ
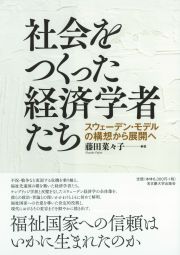
藤田菜々子著『社会をつくった経済学者たち』が、『経済学史研究』(65巻2号、2024年1月、経済学史学会編)で紹介されました。不況・戦争など直面する危機を乗り越え、福祉先進国の礎を築いた経済学者たち。ケンブリッジ学派と双璧をなしたスウェーデン経済学の全体像を、彼らの政治・世論との深いかかわりとともに初めて解明、福祉国家への合意を導いた決定的役割と、現代におけるその変容までを鮮やかに描き出します。
藤田菜々子 著
税込6,930円/本体6,300円
A5判・上製・438頁
ISBN978-4-8158-1097-9 C3033
在庫有り
『経済学史研究』 [65巻2号、2024年1月] から(評者:渡辺恵一氏)
野蛮と宗教Ⅱ
市民的統治の物語
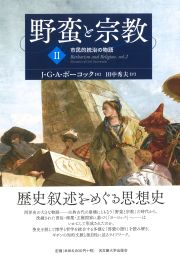
J・G・A・ポーコック著/田中秀夫訳『野蛮と宗教Ⅱ』が、『経済学史研究』(65巻2号、2024年1月、経済学史学会編)で紹介されました。西洋史の大きな物語 —— 古典古代の崩壊にともなう「野蛮と宗教」の時代から、洗練された習俗・商業・主権国家に基づく「ヨーロッパ」へ —— はいかにして形成されたのか。聖史を脱して博学と哲学を統合する多様な「啓蒙の語り」を読み解き、ギボンの知的文脈と独自性に迫るライフワーク。好評の第Ⅰ巻に続く、歴史叙述をめぐる思想史。
J・G・A・ポーコック 著/田中秀夫 訳
税込7,480円/本体6,800円
A5判・上製・424頁
ISBN978-4-8158-1096-2 C3022
在庫有り
『昭和文学研究』 [第88集、2024年3月] から(評者:佐藤泉氏)
戦後表現
Japanese Literature after 1945

坪井秀人著『戦後表現』が、『昭和文学研究』(第88集、2024年3月、昭和文学会編)で紹介されました。アジア太平洋戦争から冷戦、昭和の終わり、湾岸・イラク戦争、ポスト3・11まで、戦争をめぐる言葉がすくい上げてきたもの、底に沈めてきたものを、詩・小説・批評を中心に精緻に読解。経験や記憶に刻まれた〈傷跡〉としての表現の重層性から、〈戦後〉概念を再審にかけます。
坪井秀人 著
税込6,930円/本体6,300円
A5判・上製・616頁
ISBN978-4-8158-1116-7 C3095
在庫有り
『西洋史学』 [第276号、2023年12月] から(評者:山中由里子氏)
ヨーロッパ中世の想像界
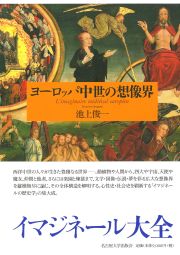
池上俊一著『ヨーロッパ中世の想像界』が、『西洋史学』(第276号、2023年12月、日本西洋史学会発行)で紹介されました。西洋中世の人々が生きた豊穣なる世界 ——。動植物や人間から、四大や宇宙、天使や魔女、仲間と他者、さらには楽園と煉獄まで、文学・図像・伝説・夢を彩る広大な想像界を縦横無尽に論じ、その全体構造を解明する。心性史・社会史を刷新する「イマジネールの歴史学」の集大成。
池上俊一 著
税込9,900円/本体9,000円
A5判・上製・960頁
ISBN978-4-8158-0979-9 C3022
在庫有り
『社会経済史学』 [第89巻第4号、2024年2月] から(評者:水野敦洋氏)
輸出立国の時代
日本の軽機械工業とアメリカ市場

沢井実著『輸出立国の時代』が、『社会経済史学』(第89巻第4号、2024年2月、社会経済史学会発行)で紹介されました。戦後日本の復興を支え、高度成長を生み出した対米輸出への道は、いかにして切り拓かれていったのか? 自動車・家電に先駆けてアメリカを席捲したカメラ、ミシンなど軽機械の動向を初めて包括的に解明、労働集約型産業の変貌を現場からとらえて、今日に及ぶ発展を鮮やかに描き出します。
沢井 実 著
税込6,380円/本体5,800円
A5判・上製・296頁
ISBN978-4-8158-1099-3 C3033
在庫有り
『社会経済史学』 [第89巻第4号、2024年2月] から(評者:加来祥男氏)
失業を埋めもどす
ドイツ社会都市・社会国家の模索
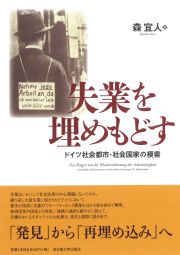
森宜人著『失業を埋めもどす』が、『社会経済史学』(第89巻第4号、2024年2月、社会経済史学会発行)で紹介されました。失業はいかにして発見され、社会政策の中心課題になったのか。繰り返し大量失業に悩まされたドイツにおいて、都市が国家に先駆けてセーフティネット構築をはかる姿を初めて解明、慈善団体や国家との対抗/連携の過程も鮮やかに捉えて、労働をめぐるモダニティの大転換を、現代も視野に描き出します。
森 宜人 著
税込7,480円/本体6,800円
A5判・上製・396頁
ISBN978-4-8158-1103-7 C3022
在庫有り
『2023年人文地理学会大会 研究発表要旨』 [2023年11月] から(評者:原口剛氏、宮内洋平氏)
カースト再考
バングラデシュのヒンドゥーとムスリム

杉江あい著『カースト再考』が、『2023年人文地理学会大会 研究発表要旨』(2023年11月、人文地理学会発行)で紹介されました。宗教が異なれば社会のかたちも異なる、という図式は、本当に有効なのか。生活の場を介して、カーストを含む多様な集団が相互に交錯する過程を、宗教の別をこえてトータルに把握。物乞いや聖者など宗教横断的な主体も視野に、分裂した南アジア像が覆い隠してきたものをすくいだします。
杉江あい 著
税込7,920円/本体7,200円
A5判・上製・426頁
ISBN978-4-8158-1112-9 C3022
在庫有り
『週刊読書人』 [2024年2月23日号、第3528号] から(評者:宮間純一氏)
維新の政治と明治天皇
岩倉・大久保・木戸の「公論」主義 1862~1871

伊藤之雄著『維新の政治と明治天皇』が、『週刊読書人』(2024年2月23日号、第3528号、読書人発行)で紹介されました。国家の危機を前に、幕末・維新のリーダーたちはいかにして政治的意思決定を行ったのか。そのとき天皇のあり方はどのように変化したのか。岩倉具視・大久保利通・木戸孝允らによる「公論」主義を軸に、倒幕から廃藩までの激動の過程を一貫した視座のもとでとらえ、新たな明治維新像を示す渾身作。
伊藤之雄 著
税込10,780円/本体9,800円
A5判・上製・834頁
ISBN978-4-8158-1139-6 C3021
在庫有り
『図書新聞』 [2024年3月2日号、第3629号] から(評者:水野祐地氏)
インドネシア政治とイスラーム主義
ひとつの現代史

茅根由佳著『インドネシア政治とイスラーム主義』が、『図書新聞』(2024年3月2日号、第3629号、武久出版発行)で紹介されました。多様な宗教を包摂する「民主化の成功国」で、「不寛容」の烙印を押されたイスラーム主義者の系譜がなぜ人々を糾合できたのか。デモクラシーと排他性の間で揺れてきた彼らの活動を軸に、インドネシアにおける政治と宗教のダイナミズムを、独立期からSNSの時代まで総体的に捉え直した、俊英の力作。
“…… 本書の魅力はそのスコープである。本書を手に取れば、インドネシアのイスラーム主義の長い歴史を俯瞰できる。それに加え、時代ごとのイスラーム主義運動における重要人物、組織、イベント、政治課題を網羅できる。議会制民主主義時代から独裁者スハルトの新秩序時代にかけては、イスラーム主義勢力における揺るぎないリーダーであったモハンマド・ナッシールに焦点が当てられる。あとがきにあるように、著者はナッシールの家族宅を訪れたことがあるとのことだが、そんなエピソードが物語るように、著者はナッシールの思想について一次資料にくまなくあたりながら議論を展開する。著者が強調するように、ナッシールの主張はイスラーム主義的でありながら民主主義の理念に基づいており、「イスラーム」と「西洋」は切り離されるべきものではなく、融合させるべきだとする20世紀初頭の「近代主義イスラーム」の影響が見て取れる。……”(第3面)
茅根由佳 著
税込6,380円/本体5,800円
A5判・上製・282頁
ISBN978-4-8158-1134-1 C3031
在庫有り
『歴史学研究』 [2024年3月号、第1046号] から(評者:高田良太氏)
近世東地中海の形成
マムルーク朝・オスマン帝国とヴェネツィア人

堀井優著『近世東地中海の形成』が、『歴史学研究』(2024年3月号、第1046号、歴史学研究会編/績文堂出版発行)で紹介されました。古くから東西交易の要衝として栄えた「レヴァント」。中世から近世への転換のなか、イスラーム国家とヨーロッパ商人の「共生」を支えてきた秩序の行方は? オスマン条約体制や海港都市アレクサンドリアのありようから、異文化接触の実像を明らかにするとともに、東アジアに及ぶ「治外法権」の淵源をも示した力作。
堀井 優 著
税込5,940円/本体5,400円
A5判・上製・240頁
ISBN978-4-8158-1053-5 C3022
在庫有り
『比較経済研究』 [第61巻第1号、2024年1月] から(評者:馬欣欣氏)
中国国有企業の政治経済学
改革と持続
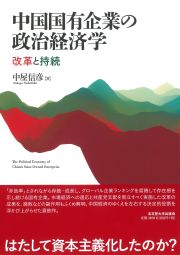
中屋信彦著『中国国有企業の政治経済学』が、『比較経済研究』(第61巻第1号、2024年1月、比較経済体制学会発行)で紹介されました。非効率なはずの企業群はなぜ存続し、成長できたのか。グローバル企業ランキングを席捲し、存在感を示し続ける国有企業が、市場経済への適応と共産党支配を両立すべく実施した改革の成果を、腐敗などの副作用も含め解明、「普通の」資本主義体制に抗いながら発展する中国経済の実像に迫ります。
中屋信彦 著
税込6,930円/本体6,300円
A5判・上製・366頁
ISBN978-4-8158-1095-5 C3033
在庫有り
『東南アジア研究』 [第61巻第2号、2024年1月] から(評者:古田元夫氏)
南シナ海問題の構図
中越紛争から多国間対立へ

庄司智孝著『南シナ海問題の構図』が、『東南アジア研究』(第61巻第2号、2024年1月、京都大学東南アジア地域研究研究所発行)で紹介されました。中国の急速な台頭により国際政治の焦点となった危機の構造を、主要な当事者であるベトナム・フィリピンやASEANの動向をふまえて解明、非対称な大国と向きあう安全保障戦略をとらえ、米中対立の枠組みにはおさまらない紛争の力学を浮かび上がらせて、危機の行方を新たに展望します。
庄司智孝 著
税込5,940円/本体5,400円
A5判・上製・344頁
ISBN978-4-8158-1054-2 C3031
在庫有り
『図書新聞』 [2024年2月24日号、第3628号] から(評者:三木理史氏)
日本帝国圏鉄道史
技術導入から東アジアへ
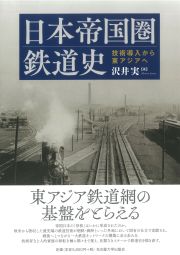
沢井実著『日本帝国圏鉄道史』が、『図書新聞』(2024年2月24日号、第3628号、武久出版発行)で紹介されました。帝国日本の「骨格」はいかに形成されたのか。欧米から吸収した最先端の鉄道技術が朝鮮・満洲といった外地において固有の仕方で実践され、戦後へとつながる一大鉄道ネットワークの構築に至る歩みを、技術者など人的資源の移転を軸に隅々まで捉え、比類なきスケールで鉄道史を描き直します。
沢井 実 著
税込6,380円/本体5,800円
A5判・上製・340頁
ISBN978-4-8158-1135-8 C3031
在庫有り
『国際法外交雑誌』 [第122巻第4号、2024年1月] から(評者:酒井哲哉氏)
国際法を編む
国際連盟の法典化事業と日本

高橋力也著『国際法を編む』が、『国際法外交雑誌』(第122巻第4号、2024年1月、国際法学会発行)で紹介されました。大国中心の法創造プロセスに風穴をあけ、初めて幅広い主体に国際法を開いた国際連盟の法典化事業。特に積極的な貢献をみせた日本を軸に、失敗とされたハーグ会議の意義を再評価、国益の追求にとどまらない法律家の実像を活写し、国際法の歴史を外交史的アプローチもふまえて描き直します。
“…… 第1に本書は、連盟における法典化事業をほぼ類例のない密度で論じた業績である。…… 本書は法典化事業を素材にすることで、連盟とワシントン体制の競合関係について新たな光をあてている。また、これまで総論的に言及されることはあっても、詳細な経緯は明らかにされてこなかったハーグ会議への道程を実証的に明らかにした点も貴重である。そして、本書の白眉ともいうべきハーグ会議の3つの委員会の重厚な分析は、本書が今後法典化事業に関する外交史的研究として不動の地位を占めるであろうことを予期させるものである。
第2に、本書が、戦間期日本の法的国際主義に関する内在的評価を可能にした点が挙げられる。…… 本書のように、平時国際法を中心にした法典化事業に焦点をあてることで、従来の研究では見えにくかった側面に光があてられたことの意義は少なくないだろう。また、法典化事業における法律家個人の役割や専門家共同体の存在を重視する点は、国際関係史の方法としても裨益するところが大きい。
第3に、本書は、戦間期日本の多国間外交の事例研究としても貴重な貢献をなしている。…… 争点に応じて多国間外交の場を利用してきた日本外務省のしたたかさも、本書から見えてくるのではないだろうか。……”(pp.190-191)
高橋力也 著
税込9,900円/本体9,000円
A5判・上製・546頁
ISBN978-4-8158-1111-2 C3032
在庫有り
『歴史評論』 [2024年2月号、第886号] から(評者:奥田俊介氏)
グローバル開発史
もう一つの冷戦
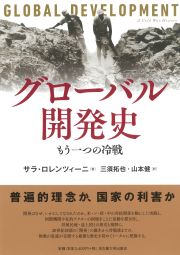
サラ・ロレンツィーニ著『グローバル開発史』(三須拓也・山本健訳)が、『歴史評論』(2024年2月号、第886号、歴史科学協議会発行)で紹介されました。開発はなぜ、いかにしてなされたのか。米・ソ・欧・中の対抗関係を軸にした実践と、国際機関や私的アクターの国境をこえた活動を描き出し、旧植民地・途上国との相克も視野に、20世紀初頭の「開発」の誕生から冷戦後までの、無数の思惑が交錯する複雑な歴史を初めてトータルに把握します。
“…… 評者がまずユニークだと感じたのは、…… ソ連以外の東側諸国と第三世界の関係を多く扱っている点である。…… 東側の視点からグローバル冷戦を理解するための格好の材料となるだろう。
また本書には、…… 英米以外の西側諸国の視点も多く盛り込まれている。…… さらに、…… 東西両陣営以外の国々の主体性および連関性を強調することに成功している。「東西対立」という伝統的冷戦像を壊し、東西両陣営の国々以外の多様なアクターに注目する必要性を改めて提示していると言えるだろう。……”(pp.109-110)
サラ・ロレンツィーニ 著
三須拓也・山本 健 訳
税込3,740円/本体3,400円
A5判・上製・384頁
ISBN978-4-8158-1090-0 C3022
在庫有り
『歴史評論』 [2023年7月号、第879号] から(評者:宮崎早季氏)
帝国のフロンティアをもとめて
日本人の環太平洋移動と入植者植民地主義
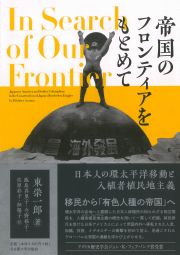
東栄一郎著『帝国のフロンティアをもとめて』(飯島真里子・今野裕子・佐原彩子・佃陽子訳)が、『歴史評論』(2023年7月号、第879号、歴史科学協議会発行)で紹介されました。環太平洋の各地へと展開した日本人移植民の知られざる相互関係を、入植者植民地主義の概念を用いて一貫して把握。移民排斥を受けた日系アメリカ人によって帝国内外へ移転された人流、知識、技術、イデオロギーの衝撃を初めて捉え、見過ごされたグローバルな帝国の連鎖を浮かび上がらせます。
“…… 特筆すべき本書の意義は、分野横断的に移民の歴史を描いたことである。その結果、本書はこれまで注目されることのなかった日本人移民の帝国的側面に光を当てることができた。…… 本書は、「日本の帝国主義は欧米の帝国主義と比較して、平和的であった」であるとか、「国際的な発展に寄与するものであった」とかいう評し方を見直し、そのような評し方をする現代日本にも、帝国主義的な考え方が残り続けていることを指摘する一冊である。……”(p.99、101)
東 栄一郎 著
飯島真里子・今野裕子・佐原彩子・佃 陽子 訳
税込5,940円/本体5,400円
A5判・上製・430頁
ISBN978-4-8158-1092-4 C3021
在庫有り
『歴史評論』 [2023年7月号、第879号] から(評者:仁藤將史氏)
日本綿業史
徳川期から日中開戦まで
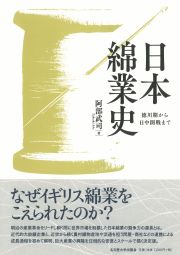
阿部武司著『日本綿業史』が、『歴史評論』(2023年7月号、第879号、歴史科学協議会発行)で紹介されました。明治の産業革命をリードし瞬く間に世界市場を制覇した日本綿紡績・織物業の競争力の源泉とは。近代的大紡績企業と、近世から続く農村織物産地や流通を担う問屋・商社などの連携による成長過程を初めて解明、衰退に向かう戦後も視野に、巨大産業の興隆を圧倒的な密度とスケールで描く決定版。
“…… 在来的な織物産地の検討を補完して、綿業全体の成長が近代産業と在来産業の併進によって支えられたという全体像を描くことに注力している。こうしたところに、本書の最大の功績が認められよう。…… 現時点における綿紡績業研究の到達点を示す、まさに金字塔であるといえる。”(pp.102-103)
阿部武司 著
税込7,920円/本体7,200円
A5判・上製・692頁
ISBN978-4-8158-1059-7 C3033
在庫有り
『ファイナンス』 [2024年2月号、第699号] から(評者:廣光俊昭氏)
財政規律とマクロ経済
規律の棚上げと遵守の対立をこえて

齊藤誠著『財政規律とマクロ経済』が、『ファイナンス』(2024年2月号、第699号、財務省発行)で紹介されました。日本経済の進む隘路を照らす ——。現状をどう考えればよいか、この先どうなるのか。過去30年間に陥った不可思議な均衡とその行方を初めて包括的に解明。戦中・敗戦直後の経験も踏まえた透徹した分析から、危機対応の方針を含め、政府・日銀のすべきこと/してはいけないことを明確に提示します。
齊藤 誠 著
税込4,950円/本体4,500円
A5判・上製・468頁
ISBN978-4-8158-1136-5 C3033
在庫有り
『歴史と経済』 [第262号、2024年1月] から(評者:中島裕喜氏)
輸出立国の時代
日本の軽機械工業とアメリカ市場

沢井実著『輸出立国の時代』が、『歴史と経済』(第262号、2024年1月、政治経済学・経済史学会発行)で紹介されました。戦後日本の復興を支え、高度成長を生み出した対米輸出への道は、いかにして切り拓かれていったのか? 自動車・家電に先駆けてアメリカを席捲したカメラ、ミシンなど軽機械の動向を初めて包括的に解明、労働集約型産業の変貌を現場からとらえて、今日に及ぶ発展を鮮やかに描き出します。
沢井 実 著
税込6,380円/本体5,800円
A5判・上製・296頁
ISBN978-4-8158-1099-3 C3033
在庫有り
「読売新聞」 [2024年2月11日付] から(評者:岡本隆司氏)
聖母の晩年
中世・ルネサンス期イタリアにおける図像の系譜
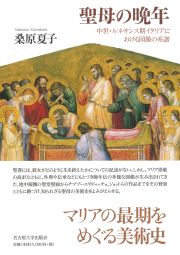
桑原夏子著『聖母の晩年』が、「読売新聞」(2024年2月11日付)読書欄で紹介されました。聖書には、彼女がどのように生を終えたかについての記述がない。しかし、マリア崇敬の高まりとともに、外典や伝承などにもとづき晩年伝の多様な図像が生み出されてきた。地中海圏の聖堂壁画からチマブーエやドゥッチョ、ジョットらの作品までをその背景とともに跡づけ、知られざる聖母の美術史をよみがえらせます。
“…… 数多の聖母晩年伝画像の周到緻密な論証でたどった一千年は、14世紀の転機とルネサンス以後の変動など、歴史家の描く史実過程に即応する。それなら被昇天への純化が、地中海の沈下と西欧の勃興、世界システムへの発展と並行するのも、そうなのか。マドンナはあらためて世界史を考えるよすがになりそうである。”(第18面)
桑原夏子 著
税込16,500円/本体15,000円
A5判・上製・904頁
ISBN978-4-8158-1141-9 C3071
在庫有り
『法と文化の制度史』 [第4号、2023年10月] から(評者:大中真氏)
国際法を編む
国際連盟の法典化事業と日本

高橋力也著『国際法を編む』が、『法と文化の制度史』(第4号、2023年10月、信山社発行)で紹介されました。大国中心の法創造プロセスに風穴をあけ、初めて幅広い主体に国際法を開いた国際連盟の法典化事業。特に積極的な貢献をみせた日本を軸に、失敗とされたハーグ会議の意義を再評価、国益の追求にとどまらない法律家の実像を活写し、国際法の歴史を外交史的アプローチもふまえて描き直します。
高橋力也 著
税込9,900円/本体9,000円
A5判・上製・546頁
ISBN978-4-8158-1111-2 C3032
在庫有り
朝日新聞 [2024年2月3日付、夕刊] から(評者:富永京子氏)
リヴァイアサンと空気ポンプ
ホッブズ、ボイル、実験的生活
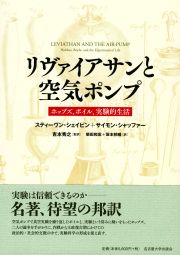
スティーヴン・シェイピン/サイモン・シャッファー著『リヴァイアサンと空気ポンプ』(吉本秀之監訳/柴田和宏・坂本邦暢訳)が、「朝日新聞」(2024年2月3日付)夕刊の「富永京子のモジモジ系時評」で紹介されました。実験で得られた知識は、信頼できるのか。空気ポンプで真空実験を繰り返したボイルと、実験という営みに疑いをもったホッブズ。二人の論争を手がかりに、内戦から王政復古期にかけての政治的・社会的文脈の中で、実験科学の形成を捉え直した名著。
スティーヴン・シェイピン/サイモン・シャッファー 著
吉本秀之 監訳/柴田和宏・坂本邦暢 訳
税込6,380円/本体5,800円
A5判・上製・454頁
ISBN978-4-8158-0839-6 C3040
在庫有り
『週刊東洋経済』 [2024年2月10日号] から(評者:河野龍太郎氏)
財政規律とマクロ経済
規律の棚上げと遵守の対立をこえて

齊藤誠著『財政規律とマクロ経済』が、『週刊東洋経済』(2024年2月10日号、東洋経済新報社発行)で紹介されました。日本経済の進む隘路を照らす ——。現状をどう考えればよいか、この先どうなるのか。過去30年間に陥った不可思議な均衡とその行方を初めて包括的に解明。戦中・敗戦直後の経験も踏まえた透徹した分析から、危機対応の方針を含め、政府・日銀のすべきこと/してはいけないことを明確に提示します。
齊藤 誠 著
税込4,950円/本体4,500円
A5判・上製・468頁
ISBN978-4-8158-1136-5 C3033
在庫有り
「朝日新聞」 [2024年2月2日付、文化欄] から
消え去る立法者
フランス啓蒙における政治と歴史

『消え去る立法者』の著者である王寺賢太先生が、「朝日新聞」(2024年2月2日付)の文化欄「混沌の先に 2024」に寄稿されました(「18世紀の啓蒙思想に学ぶこと 王寺賢太・東大教授に聞く」)。『消え去る立法者』を踏まえた論考となっています。【本書の内容】かつてこんなふうに読まれたことがあっただろうか ——。モンテスキューとルソー、そしてディドロへ。彼らが格闘し、解き明かし、残した問題とは何か。新たな共同体の創設という課題に直面し、法の根拠を問い直す重層的なテクストを読み抜き、「啓蒙」をクリシェから解き放った、気鋭の力作。
王寺賢太 著
税込6,930円/本体6,300円
A5判・上製・532頁
ISBN978-4-8158-1120-4 C3010
在庫有り
「UTokyo BiblioPlaza」 [2024年1月31日公開、自著紹介] から
カーシャーニー オルジェイトゥ史
イランのモンゴル政権イル・ハン国の宮廷年代記

大塚修・赤坂恒明・髙木小苗・水上遼・渡部良子訳註『カーシャーニー オルジェイトゥ史』の、大塚修先生による自著紹介が、「UTokyo BiblioPlaza」(2024年1月31日公開、東京大学)に掲載されました。モンゴル帝国を構成する政権の一つ、イル・ハン国に仕えた歴史家カーシャーニー。その手になるオルジェイトゥ治世の年代記は、『集史』以降の時代を扱い、大帝国の実像を伝えるとともに、ユーラシア各地の貴重な情報をも記録した第一級の史料である。詳細な解題・訳註を付した、ペルシア語史書初の日本語全訳。
大塚 修・赤坂恒明・髙木小苗・水上 遼・渡部良子 訳註
税込9,900円/本体9,000円
A5判・上製・516頁
ISBN978-4-8158-1105-1 C3022
在庫有り
『科学哲学』 [第56巻第1号、2023年11月] から(評者:原田雅樹氏)
統計力学の形成
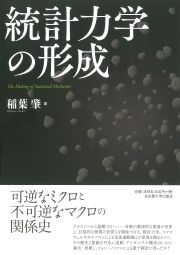
稲葉肇著『統計力学の形成』が、『科学哲学』(第56巻第1号、2023年11月、日本科学哲学会発行)で紹介されました。アナロジーから基礎づけへ ——。時間的に可逆であるミクロな多数の要素と、不可逆なマクロとを関係づける、統計力学。マクスウェルやボルツマンによる気体運動論との差異を踏まえつつ、その歴史と意義を丹念に追跡。アンサンブル概念はいかに誕生・発展し、フォン・ノイマンによる量子統計に到ったか?
稲葉 肇 著
税込6,930円/本体6,300円
A5判・上製・378頁
ISBN978-4-8158-1036-8 C3040
在庫有り
『経済セミナー』 [2024年2・3月号、736号] から
財政規律とマクロ経済
規律の棚上げと遵守の対立をこえて

齊藤誠著『財政規律とマクロ経済』が、『経済セミナー』(2024年2・3月号、736号、日本評論社発行)で紹介されました。日本経済の進む隘路を照らす ——。現状をどう考えればよいか、この先どうなるのか。過去30年間に陥った不可思議な均衡とその行方を初めて包括的に解明。戦中・敗戦直後の経験も踏まえた透徹した分析から、危機対応の方針を含め、政府・日銀のすべきこと/してはいけないことを明確に提示します。
齊藤 誠 著
税込4,950円/本体4,500円
A5判・上製・468頁
ISBN978-4-8158-1136-5 C3033
在庫有り
『図書新聞』 [2024年2月3日号、第3625号] から(評者:石井知章氏)
派閥の中国政治
毛沢東から習近平まで
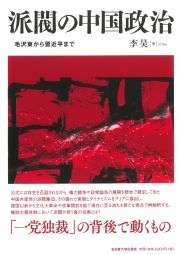
李昊著『派閥の中国政治』が、『図書新聞』(2024年2月3日号、第3625号、武久出版発行)で紹介されました。公式には存在を否認されながら、権力闘争や政策論争の展開を根本で規定してきた中国共産党の派閥集団。その隠れた実態とダイナミズムをクリアに描出し、建国以前から文化大革命や改革開放を経て現在に至る流れを新たな視点で再解釈する。権威主義体制において派閥が担う真の役割とは?
李 昊 著
税込6,380円/本体5,800円
A5判・上製・396頁
ISBN978-4-8158-1131-0 C3031
在庫有り
『週刊読書人』 [2023年11月17日号、第3515号] から(評者:西貝怜氏)
アニメ・エコロジー
テレビ、アニメーション、ゲームの系譜学
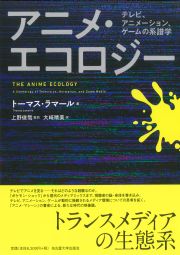
トーマス・ラマール著『アニメ・エコロジー』(上野俊哉監訳/大﨑晴美訳)が、『週刊読書人』(2023年11月17日号、第3515号、読書人発行)で紹介されました。テレビでアニメを見る —— それはどのような経験なのか。「ポケモン・ショック」から現代のメディアミックスまで、視聴者の脳・身体を巻き込み、テレビ、アニメーション、ゲームが動的に接続されるメディア環境についての思考を拓く。『アニメ・マシーン』の著者による、新たな時代の映像論。
トーマス・ラマール 著
上野俊哉 監訳/大﨑晴美 訳
税込6,930円/本体6,300円
A5判・上製・454頁
ISBN978-4-8158-1128-0 C3074
在庫有り
『図書新聞』 [2024年1月27日号、第3624号] から(評者:増田展大氏)
アニメ・エコロジー
テレビ、アニメーション、ゲームの系譜学
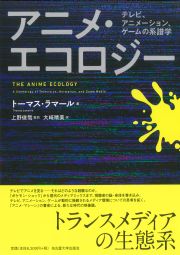
トーマス・ラマール著『アニメ・エコロジー』(上野俊哉監訳/大﨑晴美訳)が、『図書新聞』(2024年1月27日号、第3624号、武久出版発行)で紹介されました。テレビでアニメを見る —— それはどのような経験なのか。「ポケモン・ショック」から現代のメディアミックスまで、視聴者の脳・身体を巻き込み、テレビ、アニメーション、ゲームが動的に接続されるメディア環境についての思考を拓く。『アニメ・マシーン』の著者による、新たな時代の映像論。
トーマス・ラマール 著
上野俊哉 監訳/大﨑晴美 訳
税込6,930円/本体6,300円
A5判・上製・454頁
ISBN978-4-8158-1128-0 C3074
在庫有り
『月刊美術』 [2024年2月号] から
聖母の晩年
中世・ルネサンス期イタリアにおける図像の系譜
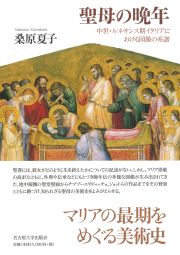
桑原夏子著『聖母の晩年』が、『月刊美術』(2024年2月号、サン・アート発行)で紹介されました。聖書には、彼女がどのように生を終えたかについての記述がない。しかし、マリア崇敬の高まりとともに、外典や伝承などにもとづき晩年伝の多様な図像が生み出されてきた。地中海圏の聖堂壁画からチマブーエやドゥッチョ、ジョットらの作品までをその背景とともに跡づけ、知られざる聖母の美術史をよみがえらせます。
桑原夏子 著
税込16,500円/本体15,000円
A5判・上製・904頁
ISBN978-4-8158-1141-9 C3071
在庫有り
「毎日新聞」 [2024年1月13日付] から(評者:加藤陽子氏)
軍国の文化 上・下
日清戦争・ナショナリズム・地域社会

羽賀祥二著『軍国の文化』が、「毎日新聞」(2024年1月13日付)で紹介されました。近代初の本格的対外戦争は、いかなる制度と心性のもとに遂行され、戦いと病いによる膨大な犠牲を社会はどのように受容したのか。動員体制の確立から、戦闘と占領地統治の様相、葬送・記念や仏教教団の活動まであまねく探究、「大量死の時代」が生んだ戦争協同体の構造を解明します。
“…… 記述の対象は文化である。動画がない時代にあって、戦勝祭典や慰霊行事を紙上に再現する苦労はいかばかりか。写真、絵画、新聞記事、中央・地方間の往復文書、手紙等の私文書が総動員されるゆえんだ。なかでも、愛知県内で確認される195の日清戦争記念碑について、名称、所在地、碑文の揮毫者・撰文の執筆者を載せた一覧表には圧倒される。
著者の視角の冴えは、碑文に刻まれた撰文の戦争観の分析からもわかる。それは、日本軍を文明の使徒、義軍として描き、朝鮮・清国を文明に導くことが日本の天職だとの認識で共通していた。第三師団は犠牲を最も多く出した師団であり、地域社会における招魂や慰霊が特に真剣になされたのだろう。著者の姿勢を示す一文を引く。『社会全体から見れば、多くの戦病死者は無名の存在であった。…… しかし、戦病死した兵卒は、自己の出身の町や村では決して無名ではない。生まれた家があり、彼を取りまく地域があった』……”(第14面)
羽賀祥二 著
上 税込6,930円/本体6,300円
下 税込8,030円/本体7,300円
A5判・上製・上478頁+下640頁
ISBN 上:978-4-8158-1137-2 下:978-4-8158-1138-9
C3021
在庫有り
「読売新聞」 [2024年1月14日付] から(評者:岡本隆司氏)
日本帝国圏鉄道史
技術導入から東アジアへ
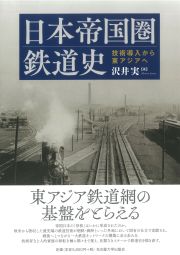
沢井実著『日本帝国圏鉄道史』が、「読売新聞」(2024年1月14日付)で紹介されました。帝国日本の「骨格」はいかに形成されたのか。欧米から吸収した最先端の鉄道技術が朝鮮・満洲といった外地において固有の仕方で実践され、戦後へとつながる一大鉄道ネットワークの構築に至る歩みを、技術者など人的資源の移転を軸に隅々まで捉え、比類なきスケールで鉄道史を描き直します。
“…… 徹底してヒトとモノ、専門技術と開発製作に密着して史実を紡ぎ出す。歴史にありがちな抽象概念はほとんどない。それにしても技術者の業績・経歴から企業・工場の組織・経営、個別技術の習得から実地の適用、設計・工事の経過から車輌の型番に至るまで、ここまで精細にわかるのか、と開いた口がふさがらなかった。……”(第31面)
沢井 実 著
税込6,380円/本体5,800円
A5判・上製・340頁
ISBN978-4-8158-1135-8 C3021
在庫有り
『化学史研究』 [第50巻第4号、2023年12月] から(評者:田中祐理子氏)
ツベルクリン騒動
明治日本の医と情報
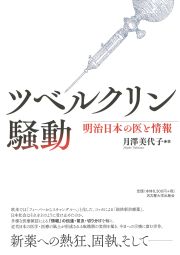
月澤美代子著『ツベルクリン騒動』が、『化学史研究』(第50巻第4号、2023年12月、化学史学会発行)で紹介されました。欧米では「フィーバーからスキャンダルへ」と化した、コッホによる「結核新治療薬」。日本社会はそれをどのように受け止めたのか。多様な医療雑誌による「情報」の伝達・普及・切り分けを軸に、近代日本の医学・医療の風土が形成される転換期の実相を描き、今日への示唆に富む労作。
“…… 本書から学ぶことのできる歴史叙述の視座は、私たちが現在体験している、そして「終息」するかのように動いている Covid-19 の「歴史」を記録するためにも、必ず有効なものであるだろう。「地の利」と「科学」だけが作用するなら決して生じえない「熱狂」と「騒動」を、そしてときに黒塗りされる記録のようなものを生み出すものが、いまもなお目の前で動き続けていることを思わずに、本書を読むことは評者にはできなかった。”(p.44)
月澤美代子 著
税込6,930円/本体6,300円
A5判・上製・504頁
ISBN978-4-8158-1101-3 C3021
在庫有り
『人民の歴史学』 [第236号、2023年6月] から(評者:千葉正史氏)
愛国とボイコット
近代中国の地域的文脈と対日関係
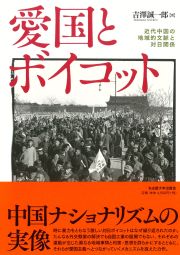
吉澤誠一郎著『愛国とボイコット』が、『人民の歴史学』(第236号、2023年6月、東京歴史科学研究会編)で紹介されました。中国ナショナリズムの実像 ——。時に暴力をともなう激しい対日ボイコットはなぜ繰り返されたのか。たんなる外交懸案の解決でも自国工業の振興でもない、それぞれの運動が生じた異なる地域事情と利害・思想を詳らかにするとともに、それらが愛国主義へとつながっていくメカニズムを捉えた力作。
“…… 本来ボイコットによる非暴力的な「文明抵制」を標榜した20世紀前半の愛国運動は、国民党と共産党の主導のもとで戦闘的な革命運動へと転化していくこととなったのであるが、そうした道筋を旧来のステレオタイプな見解にとらわれることなく実証的に見通しを示したところに、こうした古典的なテーマをあらためて今日に取り上げた本書の最も大きな価値が存在すると思われる。……”(p.36)
吉澤誠一郎 著
税込4,950円/本体4,500円
A5判・上製・314頁
ISBN978-4-8158-1048-1 C3022
在庫有り
『ゲシヒテ』 [第16号、2023年4月] から(評者:林田敏子氏)
戦争障害者の社会史
20世紀ドイツの経験と福祉国家
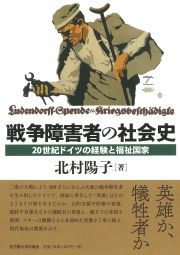
北村陽子著『戦争障害者の社会史』が、『ゲシヒテ』(第16号、2023年4月、ドイツ現代史研究会発行)で紹介されました。二度の大戦により、300万人におよぶ大量の戦争障害者を生み出したドイツで、国家に奉仕した「英雄」はどのようなその後を生きたのか。公的支援や医療の発達、義肢や盲導犬などの補助具の発展と、他方での差別や貧困、ナチへの傾倒などの多面的な実態を丁寧に描き、現代福祉の淵源を示します。
“…… 特殊なナチ党統治期も含め19世紀半ばから20世紀半ばまでの約百年を視野におさめた本書は、戦争障害者という観点からみたドイツ福祉国家形成史としてだけでなく、この時代の国家や社会のあり方を通史として描き出したドイツ現代史として読むことができる。対象は戦争と福祉にとどまらず、医療、技術革新、教育、職業訓練、家族、ジェンダー、身体、スポーツと多岐に渡っている。二重の意味で周縁化された精神障害者への着目は、本書の議論に厚みを与えているだけでなく、特殊なナチ党統治期をとらえる切り口としても有効に機能している。……”(p.82)
北村陽子 著
税込5,940円/本体5,400円
A5判・上製・366頁
ISBN978-4-8158-1017-7 C3022
在庫有り
『オリエント』 [第66巻第1号、2023年] から(評者:矢島洋一氏)
カーシャーニー オルジェイトゥ史
イランのモンゴル政権イル・ハン国の宮廷年代記

大塚修・赤坂恒明・髙木小苗・水上遼・渡部良子訳註『カーシャーニー オルジェイトゥ史』が、『オリエント』(第66巻第1号、2023年、日本オリエント学会発行)で紹介されました。モンゴル帝国を構成する政権の一つ、イル・ハン国に仕えた歴史家カーシャーニー。その手になるオルジェイトゥ治世の年代記は、『集史』以降の時代を扱い、大帝国の実像を伝えるとともに、ユーラシア各地の貴重な情報をも記録した第一級の史料である。詳細な解題・訳註を付した、ペルシア語史書初の日本語全訳。
大塚 修・赤坂恒明・髙木小苗・水上 遼・渡部良子 訳註
税込9,900円/本体9,000円
A5判・上製・516頁
ISBN978-4-8158-1105-1 C3022
在庫有り
『朝鮮族研究学会誌』 [第13号、2023年12月] から
「満洲国」以後
中国工業化の源流を考える
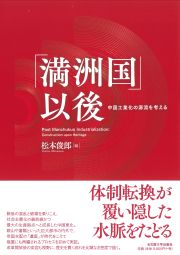
朝鮮族研究学会で開催された、松本俊郎編『「満洲国」以後』の書評会の報告録が、『朝鮮族研究学会誌』(第13号、2023年12月、朝鮮族研究学会編)に掲載されました。戦後の混乱と破壊を乗りこえ、社会主義化の最前線かつ最大の生産拠点へと成長した中国東北。鞍山や瀋陽といった巨大都市の内外で、帝国支配の「遺産」が時代をこえて幾重にも再編されるプロセスを初めて実証。改革開放後の変容も視野に、歴史を貫く流れを比類なき密度で描きます。
松本俊郎 編
税込6,380円/本体5,800円
A5判・上製・358頁
ISBN978-4-8158-1114-3 C3033
在庫有り
「ブックトーク・オン・アジア」 [第76回、2023年12月27日配信、著者インタビュー]
都市化の中国政治
土地取引の展開と多元化する社会
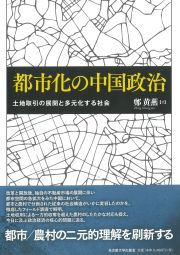
『都市化の中国政治』の著者である鄭黄燕先生が出演された、「ブックトーク・オン・アジア」(第76回、2023年12月27日、京都大学東南アジア地域研究研究所)が配信されました。
鄭 黄燕 著
税込5,940円/本体5,400円
A5判・上製・268頁
ISBN978-4-8158-1133-4 C3031
在庫有り
『大原社会問題研究所雑誌』 [第783号、2024年1月] から(評者:坂井晃介氏)
失業を埋めもどす
ドイツ社会都市・社会国家の模索
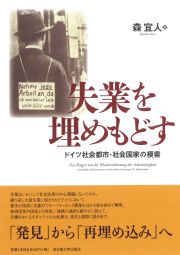
森宜人著『失業を埋めもどす』が、『大原社会問題研究所雑誌』(第783号、2024年1月、法政大学大原社会問題研究所発行)で紹介されました。失業はいかにして発見され、社会政策の中心課題になったのか。繰り返し大量失業に悩まされたドイツにおいて、都市が国家に先駆けてセーフティネット構築をはかる姿を初めて解明、慈善団体や国家との対抗/連携の過程も鮮やかに捉えて、労働をめぐるモダニティの大転換を、現代も視野に描き出します。
“…… 各種未公刊史料および公刊史料の丹念かつ子細な収集・分析により、ドイツ失業者救済の重層的構造を一貫した理論的視座から析出した、都市史研究の最前線の成果かつスケールの大きい著作である。…… ハンブルクにおける都市自治体と民間の諸アクター(使用者組合・労働組合・民間慈善団体など)との絡まり合いや、都市自治体とライヒの関係、労働市場によるジェンダー構造などの変遷を詳細に描き、ライヒ失業保険に代表される国家レベルでの政策アウトプット以前/以後に存在した制度的な網の目を、実証的かつ子細に浮かび上がらせている点で意義深い。……”(pp.71-72)
森 宜人 著
税込7,480円/本体6,800円
A5判・上製・396頁
ISBN978-4-8158-1103-7 C3022
在庫有り
「読売新聞」 [2023年12月24日付、特集「読書委員が選ぶ『2023年の3冊』」] から(評者:遠藤乾氏)
消え去る立法者
フランス啓蒙における政治と歴史

王寺賢太著『消え去る立法者』が、「読売新聞」(2023年12月24日付)読書欄の特集「読書委員が選ぶ『2023年の3冊』」で紹介されました。かつてこんなふうに読まれたことがあっただろうか ——。モンテスキューとルソー、そしてディドロへ。彼らが格闘し、解き明かし、残した問題とは何か。新たな共同体の創設という課題に直面し、法の根拠を問い直す重層的なテクストを読み抜き、「啓蒙」をクリシェから解き放った、気鋭の力作。
“王寺の本は、今年の一冊にあげるのでは済まない。おそらく四半世紀見渡しても、トップの数冊に入る水準。モンテスキューやルソーの仏語原典をここまで深く読み、日本語であそこまで多角的に、そして雄弁に再構成できる論者を他に知らない。社会や政治の始源にさかのぼるのだ。読者は急いではいけない。DX の時代にわざとゆっくり、じっくり文に付き合う構えが必要だ。そんな読者を、本書は決して裏切らない。”(遠藤乾氏評、第23面)
王寺賢太 著
税込6,930円/本体6,300円
A5判・上製・532頁
ISBN978-4-8158-1120-4 C3010
在庫有り
「『博論本』を聴く」から
哲学者たちの天球
スコラ自然哲学の形成と展開

『哲学者たちの天球』の著者であるアダム・タカハシ先生のインタビューが、「『博論本』を聴く」(斎藤哲也氏、DISTANCE.media)で公開されました。「読書としての哲学史 —— アリストテレスの〈註解〉から浮かび上がる中世の自然哲学」。【本書の内容】宇宙の原理をめぐるハイブリッドな「知」の生成を描く——。科学革命までの学問を一千年以上にわたり支配したアリストテレス主義。アラビア哲学を介して発展させられた、天と大地をめぐる教説とはいかなるものであり、キリスト教世界の中でどのように受け止められたのか。言語と文明圏をまたいだ自然哲学の展開を、つぶさに解明した気鋭の力作。
アダム・タカハシ 著
税込6,380円/本体5,800円
A5判・上製・318頁
ISBN978-4-8158-1100-6 C3010
在庫有り
「朝日新聞」 [2023年12月23日付、特集「書評委員の『今年の3点』」] から(評者:藤田結子氏)
アメリカの人種主義
カテゴリー/アイデンティティの形成と転換
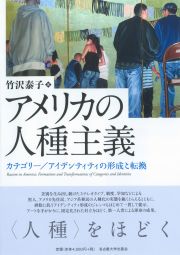
竹沢泰子著『アメリカの人種主義』が、「朝日新聞」(2023年12月23日付)読書欄の特集「書評委員の『今年の3点』」で紹介されました。差別を生み出し続けたステレオタイプ、制度、学知などによる黒人、アメリカ先住民、アジア系移民の人種化の実態を鋭くとらえるとともに、排除に抗うアイデンティティ形成のジレンマもはじめて一貫して提示、アートを手がかりに、固定化された対立をほどく、第一人者による渾身の成果。
“…… 日系・アジア系を中心に人種に関する研究を第一線で行ってきた著者の集大成。あとがきで著者は、子育てや介護で苦しい時期を乗り越え研究に専心できたと振り返る。……”(藤田結子氏評、第20面)
竹沢泰子 著
税込4,950円/本体4,500円
A5判・上製・516頁
ISBN978-4-8158-1118-1 C3022
在庫有り
「日本経済新聞」 [2023年12月23日付、特集「エコノミストが選ぶ 経済図書ベスト10」] から
財政規律とマクロ経済
規律の棚上げと遵守の対立をこえて

齊藤誠著『財政規律とマクロ経済』が、「日本経済新聞」(2023年12月23日付)読書欄の特集「エコノミストが選ぶ 経済図書ベスト10」に選ばれました。日本経済の進む隘路を照らす ——。現状をどう考えればよいか、この先どうなるのか。過去30年間に陥った不可思議な均衡とその行方を初めて包括的に解明。戦中・敗戦直後の経験も踏まえた透徹した分析から、危機対応の方針を含め、政府・日銀のすべきこと/してはいけないことを明確に提示します。
“…… マクロ経済学の視点から、分析と理論の力によって「日本経済の再出発を図る方策」を示す。政府の「借りっぱなし」状態からの脱却と危機対応マニュアルの準備を提言。再起に向けて、「財政規律がいかに重要かを説得的に論じている」(土居丈朗・慶大教授)。……”(第29面)
齊藤 誠 著
税込4,950円/本体4,500円
A5判・上製・468頁
ISBN978-4-8158-1136-5 C3033
在庫有り
『アジア経済』 [第64巻第4号、2023年12月] から(評者:丁可氏)
中国国有企業の政治経済学
改革と持続
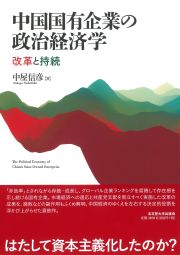
中屋信彦著『中国国有企業の政治経済学』が、『アジア経済』(第64巻第4号、2023年12月、アジア経済研究所発行)で紹介されました。非効率なはずの企業群はなぜ存続し、成長できたのか。グローバル企業ランキングを席捲し、存在感を示し続ける国有企業が、市場経済への適応と共産党支配を両立すべく実施した改革の成果を、腐敗などの副作用も含め解明、「普通の」資本主義体制に抗いながら発展する中国経済の実像に迫ります。
中屋信彦 著
税込6,930円/本体6,300円
A5判・上製・366頁
ISBN978-4-8158-1095-5 C3033
在庫有り
「国際社会経済研究所 公式note」 [2023年12月18日公開] から
宇宙開発をみんなで議論しよう

『宇宙開発をみんなで議論しよう』の編者の一人・呉羽真先生のインタビューが、国際社会経済研究所の公式note(2023年12月18日)で公開されました。【本書の内容】有人宇宙探査の新たな計画、商業化、軍事化、新興国の台頭 …… 近年、宇宙開発は大きく転換しつつある。市民がそこに関わる必要性をわかりやすく説き、そのための基礎知識や科学技術コミュニケーションの手法、議論のスキルを提供する初めての本。
呉羽 真・伊勢田哲治 編
税込2,970円/本体2,700円
A5判・上製・256頁
ISBN978-4-8158-1091-7 C3040
在庫有り
『週刊ダイヤモンド』 [2023年12月23日・30日新年合併特大号] から
『週刊ダイヤモンド』(2023年12月23日・30日新年合併特大号、ダイヤモンド社発行)の特集「経済学者・経営学者・エコノミスト123人が選んだ 2023年『ベスト経済書』」(全29点)に、以下の図書が選ばれました。
金井雄一著『中央銀行はお金を創造できるか —— 信用システムの貨幣史』
藤田菜々子著『社会をつくった経済学者たち —— スウェーデン・モデルの構想から展開へ』
『図書新聞』 [2023年12月23日号、第3620号、特集「23年下半期読書アンケート」] から(評者:岩川ありさ氏)
口述筆記する文学
書くことの代行とジェンダー
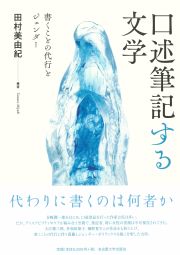
田村美由紀著『口述筆記する文学』が、『図書新聞』(2023年12月23日号、第3620号、武久出版発行)の特集「23年下半期読書アンケート」で紹介されました。谷崎潤一郎をはじめ、口述筆記を行った作家は実は多い。だが、ディスアビリティやケアが絡み合う空間で、筆記者、特に女性の役割は不可視化されてきた。大江健三郎、多和田葉子、桐野夏生らの作品をも取り上げ、書くことの代行に伴う葛藤とジェンダー・ポリティクスを鋭く分析した力作。
“……「口述筆記」という観点から、ジェンダー批評、クィア批評の新しい可能性を引き出した。……”(第1面)
田村美由紀 著
税込6,380円/本体5,800円
A5判・上製・318頁
ISBN978-4-8158-1129-7 C3095
在庫有り
「日経BOOKプラス」 [2023年12月12日公開] から(評者:前田裕之氏)
財政規律とマクロ経済
規律の棚上げと遵守の対立をこえて

齊藤誠著『財政規律とマクロ経済』が、「日経BOOKプラス」(2023年12月12日公開、日経BP)で紹介されました。日本経済の進む隘路を照らす ——。現状をどう考えればよいか、この先どうなるのか。過去30年間に陥った不可思議な均衡とその行方を初めて包括的に解明。戦中・敗戦直後の経験も踏まえた透徹した分析から、危機対応の方針を含め、政府・日銀のすべきこと/してはいけないことを明確に提示します。
齊藤 誠 著
税込4,950円/本体4,500円
A5判・上製・468頁
ISBN978-4-8158-1136-5 C3033
在庫有り
『政經研究』 [121号、2023年12月] から(評者:建部正義氏)
中央銀行はお金を創造できるか
信用システムの貨幣史
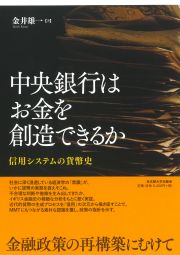
金井雄一著『中央銀行はお金を創造できるか』が、『政經研究』(121号、2023年12月、政治経済研究所発行)で紹介されました。社会に深く浸透している経済学の「常識」が、いかに貨幣の実態を捉えそこね、不合理な判断や施策を生み出してきたか、イギリス金融史の精緻な分析をもとに鋭く実証。近代的貨幣の生成プロセスを「信用」の次元から描き直すことで、MMT にもつながる素朴な認識を覆し、政策の指針を示します。
金井雄一 著
税込5,940円/本体5,400円
A5判・上製・234頁
ISBN978-4-8158-1125-9 C3033
在庫有り
『上智史學』 [第68号、2023年11月] から(評者:苅米一志氏)
狩猟と権力
日本中世における野生の価値
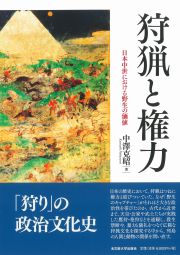
中澤克昭著『狩猟と権力』が、『上智史學』(第68号、2023年11月、上智大学史学研究会発行)で紹介されました。日本の歴史において、狩猟はつねに権力と結びついていた。なぜ「野生のキャプチャー」がそれほど大きな政治性を帯びたのか。古代から近世まで、天皇・公家や武士たちが実践した鷹狩・巻狩などを通観し、殺生禁断や、暴力と儀礼をつなぐ広範な狩猟文化を探究する中から、列島の人間と動物の関係を問い直す。
中澤克昭 著
税込7,480円/本体6,800円
A5判・上製・484頁
ISBN978-4-8158-1106-8 C3021
在庫有り
『鎌倉遺文研究』 [第51号、2023年4月] から(評者:下村周太郎氏)
狩猟と権力
日本中世における野生の価値
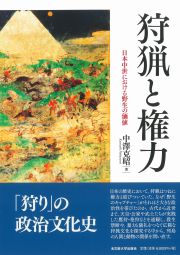
中澤克昭著『狩猟と権力』が、『鎌倉遺文研究』(第51号、2023年4月、鎌倉遺文研究会発行)で紹介されました。日本の歴史において、狩猟はつねに権力と結びついていた。なぜ「野生のキャプチャー」がそれほど大きな政治性を帯びたのか。古代から近世まで、天皇・公家や武士たちが実践した鷹狩・巻狩などを通観し、殺生禁断や、暴力と儀礼をつなぐ広範な狩猟文化を探究する中から、列島の人間と動物の関係を問い直す。
中澤克昭 著
税込7,480円/本体6,800円
A5判・上製・484頁
ISBN978-4-8158-1106-8 C3021
在庫有り
『週刊金融財政事情』 [2023年11月28日号、第74巻第44号] から(評者:板谷敏彦氏)
財政規律とマクロ経済
規律の棚上げと遵守の対立をこえて

齊藤誠著『財政規律とマクロ経済』が、『週刊金融財政事情』(2023年11月28日号、第74巻第44号、金融財政事情研究会発行)で紹介されました。日本経済の進む隘路を照らす ——。現状をどう考えればよいか、この先どうなるのか。過去30年間に陥った不可思議な均衡とその行方を初めて包括的に解明。戦中・敗戦直後の経験も踏まえた透徹した分析から、危機対応の方針を含め、政府・日銀のすべきこと/してはいけないことを明確に提示します。
“…… 来るべき変動への警告書であるとともに、金融制度や政策などの知見の宝庫だ。われわれは漠然とした不安に支配されることなく、正しくリスクを認識し備えるべきである。”(p.10)
齊藤 誠 著
税込4,950円/本体4,500円
A5判・上製・468頁
ISBN978-4-8158-1136-5 C3033
在庫有り
『日本近代文学』 [第109集、2023年11月] から(評者:川口隆行氏)
戦後表現
Japanese Literature after 1945

坪井秀人著『戦後表現』が、『日本近代文学』(第109集、2023年11月、日本近代文学会発行)で紹介されました。アジア太平洋戦争から冷戦、昭和の終わり、湾岸・イラク戦争、ポスト3・11まで、戦争をめぐる言葉がすくい上げてきたもの、底に沈めてきたものを、詩・小説・批評を中心に精緻に読解。経験や記憶に刻まれた〈傷跡〉としての表現の重層性から、〈戦後〉概念を再審にかけます。
坪井秀人 著
税込6,930円/本体6,300円
A5判・上製・616頁
ISBN978-4-8158-1116-7 C3095
在庫有り
『名古屋大学国語国文学』 [第116号、2023年11月] から(評者:藤田祐史氏)
戦後表現
Japanese Literature after 1945

坪井秀人著『戦後表現』が、『名古屋大学国語国文学』(第116号、2023年11月、名古屋大学国語国文学会編)で紹介されました。アジア太平洋戦争から冷戦、昭和の終わり、湾岸・イラク戦争、ポスト3・11まで、戦争をめぐる言葉がすくい上げてきたもの、底に沈めてきたものを、詩・小説・批評を中心に精緻に読解。経験や記憶に刻まれた〈傷跡〉としての表現の重層性から、〈戦後〉概念を再審にかけます。
坪井秀人 著
税込6,930円/本体6,300円
A5判・上製・616頁
ISBN978-4-8158-1116-7 C3095
在庫有り
「ディスカバー・ニッケイ」 [2023年11月10日公開] から(評者:川井龍介氏)
アメリカの人種主義
カテゴリー/アイデンティティの形成と転換
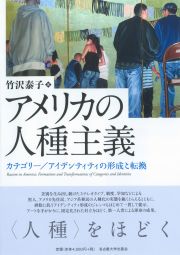
竹沢泰子著『アメリカの人種主義』が、「ディスカバー・ニッケイ」(2023年11月10日公開、全米日系人博物館)で紹介されました。差別を生み出し続けたステレオタイプ、制度、学知などによる黒人、アメリカ先住民、アジア系移民の人種化の実態を鋭くとらえるとともに、排除に抗うアイデンティティ形成のジレンマもはじめて一貫して提示、アートを手がかりに、固定化された対立をほどく、第一人者による渾身の成果。
竹沢泰子 著
税込4,950円/本体4,500円
A5判・上製・516頁
ISBN978-4-8158-1118-1 C3022
在庫有り
『中国経済経営研究』 [第7巻第2号、2023年10月] から(評者:甲斐成章氏)
中国国有企業の政治経済学
改革と持続
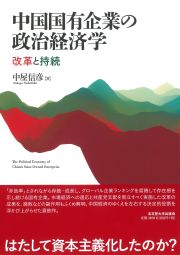
中屋信彦著『中国国有企業の政治経済学』が、『中国経済経営研究』(第7巻第2号、2023年10月、中国経済経営学会発行)で紹介されました。非効率なはずの企業群はなぜ存続し、成長できたのか。グローバル企業ランキングを席捲し、存在感を示し続ける国有企業が、市場経済への適応と共産党支配を両立すべく実施した改革の成果を、腐敗などの副作用も含め解明、「普通の」資本主義体制に抗いながら発展する中国経済の実像に迫ります。
中屋信彦 著
税込6,930円/本体6,300円
A5判・上製・366頁
ISBN978-4-8158-1095-5 C3033
在庫有り
『日本近代文学』 [第109集、2023年11月] から(評者:山田俊治氏)
変革する文体
もう一つの明治文学史

木村洋著『変革する文体』が、『日本近代文学』(第109集、2023年11月、日本近代文学会発行)で紹介されました。新たな文体は新たな社会をつくる ——。小説中心主義を脱し、政論・史論から翻訳・哲学まで、徳富蘇峰を起点にして近代の「文」の歩みを辿りなおし、新興の洋文脈と在来の和文脈・漢文脈の交錯から、それまでにない人間・社会像や討議空間が形づくられる道程をつぶさに描いた意欲作。
木村 洋 著
税込6,930円/本体6,300円
A5判・上製・358頁
ISBN978-4-8158-1108-2 C3095
在庫有り
「日本経済新聞」 [2023年11月16日付、夕刊、「あすへの話題」(根井雅弘氏)] から
イギリス思想家書簡集 アダム・スミス

篠原久・只腰親和・野原慎司訳『イギリス思想家書簡集 アダム・スミス』(シリーズ監修者 田中秀夫・坂本達哉)が、「日本経済新聞」(2023年11月16日付)夕刊の「あすへの話題」で紹介されました(「哲学者の茶目っ気」根井雅弘氏)。親密圏と公共圏のあいだで、知的コミュニケーションの場として決定的位置をしめた手紙。知られざる論点、新たなアイディアが書物とは異なるかたちで問いかけられ表明され、人々を動かしていく。『国富論』など主著には現れない見解からヒュームとの交友まで、精彩に富むスミス書簡の初の全訳。
篠原 久・只腰親和・野原慎司 訳
(シリーズ監修者 田中秀夫・坂本達哉)
税込6,930円/本体6,300円
A5判・上製・502頁
ISBN978-4-8158-1107-5 C3010
在庫有り
『週刊読書人』 [2023年11月3日号、第3513号] から(評者:関智英氏)
派閥の中国政治
毛沢東から習近平まで
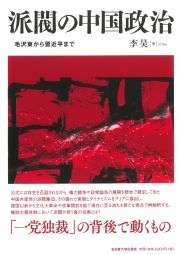
李昊著『派閥の中国政治』が、『週刊読書人』(2023年11月3日号、第3513号、読書人発行)で紹介されました。公式には存在を否認されながら、権力闘争や政策論争の展開を根本で規定してきた中国共産党の派閥集団。その隠れた実態とダイナミズムをクリアに描出し、建国以前から文化大革命や改革開放を経て現在に至る流れを新たな視点で再解釈します。権威主義体制において派閥が担う真の役割とは?
“…… 叙述は具体的で、政治学の素人でも読んでいて飽きることがない。結果として本書は良質な中国共産党史ともなっている。”(第3面)
李 昊 著
税込6,380円/本体5,800円
A5判・上製・396頁
ISBN978-4-8158-1131-0 C3031
在庫有り
『歴史と経済』 [第66巻第1号、2023年10月] から(評者:伊丹一浩氏)
村の公証人
近世フランスの家政書を読む
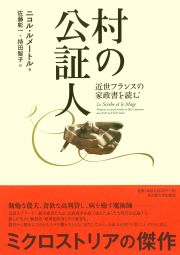
ニコル・ルメートル著『村の公証人』(佐藤彰一・持田智子訳)が、『歴史と経済』(第66巻第1号、2023年10月、政治経済学・経済史学会発行)で紹介されました。勤勉な農夫、貪欲な高利貸し、病を癒す魔術師 ——。公証人テラード一族の家長たちは、宗教戦争を経て訪れたあらたな時代を記録する。彼らが生きた物質的・精神的世界とその変容を、農村から都市にひろがる人々の繫がりとともに活写しながら、公証人が持つ「書くこと」の力に迫ります。
ニコル・ルメートル 著
佐藤彰一・持田智子 訳
税込6,380円/本体5,800円
A5判・上製・380頁
ISBN978-4-8158-1089-4 C3022
在庫有り
『図書新聞』 [2023年11月4日号、第3613号] から(評者:泉谷瞬氏)
口述筆記する文学
書くことの代行とジェンダー
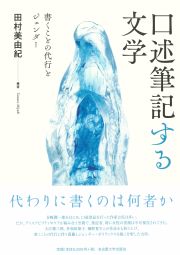
田村美由紀著『口述筆記する文学』が、『図書新聞』(2023年11月4日号、第3613号、武久出版発行)で紹介されました。谷崎潤一郎をはじめ、口述筆記を行った作家は実は多い。だが、ディスアビリティやケアが絡み合う空間で、筆記者、特に女性の役割は不可視化されてきた。大江健三郎、多和田葉子、桐野夏生らの作品をも取り上げ、書くことの代行に伴う葛藤とジェンダー・ポリティクスを鋭く分析した力作。
“…… 本書が提示する「ケア・ライティング」という視座は、かつては自明視されていた「書くこと」の定義を刷新する。それは突き詰めれば、この世に存在する(そして未だ存在していない)あらゆる「書かれたもの」についての、私たちの常套的な見方を一変させてくれる。”(第1面)
田村美由紀 著
税込6,380円/本体5,800円
A5判・上製・318頁
ISBN978-4-8158-1129-7 C3095
在庫有り
『日経サイエンス』 [2023年12月号] から(評者:丸山隆一氏)
『日経サイエンス』(2023年12月号、日系サイエンス社発行)の「ブックレビュー」で、以下の図書が紹介されました(いずれも丸山隆一氏評)。
大塚淳著『統計学を哲学する』
“…… 科学の最も基本的なツールである統計学を哲学的に分析する。ベイズ統計、仮説検定、機械学習、因果推論などの統計学的手法を科学者が使うとき、何が暗黙の前提となり、何が正当化の根拠になっているのか。哲学的認識論の道具立てによる本書の整理は鮮やかだ。深層学習に関する議論は、どのような意味で AI に科学ができるのかという大問題にもつながる。「AI 科学の哲学」の始動を感じる。……”(pp.107-108)
吉澤剛著『不定性からみた科学 —— 開かれた研究・組織・社会のために』
“…… そもそもなぜ人は科学をするのか。科学で何がわかるのか。成果はどのように利用されるのか。副作用はないのか。誰が責任をとるのか。科学者はどう評価されるのか。科学がもたらす価値とは何か ……。『不定性からみた科学』は、科学と社会に関するそうした問いと向き合ってきた科学技術社会論や科学技術政策論の蓄積を丸ごと学べる一冊だ。ただし、本書はそのすべてを「不定性」、つまり「分からなさ」から語る。科学の成果や役割や価値は本質的に不定であり、対話を通して見いだすしかない。科学の「あるべき論」に関するどんな歯切れが良い主張も、本書の精度には届かないはず。……”(p.108)
『科学史研究』 [2023年10月号、第Ⅲ期 第62巻第307号] から(評者:永島昂氏)
技能形成の戦後史
工場と学校をむすぶもの

沢井実著『技能形成の戦後史』が、『科学史研究』(2023年10月号、第Ⅲ期 第62巻第307号、日本科学史学会発行)で紹介されました。高度成長期の高校進学率上昇が職業教育・職業訓練に与えたインパクトとは? 企業内養成施設、公共職業訓練所、工業高校、各種学校などで起こった劇的な変遷を分析。「役に立つ」「即戦力」を歴史的に問い直し、実践に根ざした教養教育を考えます。
“…… 戦後の産業構造の変化、継起的な技術革新、職種の増加、進学率と労働市場の変容に応答しつつ、職業人を輩出してきた教育訓練施設の努力を正当に評価し、史資料に依拠して通史的に描かれたことが本書の最大の功績である。……
戦後史においては OJT と座学という関係は、職業教育と教養教育という関係へと継承されることになった。ところが、戦後の多能工教育思想を支えてきた教養は次第に職業世界との関係を希薄化させ、高校そして大学進学のための一般教育・教養教育へとその内実を変化させてしまったとする主張は説得的である。「製造業の強さを生み出したもの」の根底に「職業人としての教養」があったという評者の解釈に従えば、本書は「製造業の強さ」が現在、足元から揺らぎつつあると警鐘を鳴らしている本でもあると考えられる。大学「全入」時代の技能形成のあり方、教養のあり方がいま問われている。……”(p.311)
沢井 実 著
税込5,940円/本体5,400円
A5判・上製・258頁
ISBN978-4-8158-1038-2 C3033
在庫有り
「日本経済新聞」 [2023年10月24日付、「経済教室」] から
財政規律とマクロ経済
規律の棚上げと遵守の対立をこえて

『財政規律とマクロ経済』の著者である齊藤誠先生が、「日本経済新聞」(2023年10月24日付)の「経済教室」に寄稿されました(「財政・金融政策の針路 中 正常化は拙速避け慎重に」)。より詳細な議論が、本書『財政規律とマクロ経済』で展開されています。【本書の内容】日本経済の進む隘路を照らす ——。現状をどう考えればよいか、この先どうなるのか。過去30年間に陥った不可思議な均衡とその行方を初めて包括的に解明。戦中・敗戦直後の経験も踏まえた透徹した分析から、危機対応の方針を含め、政府・日銀のすべきこと/してはいけないことを明確に提示する。
齊藤 誠 著
税込4,950円/本体4,500円
A5判・上製・468頁
ISBN978-4-8158-1136-5 C3033
在庫有り
『日本歴史』 [2023年11月号、第906号] から(評者:苅米一志氏)
狩猟と権力
日本中世における野生の価値
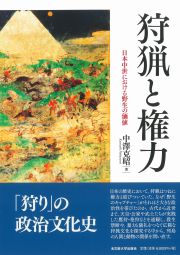
中澤克昭著『狩猟と権力』が、『日本歴史』(2023年11月号、第906号、日本歴史学会編/吉川弘文館発行)で紹介されました。日本の歴史において、狩猟はつねに権力と結びついていた。なぜ「野生のキャプチャー」がそれほど大きな政治性を帯びたのか。古代から近世まで、天皇・公家や武士たちが実践した鷹狩・巻狩などを通観し、殺生禁断や、暴力と儀礼をつなぐ広範な狩猟文化を探究する中から、列島の人間と動物の関係を問い直します。
中澤克昭 著
税込7,480円/本体6,800円
A5判・上製・484頁
ISBN978-4-8158-1106-8 C3021
在庫有り
『日本歴史』 [2023年11月号、第906号] から(評者:廣川和花氏)
ツベルクリン騒動
明治日本の医と情報
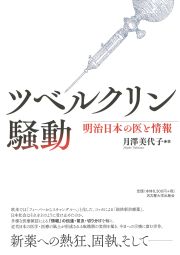
月澤美代子著『ツベルクリン騒動』が、『日本歴史』(2023年11月号、第906号、日本歴史学会編/吉川弘文館発行)で紹介されました。欧米では「フィーバーからスキャンダルへ」と化した、コッホによる「結核新治療薬」。日本社会はそれをどのように受け止めたのか。多様な医療雑誌による「情報」の伝達・普及・切り分けを軸に、近代日本の医学・医療の風土が形成される転換期の実相を描き、今日への示唆に富む労作。
月澤美代子 著
税込6,930円/本体6,300円
A5判・上製・504頁
ISBN978-4-8158-1101-3 C3021
在庫有り
『ランドスケープデザイン』 [第153号、2023年12月] から
チョコレート・タウン
〈食〉が拓いた近代都市

片木篤著『チョコレート・タウン』が、『ランドスケープデザイン』(第153号、2023年12月、マルモ出版発行)で紹介されました。チョコレート工場を中核として築かれた新たな都市「チョコレート・タウン」。甘くて苦い嗜好品の大量生産・輸送・消費・広告は、どのような空間や生活をもたらしたのか ——。欧米の代表的事例から、外来の〈食〉が〈住〉を刷新していく歴史をトータルに描きだします。
“…… チョコレートの生産によって新しく生まれた4つの都市(チョコレート・タウン)に焦点を当て、その発展の歴史やライフスタイル・文化等の変遷を紐解いていく、ユニークな視点からまちづくりを探究する一冊である。…… 日本では安価でどこでも買える菓子のイメージが強いが、まちづくりの礎になりうるものかと思うと、なかなかに目から鱗だ。”(p.123)
片木 篤 著
税込6,930円/本体6,300円
A5判・上製・440頁
ISBN978-4-8158-1132-7 C3052
在庫有り
「読売新聞」 [2023年10月22日付] から(評者:牧野邦昭氏)
皇室財政の研究
もう一つの近代日本政治史
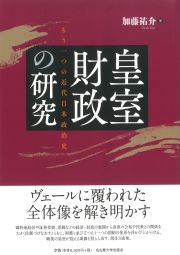
加藤祐介著『皇室財政の研究』が、「読売新聞」(2023年10月22日付)で紹介されました。ヴェールに覆われた皇室財政の姿を初めてトータルに解明。御料地経営や証券投資、恩賜などの経済・財政の展開から皇室の公私や民衆との関係を大きく位置づけなおすとともに、国務と並び立つもう一つの国制の体系を浮かび上がらせます。戦後の皇室が抱える葛藤も照らし出す、刮目の成果。
加藤祐介 著
税込6,930円/本体6,300円
A5判・上製・410頁
ISBN978-4-8158-1126-6 C3021
在庫有り
『図書新聞』 [2023年10月21日号、第3611号] から(評者:中西亮太氏)
真理・政治・道徳
プラグマティズムと熟議
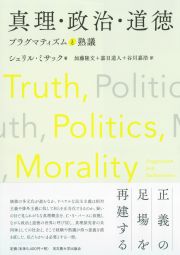
C・ミサック著『真理・政治・道徳』(加藤隆文・嘉目道人・谷川嘉浩訳)が、『図書新聞』(2023年10月21日号、第3611号、武久出版発行)で紹介されました。価値の多元化が進むなか、リベラルな民主主義は相対主義や排外主義に抗して自らを正当化できるのか。疑いの目で見られがちな真理概念を、C・S・パースに依拠しながら政治と道徳の世界に呼び戻し、真理探究者の共同体としての社会と、そこで経験や熟議が持つ意義を描き直した、私たちがいま必要とする一冊。
“…… ミサックが我々に呼びかけているのは、我々は真理を諦める必要などないし、むしろ諦めるべきではないということなのである。さまざまな人びととの共同探究を通して、我々は正しいことに正しいと、そして、間違っていることに間違っていると主張すべきなのだろう。とりわけそれは、あらゆる信念が「私にとっては真である」という理由だけで生き延びてしまうような昨今の状況を痛烈に批判してくれる。……”(第5面)
C・ミサック 著
加藤隆文・嘉目道人・谷川嘉浩 訳
税込5,940円/本体5,400円
A5判・上製・326頁
ISBN978-4-8158-1122-8 C3010
在庫有り
『日本思想史学』 [第55号、2023年9月] から(評者:高山大毅氏)
詩文と経世
幕府儒臣の十八世紀

山本嘉孝著『詩文と経世』が、『日本思想史学』(第55号、2023年9月、日本思想史学会発行)で紹介されました。江戸時代の漢詩文制作はどのように政治と結びつき、古来の言葉に何が託されたのか。これまで注目されてこなかった幕府儒臣に焦点を当て、漢詩・漢文書簡・建議などの多彩な表現を読み解くとともに、武家の学問論や民間の技芸論をも視野に入れて、近世日本における「文」の行方を問い直します。
山本嘉孝 著
税込6,930円/本体6,300円
A5判・上製・440頁
ISBN978-4-8158-1043-6 C3095
在庫有り
「北海道新聞」 [2023年9月24日付、日曜文芸欄] から(評者:田中綾氏)
口述筆記する文学
書くことの代行とジェンダー
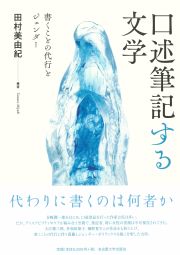
田村美由紀著『口述筆記する文学』が、「北海道新聞」(2023年9月24日付、日曜文芸欄)で紹介されました。谷崎潤一郎をはじめ、口述筆記を行った作家は実は多い。だが、ディスアビリティやケアが絡み合う空間で、筆記者、特に女性の役割は不可視化されてきた。大江健三郎、多和田葉子、桐野夏生らの作品をも取り上げ、書くことの代行に伴う葛藤とジェンダー・ポリティクスを鋭く分析した力作。
“……〈内助の功〉で片づけられない筆記者の役割、ケア労働の課題等、大切な視点と思う。”(第7面)
田村美由紀 著
税込6,380円/本体5,800円
A5判・上製・318頁
ISBN978-4-8158-1129-7 C3095
在庫有り
「読売新聞」 [2023年10月1日付] から(評者:遠藤乾氏)
派閥の中国政治
毛沢東から習近平まで
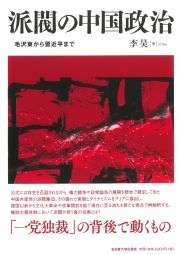
李昊著『派閥の中国政治』が、「読売新聞」(2023年10月1日付)で紹介されました。公式には存在を否認されながら、権力闘争や政策論争の展開を根本で規定してきた中国共産党の派閥集団。その隠れた実態とダイナミズムをクリアに描出し、建国以前から文化大革命や改革開放を経て現在に至る流れを新たな視点で再解釈します。権威主義体制において派閥が担う真の役割とは?
“…… 中国共産党内の派閥に注目し、その100年史を紐解く。著者の李昊氏は、新進気鋭の中国政治研究者。比較政治学で蓄積のある派閥研究と中国政治史研究を掛け合わせ、一党独裁下の中国における派閥の盛衰と政争を追跡する。
簡単な作業ではあるまい。レーニン主義政党では分派活動は禁止され、その存在と活動は水面下に潜らざるをえない。しかし、党が国家となり、エリートが昇進を求め仲間を作るなか、一党独裁下でも派閥はなくなりはしない。それは職縁や地縁などの縁故を紐帯とし、党内に留まり続けなお、個人的な恩顧とともに、継続的な協力関係を構築する。……”(第25面)
李 昊 著
税込6,380円/本体5,800円
A5判・上製・396頁
ISBN978-4-8158-1131-0 C3031
在庫有り
『経営史学』 [第58巻第2号、2023年9月] から(評者:平野恭平氏)
日本綿業史
徳川期から日中開戦まで
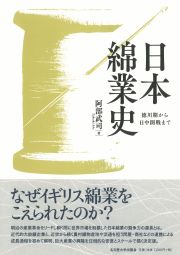
阿部武司著『日本綿業史』が、『経営史学』(第58巻第2号、2023年9月、経営史学会発行)で紹介されました。明治の産業革命をリードし瞬く間に世界市場を制覇した日本綿紡績・織物業の競争力の源泉とは。近代的大紡績企業と、近世から続く農村織物産地や流通を担う問屋・商社などの連携による成長過程を初めて解明、衰退に向かう戦後も視野に、巨大産業の興隆を圧倒的な密度とスケールで描く決定版。
阿部武司 著
税込7,920円/本体7,200円
A5判・上製・692頁
ISBN978-4-8158-1059-7 C3033
在庫有り
『イスラム世界』 [第99号、2023年9月] から(評者:末森晴賀氏)
近世東地中海の形成
マムルーク朝・オスマン帝国とヴェネツィア人

堀井優著『近世東地中海の形成』が、『イスラム世界』(第99号、2023年9月、日本イスラム協会発行)で紹介されました。古くから東西交易の要衝として栄えた「レヴァント」。中世から近世への転換のなか、イスラーム国家とヨーロッパ商人の「共生」を支えてきた秩序の行方は? オスマン条約体制や海港都市アレクサンドリアのありようから、異文化接触の実像を明らかにするとともに、東アジアに及ぶ「治外法権」の淵源をも示した力作。
堀井 優 著
税込5,940円/本体5,400円
A5判・上製・240頁
ISBN978-4-8158-1053-5 C3022
在庫有り
『経済セミナー』 [2023年10・11月号、第734号] から
中央銀行はお金を創造できるか
信用システムの貨幣史
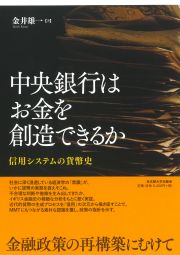
金井雄一著『中央銀行はお金を創造できるか』が、『経済セミナー』(2023年10・11月号、第734号、日本評論社発行)で紹介されました。社会に深く浸透している経済学の「常識」が、いかに貨幣の実態を捉えそこね、不合理な判断や施策を生み出してきたか、イギリス金融史の精緻な分析をもとに鋭く実証。近代的貨幣の生成プロセスを「信用」の次元から描き直すことで、MMTにもつながる素朴な認識を覆し、政策の指針を示します。
金井雄一 著
税込5,940円/本体5,400円
A5判・上製・234頁
ISBN978-4-8158-1125-9 C3033
在庫有り
『週刊読書人』 [2023年9月22日号、第3507号] から(評者:松下和夫氏)
現代気候変動入門
地球温暖化のメカニズムから政策まで

アンドリュー・E・デスラー著『現代気候変動入門』が、『週刊読書人』(2023年9月22日号、第3507号、読書人発行)で紹介されました。「気候とは何か」といった初歩の初歩から、脱炭素に向けて世界がとるべき対策まで、温暖化に関する科学と政治・経済をバランスよく記述。懐疑論への応答も随所に交えながら、問題の全体像を、理解に必要な深さまで明快に語る、「文系」「理系」双方へ向けたスタンダードかつ最良の書。
“…… 本書『現代気候変動入門』は、私たちが渇望する信頼できる基礎知識を、正確にバランスよく提供してくれる。…… 気候変動の科学が対象とする気候システムと、経済や政治が対象とする社会システムの双方について包括的かつバランスよく記述し、気候変動に関する明解な理解を可能としているのである。……
…… 本書の目標は、読者が気候危機に関する公共政策の議論に参加できるようになることである。著者の記述は丁寧でありながら明快であり、その主張は力強く、情熱的である。また、本書では気候懐疑論に対して明解な論拠に基づく論理的な論駁も随所に交えている。……
本書の訳文は科学的正確さを損なうことなく、一般向けに読みやすく平易にこなれた文章となっており、訳者と監訳者の労を多としたい。…… 学生や研究者のみならず、企業の実務家、政策立案にかかわる者、そして広く一般の市民にも推薦したい。”(第3面)
アンドリュー・E・デスラー 著
神沢 博 監訳/石本美智 訳
税込3,850円/本体3,500円
菊判・並製・334頁
ISBN978-4-8158-1130-3 C3040
在庫有り
『アジア経済』 [第64巻第3号、2023年9月] から(評者:島田竜登氏)
世界史のなかの東アジアの奇跡

杉原薫著『世界史のなかの東アジアの奇跡』が、『アジア経済』(第64巻第3号、2023年9月、ジェトロ・アジア経済研究所発行)で紹介されました。脱〈西洋中心〉のグローバル・ヒストリー。—— 豊かさをもたらす工業化の世界的普及は、日本をはじめとする「東アジアの奇跡」なしにはありえなかった。それは「ヨーロッパの奇跡」とは異なる、分配の奇跡だった。地球環境や途上国の行方も見据え、複数の発展径路の交錯と融合によるダイナミックな世界史の姿を提示する、渾身のライフワーク。
“…… 本書の第1の意義は近代西洋経済の相対化である。…… 本来の意味で、アジア、とりわけ東アジアをグローバル・ヒストリー研究のなかに位置づけることに一定の成功を見ている。この意味で、本書はグローバル・ヒストリー研究を格段に進歩させたとも評することができるであろう。
第2の本書の意義としては、グローバル経済史研究において、環境的要因分析を導入することを試みていることが指摘できる。…… 西洋と東アジアとの対比において、環境や資源の観点を導入し、さらには経済学分析に新たな生産要素を加えることも提唱する。……
さらに本書の第3の意義としては、歴史叙述における1つの野心的な試みであることを言及すべきであろう。…… 現代的な事象の歴史的な根源を、500年、200年、50年という異なるスパンで解明を試みており、それは現代社会が多層的な歴史的な経緯をもっていることを著者が自覚し、現代社会の歴史的根源を多層性的に解明することを試みているのに他ならない。少なくとも、多くの歴史学の研究書が単に時系列的な叙述にあふれていることを考えると、本書の編構成は非常に意欲的な試みであることに間違いない。……”(pp.76-77)
杉原 薫 著
税込6,930円/本体6,300円
A5判・上製・776頁
ISBN978-4-8158-1000-9 C3022
在庫有り
『経済研究』 [第73巻第4号、2022年10月] から(評者:橋野知子氏)
世界史のなかの東アジアの奇跡

杉原薫著『世界史のなかの東アジアの奇跡』が、『経済研究』(第73巻第4号、2022年10月、一橋大学経済研究所編/岩波書店発行)で紹介されました。脱〈西洋中心〉のグローバル・ヒストリー。—— 豊かさをもたらす工業化の世界的普及は、日本をはじめとする「東アジアの奇跡」なしにはありえなかった。それは「ヨーロッパの奇跡」とは異なる、分配の奇跡だった。地球環境や途上国の行方も見据え、複数の発展径路の交錯と融合によるダイナミックな世界史の姿を提示する、渾身のライフワーク。
“…… 工業化は温帯で興り、近代技術は温帯に伝播してきた。著者は、熱帯にふさわしい持続可能性に配慮した開発問題を地球規模で議論すべきだと最後の章で述べており、グローバル・ヒストリーにおけるアジアのみならず、環境経済史という分野へも視野を広げている。エネルギーや移民といった今日的問題も、欧米の歴史の中にだけあるのではなく、アジア的でもある。その意味でも、本書には未来へのメッセージも込められている。
著者の視点は一貫して俯瞰的であり、工業化が国境を越えたように、国境を越えた東アジアという地域が地域内での相互作用を進めつつ、世界経済にいかなる影響を持ったのかを鮮やかに描いている。そのためには、ある種の単純化やモデル化が必要であるが、著者のそのスキルは見事としか言いようがない。特に、膨大な貿易データを駆使しつつコンパクトな図式化がなされている点は、reader-friendly であり、著者特有の鳥瞰的な視点を強く感じた。……”(p.394)
杉原 薫 著
税込6,930円/本体6,300円
A5判・上製・776頁
ISBN978-4-8158-1000-9 C3022
在庫有り
『アフリカレポート』 [第61号、2023年] から(評者:牧野久美子氏)
社会的企業の挫折
途上国開発と持続的エンパワーメント

一栁智子著『社会的企業の挫折』が、『アフリカレポート』(第61号、2023年、ジェトロ・アジア経済研究所発行)で紹介されました。英雄的な物語を超えて ——。NPO と営利企業のハイブリッドとして現れた社会的企業。その華々しい成功譚の背後には、使命と利益の両立をめぐる苦悩が隠されていた。注目を集めるソーシャルビジネスの具体的事例を、当事者インタビューと現地調査を中心に、長期の視点から徹底的に検証。持続的で多元的な社会貢献の可能性をさぐります。
一栁智子 著
税込6,930円/本体6,300円
A5判・上製・304頁
ISBN978-4-8158-1121-1 C3036
在庫有り
『アフリカレポート』 [第61号、2023年] から(評者:佐藤章氏)
グローバル開発史
もう一つの冷戦
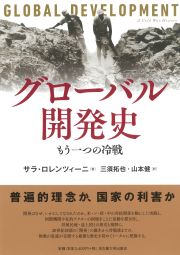
サラ・ロレンツィーニ著『グローバル開発史』(三須拓也・山本健訳)が、『アフリカレポート』(第61号、2023年、ジェトロ・アジア経済研究所発行)で紹介されました。開発はなぜ、いかにしてなされたのか。米・ソ・欧・中の対抗関係を軸にした実践と、国際機関や私的アクターの国境をこえた活動を描き出し、旧植民地・途上国との相克も視野に、20世紀初頭の「開発」の誕生から冷戦後までの、無数の思惑が交錯する複雑な歴史を初めてトータルに把握します。
サラ・ロレンツィーニ 著
三須拓也・山本 健 訳
税込3,740円/本体3,400円
A5判・上製・384頁
ISBN978-4-8158-1090-0 C3022
在庫有り
『歴史と経済』 [第260号、2023年7月] から(評者:浅田進史氏)
奴隷貿易をこえて
西アフリカ・インド綿布・世界経済
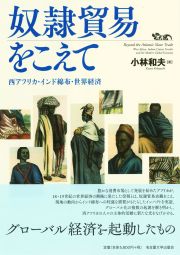
小林和夫著『奴隷貿易をこえて』が、『歴史と経済』(第260号、2023年7月、政治経済学・経済史学会発行)で紹介されました。豊かな消費市場として発展を始めたアフリカが、18・19世紀の世界経済の興隆に果たした役割とは。奴隷貿易史観をこえ、現地の動向からインド綿布への旺盛な需要がもたらしたインパクトを実証、グローバル化の複数の起源を解き明かし、西アフリカの人々の主体的活動に新たな光をなげかけます。
小林和夫 著
税込6,380円/本体5,800円
A5判・上製・326頁
ISBN978-4-8158-1037-5 C3022
在庫有り
『週刊読書人』 [2023年9月15日号、第3505号] から(評者:熊倉修一氏)
中央銀行はお金を創造できるか
信用システムの貨幣史
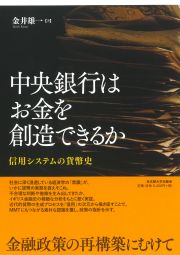
金井雄一著『中央銀行はお金を創造できるか』が、『週刊読書人』(2023年9月15日号、第3505号、読書人発行)で紹介されました。社会に深く浸透している経済学の「常識」が、いかに貨幣の実態を捉えそこね、不合理な判断や施策を生み出してきたか、イギリス金融史の精緻な分析をもとに鋭く実証。近代的貨幣の生成プロセスを「信用」の次元から描き直すことで、MMTにもつながる素朴な認識を覆し、政策の指針を示します。
“…… イングランド銀行などに残された膨大な金融史料やデータを丹念に追い、その実証分析結果を踏まえて内生説の妥当性を訴える論述を展開する。そこには強い納得性が備わっており、読む人を引きつける。……”(第3面)
金井雄一 著
税込5,940円/本体5,400円
A5判・上製・234頁
ISBN978-4-8158-1125-9 C3033
在庫有り
『社会思想史研究』 [第47号、2023年9月] から(評者:橋本努氏)
社会をつくった経済学者たち
スウェーデン・モデルの構想から展開へ
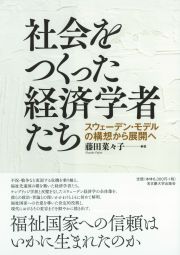
藤田菜々子著『社会をつくった経済学者たち』が、『社会思想史研究』(第47号、2023年9月、社会思想史学会編)で紹介されました。不況・戦争など直面する危機を乗り越え、福祉先進国の礎を築いた経済学者たち。ケンブリッジ学派と双璧をなしたスウェーデン経済学の全体像を、彼らの政治・世論との深いかかわりとともに初めて解明、福祉国家への合意を導いた決定的役割と、現代におけるその変容までを鮮やかに描き出します。
“…… 19世紀末から1930年代にかけて開花したスウェーデンの経済学と、そこから派生した政策構想に焦点を当てている。…… 主旋律は明快であり、すべてはこのモデルへの貢献という観点から編まれている。著者の長年にわたる研究が知性史の豊かな作品へと結実しており、一国の経済体制と経済学説が織りなす関係を鮮やかな筆致で捉えた大作である。……”(p.208)
藤田菜々子 著
税込6,930円/本体6,300円
A5判・上製・438頁
ISBN978-4-8158-1097-9 C3033
在庫有り
Bullettino Senese di Storia Patria [2022年号] から(評者:Enzo Mecacci氏)
転生するイコン
ルネサンス末期シエナ絵画と政治・宗教抗争
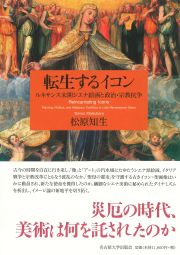
松原知生著『転生するイコン』が、Bullettino Senese di Storia Patria(2022年号、Legare Street Press 発行)で紹介されました。古今の時間を自在に行き来し、「像」と「アート」の汽水域にたゆたうシエナ派絵画。イタリア戦争と宗教改革にともなう波乱のなか、「聖母の都市」を守護する古きイコン=聖画像はいかに動員され、新たな使命を獲得したのか。繊細なシエナ美術に秘められたダイナミズムを析出し、イメージ論の新地平を切り拓きます。
松原知生 著
税込12,980円/本体11,800円
A5判・上製・652頁
ISBN978-4-8158-1007-8 C3071
在庫有り
『週刊エコノミスト』 [2023年9月19・26日合併号] から(評者:平山賢一氏)
中央銀行はお金を創造できるか
信用システムの貨幣史
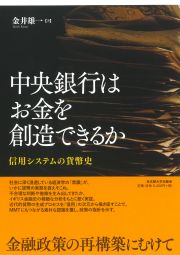
金井雄一著『中央銀行はお金を創造できるか』が、『週刊エコノミスト』(2023年9月19・26日合併号、毎日新聞出版発行)で紹介されました。社会に深く浸透している経済学の「常識」が、いかに貨幣の実態を捉えそこね、不合理な判断や施策を生み出してきたか、イギリス金融史の精緻な分析をもとに鋭く実証。近代的貨幣の生成プロセスを「信用」の次元から描き直すことで、MMTにもつながる素朴な認識を覆し、政策の指針を示します。
金井雄一 著
税込5,940円/本体5,400円
A5判・上製・234頁
ISBN978-4-8158-1125-9 C3033
在庫有り
『週刊金曜日』 [2023年9月8日号、第1439号] から(評者:長瀬海氏)
口述筆記する文学
書くことの代行とジェンダー
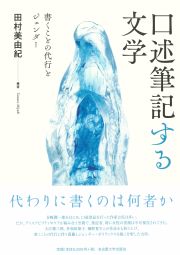
田村美由紀著『口述筆記する文学』が、『週刊金曜日』(2023年9月8日号、第1439号、金曜日発行)で紹介されました。谷崎潤一郎をはじめ、口述筆記を行った作家は実は多い。だが、ディスアビリティやケアが絡み合う空間で、筆記者、特に女性の役割は不可視化されてきた。大江健三郎、多和田葉子、桐野夏生らの作品をも取り上げ、書くことの代行に伴う葛藤とジェンダー・ポリティクスを鋭く分析した力作。
“…… 口述筆記から文学を考えるこの研究書は、作家の権威性、ジェンダー間の秩序、創作行為の神話、そのぜんぶを瓦解させる勇敢な一冊だ。たとえば、晩年筆記のできなくなった谷崎潤一郎。彼が女性の筆記者に口述する現場を見つめる著者の眼差しは、近代文学が堅固に守ってきた支配-被支配の構造を暴き、のみならず、作家の自律性を彼女たちの存在が脅かす、その可能性を明らかにする。ぱら、ぱら。近代文学のメッキが剥がれていく。いいぞ。……”(p.55)
田村美由紀 著
税込6,380円/本体5,800円
A5判・上製・318頁
ISBN978-4-8158-1129-7 C3095
在庫有り
『図書新聞』 [2023年9月9日号、第3606号] から(評者:佐々木和貴氏)
シェイクスピアはどのようにしてシェイクスピアとなったか
版本の扉が語る1700年までのイギリス演劇

山田昭廣著『シェイクスピアはどのようにしてシェイクスピアとなったか』が、『図書新聞』(2023年9月9日号、第3606号、武久出版発行)で紹介されました。劇場閉鎖による危機を乗り越えて、その芝居は生き続けた ——。エリザベス時代から王政復古後まで、戯曲本の数や印刷された情報の変遷を網羅的に跡づけ、劇作家・出版者・観客・読者の多様な関係をふまえてシェイクスピアを歴史的に位置づけます。演劇と出版をめぐる探究の到達点。
“…… 氏の研究の決定的に新しいところは、この3つの資料[ウォールタ・グレッグ『王政復古までの英国戯曲本書誌』、アルフレッド・ハービッジ『975年から1700年までのイギリス戯曲の年表』、ベン・シュナイダー『ロンドン・ステージ1660-1800』の『総索引』]を時間軸に沿って読み解き整理した上で、できるだけ数値化し、数多くの表として示したことにある。結果として、この3つのデータベースがいわば連結され、極めて立体的な形で、当時の演劇の姿が浮かびあがってくることになった(なお、この3つの資料は、氏によって再構成された形で、巻末に200頁にわたって収録されており、それ自体、大変利用価値の高いものである)。
さらに氏の切り口も、書誌学の専門家ならではのオリジナルなものだ。たとえば、氏は戯曲本の扉の情報に着目して、それを丁寧に比較・吟味することで、あるいは戯曲本の初版と再版・重版の統計をとり、それを図表化することで、イギリス演劇の生成と変化の再現を試みたのである。その結果、通常の演劇史では殆ど触れられることのない興味深い事実が、数多く浮かび上がってきた。……”(第8面)
山田昭廣 著
税込8,800円/本体8,000円
A5判・上製・524頁
ISBN978-4-8158-1123-5 C3098
在庫有り
『図書新聞』 [2023年9月9日号、第3606号] から(評者:狭間芳樹氏)
殉教の日本
近世ヨーロッパにおける宣教のレトリック
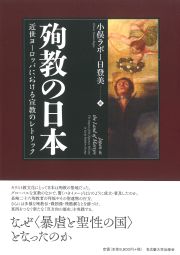
小俣ラポー日登美著『殉教の日本』が、『図書新聞』(2023年9月9日号、第3606号、武久出版発行)で紹介されました。キリスト教文化にとって、日本は〈暴虐と聖性の国〉だった。グローバルな宣教のなかで、驚くべきイメージはどのように成立・普及したのか。長崎二十六殉教者の列福やその聖遺物の行方、さらには多様な殉教伝・磔図像・残酷劇などを跡づけ、東西をつなぐ新たな「双方向の歴史」を実践します。
“…… 評者が特に印象にのこったのはそうした殉教の言説が明治以降の日本において積極的に受け入れられたという史実である。カトリック側が殉教者を英雄視し顕彰するのは当然として、日本はあくまでもキリシタンたちを断罪した側であった。ところが、こうした立場の違いというのは自明であるにもかかわらず、そのことは現代においてほとんど意識されない。著者は「終章」において現代の日本人の歴史とアイデンティティの一部が「前近代の西欧の歴史的文脈で育まれた思考の枠組み」に端を発しており、これは「戦後の一部の界隈で観察される殉教者の受容、さらには流用という現象においても同様である」と述べているが、このことは示唆深い。確かに殉教は、ときに武士の殉死と重なり合わせて捉えられることがあり、これもまた流用だといってよいであろう。
キリシタンの殉教については、これまで国内外を問わずキリスト教史家によって扱われてきたとはいえ、そのほとんどが近世日本で生じたその現象を賞賛し、感傷的・情緒的に捉えるにとどまってきた。このことを、かつて高瀬弘一郎氏が「美化された殉教史」(『キリシタンの世紀 —— ザビエル渡日から「鎖国」まで』岩波書店)と問題視して以来、それを乗りこえる研究が進みつつあるが、そうしたなか殉教の概念それ自体を論じた本書のもつ意義は大きい。……”(第5面)
小俣ラポー日登美 著
税込9,680円/本体8,800円
A5判・上製・600頁
ISBN978-4-8158-1119-8 C3022
在庫有り
『史学雑誌』 [第132編第7号、2023年7月] から(評者:片山剛氏)
闘う村落
近代中国華南の民衆と国家
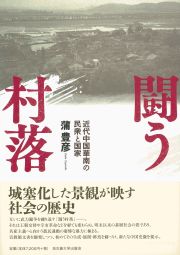
蒲豊彦著『闘う村落』が、『史学雑誌』(第132編第7号、2023年7月、史学会発行)で紹介されました。互いに武力闘争を繰り返す城塞化した村落 ——。それは王朝交替や辛亥革命などを経ても変わらぬ、明末以来の基層社会の姿であり、共産主義へと向かう農民運動の凄惨な暴力に極まる。宣教師文書を駆使しつつ、初めてその生成・展開・終焉を跡づけ、新たな中国史像を提示した渾身の力作。
蒲 豊彦 著
税込7,920円/本体7,200円
A5判・上製・504頁
ISBN978-4-8158-0998-0 C3022
在庫有り
早稲田大学総合人文科学研究センターウェブサイト [自著紹介、2023年8月公開] から
戦後表現
Japanese Literature after 1945

坪井秀人著『戦後表現』の自著紹介が、早稲田大学総合人文科学研究センターウェブサイト(2023年8月)に掲載されました。アジア太平洋戦争から冷戦、昭和の終わり、湾岸・イラク戦争、ポスト3・11まで、戦争をめぐる言葉がすくい上げてきたもの、底に沈めてきたものを、詩・小説・批評を中心に精緻に読解。経験や記憶に刻まれた〈傷跡〉としての表現の重層性から、〈戦後〉概念を再審にかけます。
坪井秀人 著
税込6,930円/本体6,300円
A5判・上製・616頁
ISBN978-4-8158-1116-7 C3095
在庫有り
『日本歴史』 [2023年9月号、第904号] から(評者:上杉和央氏)
絵図の史学
「国土」・海洋認識と近世社会
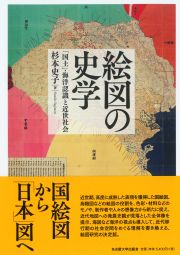
杉本史子著『絵図の史学』が、『日本歴史』(2023年9月号、第904号、日本歴史学会編)で紹介されました。近世期、高度に成熟した表現を獲得した国絵図、鳥瞰図などの絵図の役割を、色彩・材料などのモノや、制作者や人々の想像力から新たに捉え、近代地図への発展史観が見落とした全体像を提示、海図など海洋の視点も導入して、近代移行期の社会空間をめぐる理解を書き換える、絵図研究の決定版。
杉本史子 著
税込5,940円/本体5,400円
A5判・上製・440頁
ISBN978-4-8158-1062-7 C3021
在庫有り
『西洋史学』 [第275号、2023年6月] から(評者:村上宏昭氏)
政治的暴力の共和国
ワイマル時代における街頭・酒場とナチズム
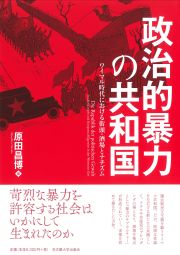
原田昌博著『政治的暴力の共和国』が、『西洋史学』(第275号、2023年6月、日本西洋史学会発行)で紹介されました。苛烈な暴力を許容する社会はいかにして生まれたのか ——。議会制民主主義を謳うワイマル共和国。だが、街頭は世論を左右する新たな公共圏として、ナチスや共産党のプロパガンダの場となり、酒場を拠点とした「暴力のサブカルチャー」が形成されていく。実像を初めて描きだした力作。
“…… なぜワイマル共和国はわずか14年で崩壊したのか。この問いかけに関し、本書は共和国に終始影を落とし続けた政治的暴力という現象に着目し、そこからこの問いの答えを導き出そうとする、ユニークかつ野心的な試みであるといえる。…… 当時のドイツ社会では政治的暴力が忌避されず、むしろプロパガンダとして機能するような風潮があったこと、この点に目を向けずにナチ党の台頭は説明できないことが指摘されており、ここに街頭や酒場での暴力という視点からドイツ近現代史を読みなおす展望が開かれている。これは本書の大きな学術的意義と評してよいだろう。……”(p.88)
原田昌博 著
税込6,930円/本体6,300円
A5判・上製・432頁
ISBN978-4-8158-1039-9 C3022
在庫有り
『西洋史学』 [第275号、2023年6月] から(評者:森田直子氏)
〈叫び〉の中世
キリスト教世界における救い・罪・霊性

後藤里菜著『〈叫び〉の中世』が、『西洋史学』(第275号、2023年6月、日本西洋史学会発行)で紹介されました。中世ヨーロッパは叫び声に満ちていた ——。修道士や「敬虔な女性たち」の内心の叫びから、異界探訪譚が語る罪人の悲鳴、さらには少年十字軍や鞭打ち苦行運動に伴う熱狂まで、キリスト教世界に響き渡る多様な〈声〉に耳を傾け、霊性史・感情史の新生面を切り拓く気鋭の力作。
“…… 本書の最大の魅力は、感情史的アプローチの有効性や将来性が示されたことにあるだろう。…… 本書のほぼ中心、第2章と第3章の間の補論2において、近年盛んになっている感情史研究を引き合いにだして「感情の〈叫び〉」を論じている …… 先行研究に拠りながら、西洋中世では苦しみや怒りにまかせて発する〈叫び〉が、聖界では〈罪〉に結び付くもの、俗界でも不徳の致すものとして否定されていたのが、次第に肯定的な意味で捉えられるようになったことが簡潔に示される。聖界に関して言えば、クリュニュー修道院において「強い感情のこもった霊性」が見いだされ、「感情」と〈救い〉が近づいた。その際、「感情」を抑えきれずに露わにした〈叫び〉で神と繋がる女性たちが、新たな「聖なる感情」の担い手として登場した(=「感情の女性化」)ことは、第2章で丁寧に論じられる通りである。……”(p.90)
後藤里菜 著
税込5,940円/本体5,400円
A5判・上製・364頁
ISBN978-4-8158-1040-5 C3022
在庫有り
『月刊星ナビ』 [2023年9月号] から(評者:原智子氏)
宇宙開発をみんなで議論しよう

呉羽真・伊勢田哲治編『宇宙開発をみんなで議論しよう』が、『月刊星ナビ』(2023年9月号、アストロアーツ発行)で紹介されました。有人宇宙探査の新たな計画、商業化、軍事化、新興国の台頭 …… 近年、宇宙開発は大きく転換しつつある。市民がそこに関わる必要性をわかりやすく説き、そのための基礎知識や科学技術コミュニケーションの手法、議論のスキルを提供する初めての本。
“…… 宇宙開発のあり方について「市民が考え、議論に参加する」ことが大切だという。すべての科学技術は私たちの生活にとって好ましいものばかりとは限らず、良くも悪くもさまざまな影響を受ける。宇宙の利用や開発も「国家や企業にお任せ」ではなく、市民(私たち)が主体的に考え議論に関わることが必要である。そんなときに、問題点を整理し判断するための手がかりを教えてくれるのがこの本だ。……”(p.61)
呉羽 真・伊勢田哲治 編
税込2,970円/本体2,700円
A5判・並製・256頁
ISBN978-4-8158-1091-7 C3040
在庫有り
『中国研究月報』 [2023年7月号、第77巻第7号] から(評者:丸川知雄氏)
中国国有企業の政治経済学
改革と持続
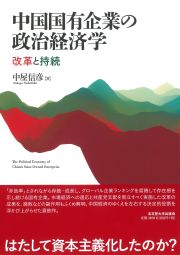
中屋信彦著『中国国有企業の政治経済学』が、『中国研究月報』(2023年7月号、第77巻第7号、中国研究所発行)で紹介されました。非効率なはずの企業群はなぜ存続し、成長できたのか。グローバル企業ランキングを席捲し、存在感を示し続ける国有企業が、市場経済への適応と共産党支配を両立すべく実施した改革の成果を、腐敗などの副作用も含め解明、「普通の」資本主義体制に抗いながら発展する中国経済の実像に迫ります。
“…… 本書が主張する通り、中国の国有企業はその重要性にもかかわらず、その実態が十分に解明されてこなかった。本書は広範な資料の収集により、「赤いヴェール」をはがして国有企業の実態に迫っており、きわめて重要な業績であるといえる。特に、上場企業における国家所有の分析、国有企業の企業会計の変遷、党による国有企業の人事管理の詳細な解明は、本書独自の貢献であると思われる。また、特に鉄鋼業の事例を多く取り上げていることは、国有企業支配の実態を理解する上で有益であった。……”(p.16)
中屋信彦 著
税込6,930円/本体6,300円
A5判・上製・366頁
ISBN978-4-8158-1095-5 C3033
在庫有り
「毎日新聞」 [2023年8月19日付] から(評者:伊藤亜紗氏)
口述筆記する文学
書くことの代行とジェンダー
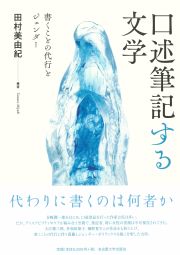
田村美由紀著『口述筆記する文学』が、「毎日新聞」(2023年8月19日付)で紹介されました。谷崎潤一郎をはじめ、口述筆記を行った作家は実は多い。だが、ディスアビリティやケアが絡み合う空間で、筆記者、特に女性の役割は不可視化されてきた。大江健三郎、多和田葉子、桐野夏生らの作品をも取り上げ、書くことの代行に伴う葛藤とジェンダー・ポリティクスを鋭く分析した力作。
田村美由紀 著
税込6,380円/本体5,800円
A5判・上製・318頁
ISBN978-4-8158-1129-7 C3095
在庫有り
「毎日新聞」 [2023年8月5日付] から(評者:松原隆一郎氏)
中央銀行はお金を創造できるか
信用システムの貨幣史
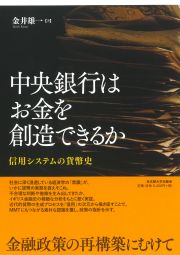
金井雄一著『中央銀行はお金を創造できるか』が、「毎日新聞」(2023年8月5日付)で紹介されました。社会に深く浸透している経済学の「常識」が、いかに貨幣の実態を捉えそこね、不合理な判断や施策を生み出してきたか、イギリス金融史の精緻な分析をもとに鋭く実証。近代的貨幣の生成プロセスを「信用」の次元から描き直すことで、MMTにもつながる素朴な認識を覆し、政策の指針を示します。
金井雄一 著
税込5,940円/本体5,400円
A5判・上製・234頁
ISBN978-4-8158-1125-9 C3033
在庫有り
『東南アジア研究』 [第61巻第1号、2023年7月] から(評者:柳澤雅之氏)
反転する環境国家
「持続可能性」の罠をこえて
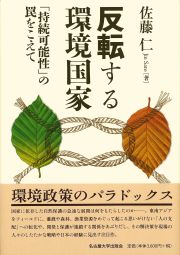
佐藤仁著『反転する環境国家』が、『東南アジア研究』(第61巻第1号、2023年7月、京都大学東南アジア地域研究研究所発行)で紹介されました。国家に依存した自然保護の急速な展開は何をもたらしたのか ——。東南アジアをフィールドに、灌漑や森林、漁業資源をめぐって起こる思いがけない「人の支配」への転化や、開発と保護の連鎖する関係をあぶりだし、その解決策を現場の人々のしたたかな戦略や日本の経験に見出す。環境論の新たな地平を拓く著者の到達点。
佐藤 仁 著
税込3,960円/本体3,600円
四六判・上製・366頁
ISBN978-4-8158-0949-2 C3031
在庫有り
『地理学評論』 [第96巻第4号、2023年7月] から(評者:浅田晴久氏)
カースト再考
バングラデシュのヒンドゥーとムスリム

杉江あい著『カースト再考』が、『地理学評論』(第96巻第4号、2023年7月、日本地理学会発行)で紹介されました。宗教が異なれば社会のかたちも異なる、という図式は、本当に有効なのか。生活の場を介して、カーストを含む多様な集団が相互に交錯する過程を、宗教の別をこえてトータルに把握。物乞いや聖者など宗教横断的な主体も視野に、分裂した南アジア像が覆い隠してきたものをすくいだします。
杉江あい 著
税込7,920円/本体7,200円
A5判・上製・426頁
ISBN978-4-8158-1112-9 C3022
在庫有り
『図書新聞』 [2023年7月29日号、第3601号、特集「2023年上半期読書アンケート」] から(評者:石原千秋氏)
アメリカの人種主義
カテゴリー/アイデンティティの形成と転換
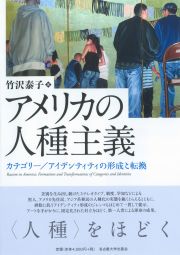
竹沢泰子著『アメリカの人種主義』が、『図書新聞』(2023年7月29日号、第3601号、武久出版発行)の特集「2023年上半期読書アンケート」で紹介されました。差別を生み出し続けたステレオタイプ、制度、学知などによる黒人、アメリカ先住民、アジア系移民の人種化の実態を鋭くとらえるとともに、排除に抗うアイデンティティ形成のジレンマもはじめて一貫して提示、アートを手がかりに、固定化された対立をほどく、第一人者による渾身の成果。
“…… たとえば人口の統計を取るとき人は人種というカテゴリーを用いる。カテゴリーは価値観にほかならない。これは一体何だろう。進化論も美術もこの本では同居している。そして、「~らしさ」の恐ろしさを教えてくれる。アミン・マアルーフ『アイデンティティが人を殺す』(小野正嗣訳、ちくま学芸文庫)の「アイデンティティ」がまさに「カテゴリー」の意味だったとよくわかった。……”(第6面)
竹沢泰子 著
税込4,950円/本体4,500円
A5判・上製・516頁
ISBN978-4-8158-1118-1 C3022
在庫有り
『週刊読書人』 [2023年7月28日号、第3499号、特集「2023年上半期の収穫から」] から
『週刊読書人』(2023年7月28日号、第3499号、読書人発行)の特集「2023年上半期の収穫から」で、以下の図書が紹介されました。
【荻野哉氏による紹介】
藤原貞朗著『共和国の美術 —— フランス美術史編纂と保守/学芸員の時代』
【成田龍一氏による紹介】
坪井秀人著『戦後表現 —— Japanese Literature after 1945』
【三浦麻美氏による紹介】
小俣ラポー日登美著『殉教の日本 —— 近世ヨーロッパにおける宣教のレトリック』
『経済学史研究』 [第65巻第1号、2023年7月] から(評者:木宮正裕氏)
スミスの倫理
『道徳感情論』を読む

竹本洋著『スミスの倫理』が、『経済学史研究』(第65巻第1号、2023年7月、経済学史学会発行)で紹介されました。スミス倫理学の真の射程とは。近代における倫理のメカニズムと意義を明瞭に説き、政治・経済・社会のよき運用を支える心理学的な人間学を打ち立てた、もうひとつの主著から描き出す。『国富論』とは違った現代への示唆と、経済学にとどまらない社会科学的知への豊かな洞察を浮かび上がらせます。
“…… 本書の特色は、スミスの提示する概念や理論の「表側」だけでなく、いわば「裏側」も考究することによって、これまでのスミス研究とは異なる視点から『道徳感情論』を繙くところにある。特に本書において興味深いのは、そうした新しい視点で解釈された諸概念から、スミスの倫理学における社会統合と社会分節化の両側面が浮き彫りにされることである。……
本書は、一般的に「アダム・スミス」という名前から想起される、「自由」「平等」「自律」といったイメージとは異なるスミス像を提示する。本書が導き出すのは、秩序を第一に重視し、そのためには社会の不平等を肯定し、人びとに統治者や既存の秩序に対する従順さを要求するスミスである。本書を通して、私たちはアダム・スミスの新たな一面に出逢うことができるのである。”(pp.99-100)
竹本 洋 著
税込5,940円/本体5,400円
A5判・上製・262頁
ISBN978-4-8158-0990-4 C3012
在庫有り
『歴史学研究』 [2023年8月号、第1038号] から(評者:井出匠氏)
愛国とボイコット
近代中国の地域的文脈と対日関係
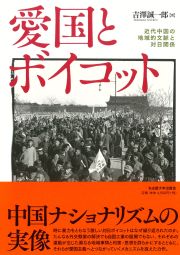
吉澤誠一郎著『愛国とボイコット』が、『歴史学研究』(2023年8月号、第1038号、歴史学研究会編)で紹介されました。中国ナショナリズムの実像 ——。時に暴力をともなう激しい対日ボイコットはなぜ繰り返されたのか。たんなる外交懸案の解決でも自国工業の振興でもない、それぞれの運動が生じた異なる地域事情と利害・思想を詳らかにするとともに、それらが愛国主義へとつながっていくメカニズムを捉えた力作。
吉澤誠一郎 著
税込4,950円/本体4,500円
A5判・上製・314頁
ISBN978-4-8158-1048-1 C3022
在庫有り
『週刊読書人』 [2023年7月21日号、第3498号] から(評者:大賀祐樹氏)
真理・政治・道徳
プラグマティズムと熟議
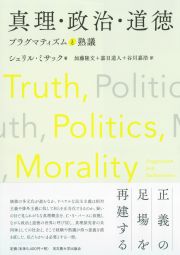
C・ミサック著『真理・政治・道徳』(加藤隆文・嘉目道人・谷川嘉浩訳)が、『週刊読書人』(2023年7月21日号、第3498号、読書人発行)で紹介されました。価値の多元化が進むなか、リベラルな民主主義は相対主義や排外主義に抗して自らを正当化できるのか。疑いの目で見られがちな真理概念を、C・S・パースに依拠しながら政治と道徳の世界に呼び戻し、真理探究者の共同体としての社会と、そこで経験や熟議が持つ意義を描き直した、私たちがいま必要とする一冊。
“…… プラグマティズムの再評価においても見逃されていたパースの意義を見出すだけでなく、政治、道徳に拡張するミサックの議論は、現代的な価値がある。異文化における差別や人権侵害が何故問題となるのかについて、多元性に対する中立性を前提とすると、指摘し難くなる可能性があるが、認識的な探究のプロセスを通して、何故それが誤りであるのか、指摘できるようになるからだ。……”(第3面)
C・ミサック 著
加藤隆文・嘉目道人・谷川嘉浩 訳
税込5,940円/本体5,400円
A5判・上製・326頁
ISBN978-4-8158-1122-8 C3010
在庫有り
『国際安全保障』 [第51巻第1号、2023年6月] から(評者:福田保氏)
南シナ海問題の構図
中越紛争から多国間対立へ

庄司智孝著『南シナ海問題の構図』が、『国際安全保障』(第51巻第1号、2023年6月、国際安全保障学会発行)で紹介されました。中国の急速な台頭により国際政治の焦点となった危機の構造を、主要な当事者であるベトナム・フィリピンやASEANの動向をふまえて解明、非対称な大国と向きあう安全保障戦略をとらえ、米中対立の枠組みにはおさまらない紛争の力学を浮かび上がらせて、危機の行方を新たに展望します。
“…… 本書の特長の1つは、…… 南シナ海問題という複雑化した国家間争いの歴史を3つに区分し、重要な出来事を端的に解説している。また、2010年代の南シナ海をめぐる国家間関係が1つの章(第8章)を読むことで手際良く把握できる。著者が述べる通り、本書は南シナ海問題の概説書としての意義を持つ。第2の特長は、ベトナムの南シナ海政策および対外政策を、日本語、英語文献のみならずベトナム語文献を丹念に読み込み、包括的に分析している点である。ベトナムの南シナ海政策を体系的にまとめた和書は貴重である。第3の特長は、本書の視点を米中二大国ではなく、地域安全保障においてその重要性が相対化されがちなASEAN、ベトナム、フィリピンに着目している点である。1980~90年代のASEANによる南シナ海問題の「第1の多国間対立化」(中越二国間紛争からASEANと中国の多国間紛争への構図の変化)、2000年代後半に米国の本格的関与を膳立てして「第2の多国間対立化」を後押ししたベトナムのイニシアティブ、2010年代半ばにASEANのみならず米中の南シナ海対応にも影響を及ぼしたフィリピンの変節などを踏まえ、これら3者が「米中に比肩しうる重要な役割を果たしてきた」との著者の考察は、本書の中核をなす議論である(254頁)。 ……”(pp.102-103)
庄司智孝 著
税込5,940円/本体5,400円
A5判・上製・344頁
ISBN978-4-8158-1054-2 C3031
在庫有り
『図書新聞』 [2023年7月22日号、第3600号] から(評者:廣部泉氏)
アメリカの人種主義
カテゴリー/アイデンティティの形成と転換
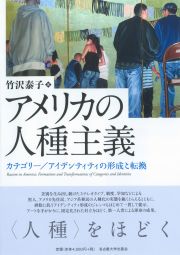
竹沢泰子著『アメリカの人種主義』が、『図書新聞』(2023年7月22日号、第3600号、武久出版発行)で紹介されました。差別を生み出し続けたステレオタイプ、制度、学知などによる黒人、アメリカ先住民、アジア系移民の人種化の実態を鋭くとらえるとともに、排除に抗うアイデンティティ形成のジレンマもはじめて一貫して提示、アートを手がかりに、固定化された対立をほどく、第一人者による渾身の成果。
“…… とりわけ巻の後半に登場する様々な人種的背景をもった芸術家たちとの交流とその作品についての章は圧巻である。芸術家に注目する理由を著者は、かれらが「しばしば学問が言語化・概念化する以前に、時代の最先端を切り取って人びとの感性を刺激する作品を世に送り出しているから」であると述べる。すなわち、芸術家を扱うことで、通常の人種研究の範囲をも超越しようとしているのである。本書が扱う芸術家は多岐にわたる。中でも読後に心に残ったのは、先住民居留地の放射能汚染へ問題提起する日本出身の井上葉子や人種間のヘイトに巻き込まれることなく新しいコミュニティを作り上げる努力を続ける韓国出身のジーン・シンである。かれらの作品と語りから、著者は、「いかに人種主義に抗いつつ、希望を捨てることなく未来へとつなげることができるかを」構想する。……”(第2面)
竹沢泰子 著
税込4,950円/本体4,500円
A5判・上製・516頁
ISBN978-4-8158-1118-1 C3022
在庫有り
『日本文学』 [2023年7月号、第72号] から(評者:大橋崇行氏)
変革する文体
もう一つの明治文学史

木村洋著『変革する文体』が、『日本文学』(2023年7月号、第72号、日本文学協会発行)で紹介されました。新たな文体は新たな社会をつくる ——。小説中心主義を脱し、政論・史論から翻訳・哲学まで、徳富蘇峰を起点にして近代の「文」の歩みを辿りなおし、新興の洋文脈と在来の和文脈・漢文脈の交錯から、それまでにない人間・社会像や討議空間が形づくられる道程をつぶさに描いた意欲作。
“…… 本書は「文学」の概念を、その後の「文学史」が形作ってきたものではなく、同時代の思案そのものに立ち返って捉えることで、「小説」だけでは見えてこない明治期における「文学」の有機的なつながりを再検討しようとしたものである。たとえば第2章、第6章で扱われた「風景」をめぐる問題は柄谷行人や加藤典洋らによる議論でいわゆる「風景の発見」と捉えられてきた。しいかし、明治20年代における民友社と徳富蘇峰が持っていた当時の文学青年たちへの影響力を考えれば、本書によって示された「風景」の位置づけによって異なる地平が見えてくる。また、第7章における「文明論」をめぐる議論や第9章の明治期における人生観についての問題は、従来の「文学史」がどのように形成されたかという枠組みを対象化することによって、「文学史」というあり方そのものを問い直している。
特に注目されるのは、第Ⅲ部において、平塚らいてうや田村俊子と、同時代の自然主義や思想をめぐる言説との有機的な関係性を具体的に論じた点であろう。女性たちによる表現の試みを、従来のジェンダー研究、フェミニズム批評からは見えてこなかった視点から、同時代の思索のあり方に基づいて再考している。……”(p.53)
木村 洋 著
税込6,930円/本体6,300円
A5判・上製・358頁
ISBN978-4-8158-1108-2 C3095
在庫有り
「日本ヴァレリー研究会ブログ」 [2023年7月12日公開] から(評者:淵田仁氏)
消え去る立法者
フランス啓蒙における政治と歴史

王寺賢太著『消え去る立法者』が、日本ヴァレリー研究会ブログ(2023年7月12日公開)で紹介されました。かつてこんなふうに読まれたことがあっただろうか ——。モンテスキューとルソー、そしてディドロへ。彼らが格闘し、解き明かし、残した問題とは何か。新たな共同体の創設という課題に直面し、法の根拠を問い直す重層的なテクストを読み抜き、「啓蒙」をクリシェから解き放った、気鋭の力作。
王寺賢太 著
税込6,930円/本体6,300円
A5判・上製・532頁
ISBN978-4-8158-1120-4 C3010
在庫有り
『図書新聞』 [2023年7月15日号、第3599号] から(評者:三木理史氏)
「満洲国」以後
中国工業化の源流を考える
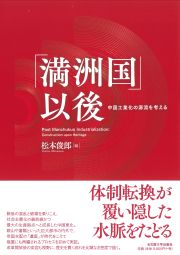
松本俊郎編『「満洲国」以後』が、『図書新聞』(2023年7月15日号、第3599号、武久出版発行)で紹介されました。戦後の混乱と破壊を乗りこえ、社会主義化の最前線かつ最大の生産拠点へと成長した中国東北。鞍山や瀋陽といった巨大都市の内外で、帝国支配の「遺産」が時代をこえて幾重にも再編されるプロセスを初めて実証。改革開放後の変容も視野に、歴史を貫く流れを比類なき密度で描きます。
“…… おそらく執筆者らの最大の論点は、満洲国期と国共内戦期、共和国創生期を「断絶」前提に語る多くの先行研究に対し、「連続性」を認めようとする点(306頁)にあると思われる。しかし、単に連続性を強調するのではなく、四都市各々の断絶や連続の強弱を充分に検証したうえで、その点を主張する本書の姿勢には執筆者の誠実さが滲み出ており、読者の多くも好感を抱くことであろう。……”(第6面)
松本俊郎 編
税込6,380円/本体5,800円
A5判・上製・358頁
ISBN978-4-8158-1114-3 C3033
在庫有り
『週刊読書人』 [2023年7月7日号、第3496号] から(評者:久保亨氏)
「満洲国」以後
中国工業化の源流を考える
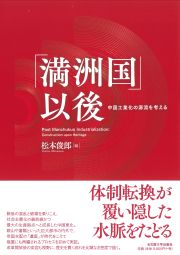
松本俊郎編『「満洲国」以後』が、『週刊読書人』(2023年7月7日号、第3496号、読書人発行)で紹介されました。戦後の混乱と破壊を乗りこえ、社会主義化の最前線かつ最大の生産拠点へと成長した中国東北。鞍山や瀋陽といった巨大都市の内外で、帝国支配の「遺産」が時代をこえて幾重にも再編されるプロセスを初めて実証。改革開放後の変容も視野に、歴史を貫く流れを比類なき密度で描きます。
“日本人の満洲イメージに転換を迫る1冊である。…… 満洲国時期の工業化の到達点を確認した上で、満洲国が崩壊した後の、東北地域における工業化の過程を、ソ連軍占領期、国民党統治期、共産党統治期の全てを含めて解明した。また本書は、製鉄業、軍需工業、機械工業、化学工業を含む多様な工業について論じ、地域的にも、鞍山や瀋陽に加え哈爾濱や長春などまで考察することによって、東北全体の変化の過程を追っている点に特徴がある。……”(第4面)
松本俊郎 編
税込6,380円/本体5,800円
A5判・上製・358頁
ISBN978-4-8158-1114-3 C3033
在庫有り
『法制史研究』 [第72号、2023年3月] から(評者:李穂枝氏)
交隣と東アジア
近世から近代へ
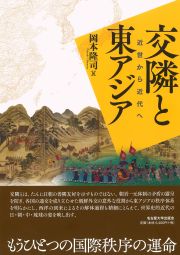
岡本隆司編『交隣と東アジア』が、『法制史研究』(第72号、2023年3月、法制史学会発行)で紹介されました。交隣とは、たんに日朝の善隣友好を示すものではない。朝貢一元体制の矛盾の露呈を防ぎ、各国の通交を成り立たせた朝鮮外交の意外な役割から東アジアの秩序体系を明らかにし、西洋の到来によるその解体過程も精細にとらえて、世界史的近代の日・朝・中・琉球の姿を映し出します。
“…… 編者が序章で提示したように、交隣関係のプリズムが多様な映像として表れたと言えるだろう。各論文は朝鮮の対外関係について、新しく発掘した史料や重要な史料を用いて緻密な実証研究を行った。本書の最大の意義は、「交隣」を軸にして東アジア近代史を再考するという発想のもと、このような多様な論文を結集したことにあると言える。近代東アジアは事大・交隣・互市関係が共存する地域で、朝鮮の交隣外交を中心に据えて対外関係を見てみると、新たな像が浮かび上がるのではないか、という点には評者も共感した。……”(pp.404-405)
岡本隆司 編
税込5,940円/本体5,400円
A5判・上製・380頁
ISBN978-4-8158-1044-3 C3022
在庫有り
『歴史の理論と教育』 [第158・159合併号、2023年3月] から(評者:池内敏氏)
交隣と東アジア
近世から近代へ
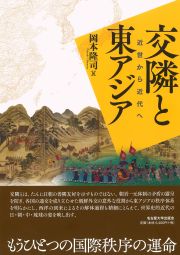
岡本隆司編『交隣と東アジア』が、『歴史の理論と教育』(第158・159合併号、2023年3月、名古屋歴史科学研究会発行)で紹介されました。交隣とは、たんに日朝の善隣友好を示すものではない。朝貢一元体制の矛盾の露呈を防ぎ、各国の通交を成り立たせた朝鮮外交の意外な役割から東アジアの秩序体系を明らかにし、西洋の到来によるその解体過程も精細にとらえて、世界史的近代の日・朝・中・琉球の姿を映し出します。
岡本隆司 編
税込5,940円/本体5,400円
A5判・上製・380頁
ISBN978-4-8158-1044-3 C3022
在庫有り
朝日新聞 [2023年7月8日付、書評欄「ひもとく」] から(評者:石原俊氏)
大学論を組み替える
新たな議論のために

広田照幸著『大学論を組み替える』が、「朝日新聞」(2023年7月8日付)読書欄の「ひもとく」(石原俊氏)で紹介されました。何を守り、何を見直していけばよいのか ——。なしくずしの政策追随に陥る大学。なぜこんなことになっているのか。価値や理念や規範をめぐる議論を避けることなく、教育の質、評価、学問の自由など具体的なトピックを通して、よい改革論とダメな改革論を区別し、大学が公共的な役割を果たし続けられる道を拓きます。
広田照幸 著
税込2,970円/本体2,700円
四六判・並製・320頁
ISBN978-4-8158-0967-6 C3037
在庫有り
『移民研究年報』 [第29号、2023年6月] から(評者:木村健二氏)
帝国のフロンティアをもとめて
日本人の環太平洋移動と入植者植民地主義
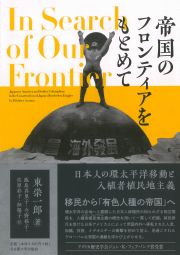
東栄一郎著『帝国のフロンティアをもとめて』が、『移民研究年報』(第29号、2023年6月、日本移民学会発行)で紹介されました。環太平洋の各地へと展開した日本人移植民の知られざる相互関係を、入植者植民地主義の概念を用いて一貫して把握。移民排斥を受けた日系アメリカ人によって帝国内外へ移転された人流、知識、技術、イデオロギーの衝撃を初めて捉え、見過ごされたグローバルな帝国の連鎖を浮かび上がらせます。
“…… 明治中期以降、いかに多くの海外発展論者たちがアメリカをめざしたか、そして1945年に至る日本人の海外進出が、いかに北米渡航者の入植者植民地主義に影響され、あるいはそこを基点として展開していったかということが示され、そのことによって、植民地朝鮮・台湾、中南米や南洋、さらには満洲への農業移民を語る際、常にハワイ・北米との対比においてみていくことの重要性が提示されたといえる。…… 本書のように、明治中期以降のアメリカにおける入植者植民地主義の思想と実践を「東進論」として強調し、それ以降の日本人の海外進出の足跡を入植者植民地主義という切り口で浮かび上がらせた意義は大きい。それによって、日本の帝国主義を相対化し、その上で改めてその特質の軽からざる一端を浮かび上がらせることにもつながるからである。”(p.114)
東 栄一郎 著
飯島真里子・今野裕子・佐原彩子・佃 陽子 訳
税込5,940円/本体5,400円
A5判・上製・430頁
ISBN978-4-8158-1092-4 C3021
在庫有り
『アジア経済』 [第64巻第2号、2023年6月] から(評者:湊照宏氏)
塩と帝国
近代日本の市場・専売・植民地

前田廉孝著『塩と帝国』が、『アジア経済』(第64巻第2号、2023年6月、ジェトロ・アジア経済研究所発行)で紹介されました。帝国日本の経済と生命を支えた一次産品、塩の生産・流通・消費の動態をトータルに解明、植民地塩の内地への浸透プロセスを専売や瀬戸内塩業も視野にとらえて、忘れられた塩の経済圏の全体像を示すとともに、戦後へとつながる食料、資源の対外依存構造のルーツを描き出します。
“…… 本書の特徴は、分析対象時期を絞った上で当該期における生産・流通・消費・政策の各主体に対して丁寧な考察を行っている点にある。同時期における各主体の行動が相互に影響し合い、塩専売制度が有した機能の変化と共に市場が変容していく様を描く本書のストーリー展開に、評者は引き込まれていった。その分析に用いられた一次資料は数多く、その所蔵地は地理的に広範囲で、北は北海道、南は台湾にまで及ぶ。竜王会館所蔵野崎家文書、上花輪歴史館所蔵高梨本家文書、国史館台湾文献館所蔵台湾総督府檔案・台湾塩業檔案などの貴重な一次資料から、当時における各主体の認識と行動を明らかにしている。また一次資料より得られたデータから作成された数多くの図表は、著者の主張に説得力を与えている。…… また、価格の高低のみではなく、品質の差異に着目している点も本書の特徴である。内地塩に対して植民地塩は、相対的に廉価ではあっても質的代替性に限界があった点が繰り返し強調される。こうした筆者の視点は、「1910年代に食塩供給の量的安定化・価格低廉化と需給の質的乖離が併進した」(362ページ)という本書ならではの知見の提示につながっている。……
既存の日本経済史研究は、植民地・租借地を食料・原料供給地と位置づけ、量的な自給率の上昇に着目する傾向があった。それに対して、同一商品の品質差にも注目した上で、内地・植民地それぞれにおける生産・流通・消費・政策の各主体に目を配った本書から得られる論点は、帝国内「比較優位」に基づく帝国内「分業」の形成過程について、より精緻に解明する役割を果たすことになるであろう。”(p.61, 62)
前田廉孝 著
税込8,800円/本体8,000円
A5判・上製・484頁
ISBN978-4-8158-1055-9 C3033
在庫有り
『社会経済史学』 [第89巻第1号、2023年5月] から(評者:中村美幸氏)
村の公証人
近世フランスの家政書を読む
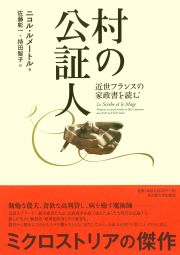
ニコル・ルメートル著『村の公証人』(佐藤彰一・持田智子訳)が、『社会経済史学』(第89巻第1号、2023年5月、社会経済史学会発行)で紹介されました。勤勉な農夫、貪欲な高利貸し、病を癒す魔術師 ——。公証人テラード一族の家長たちは、宗教戦争を経て訪れたあらたな時代を記録する。彼らが生きた物質的・精神的世界とその変容を、農村から都市にひろがる人々の繫がりとともに活写しながら、公証人が持つ「書くこと」の力に迫ります。
“本書は、16世紀末期~17世紀前半(宗教戦争末期・終結~絶対王政進展期)におけるフランス中央部バ・リムーザンのフレスリーヌ村の一農民一族の家政書を手がかりに、多面的にして重層的な農村世界と時代相への接近を試みる意欲作である。当該家政書の存在自体が発信する人的・物的諸情報を極めて該博かつ広範な知識を駆使して関連づける著者の姿勢は、歴史を掘り起こす営為の面白さと歴史研究方法の可能性の広がりを感じさせる。…… 通読のたびに著者の歴史を縦横に紡ぐ多様な糸(意図)に気づかされること再三で、バ・リムーザンのフレスリーヌ村の日常生活とフランス王国の大きなうねりとの間の時空の空隙に大小濃淡の輪郭が描き込まれていく面白さを感じた。それは、個々の事例を追究する面白さであり、その事例の分析的研究を通して包括的、全体的な解釈(仮説)を試みる面白さである。本書が「ミクロストリアの傑作」(ドリュモー「序文」)とか「フランスにおけるミクロストリアの試み」(佐藤彰一「訳者あとがき」)とか評価される所以であろう。……”(p.77-78, 82)
ニコル・ルメートル 著
佐藤彰一・持田智子 訳
税込6,380円/本体5,800円
A5判・上製・380頁
ISBN978-4-8158-1089-4 C3022
在庫有り
『社会経済史学』 [第89巻第1号、2023年5月] から(評者:渡辺昭一氏)
グローバル開発史
もう一つの冷戦
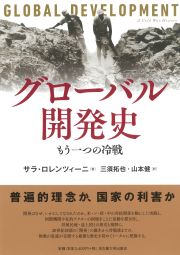
サラ・ロレンツィーニ著『グローバル開発史』(三須拓也・山本健訳)が、『社会経済史学』(第89巻第1号、2023年5月、社会経済史学会発行)で紹介されました。開発はなぜ、いかにしてなされたのか。米・ソ・欧・中の対抗関係を軸にした実践と、国際機関や私的アクターの国境をこえた活動を描き出し、旧植民地・途上国との相克も視野に、20世紀初頭の「開発」の誕生から冷戦後までの、無数の思惑が交錯する複雑な歴史を初めてトータルに把握します。
“…… 本書の魅力については次の3点を指摘しておきたい。第一は、開発の通史として、復興から開発、環境、そして人権へと1940年代から1980年代後半まで冷戦下の開発(援助)に関する言説の変遷過程をまとめていることである。…… 第二は、援助国の米ソ両陣営を対抗軸に、両陣営内の主要な地域アクター(特に EEC とその内部対立)、そして第三世界との対立・協調関係を描き出し、あまり注目されない人物や機関にも触れていることである。…… 第三は、東西両陣営と第三世界との調整の場としての国連や世界銀行などの国際機関の開発援助政策の変遷過程を追いながらその役割の変容に注目していることである。…… 本書は、第三世界との関連を追いながら米ソ両陣営およびその内部の開発計画や政策を追うことによって、20世紀を特徴づける冷戦構造とその変容が開発をグローバル化させ、その内容を同様に変容させていった過程の究明に成功していることがわかる。……”(p.87)
サラ・ロレンツィーニ 著
三須拓也・山本 健 訳
税込3,740円/本体3,400円
A5判・上製・384頁
ISBN978-4-8158-1090-0 C3022
在庫有り
『歴史学研究』 [2023年7月号、第1037号] から(評者:藤井渉氏)
戦争障害者の社会史
20世紀ドイツの経験と福祉国家
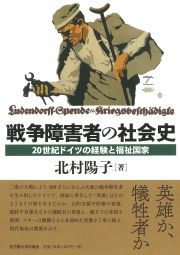
北村陽子著『戦争障害者の社会史』が、『歴史学研究』(2023年7月号、第1037号、歴史学研究会編)で紹介されました。二度の大戦により、300万人におよぶ大量の戦争障害者を生み出したドイツで、国家に奉仕した「英雄」はどのようなその後を生きたのか。公的支援や医療の発達、義肢や盲導犬などの補助具の発展と、他方での差別や貧困、ナチへの傾倒などの多面的な実態を丁寧に描き、現代福祉の淵源を示します。
北村陽子 著
税込5,940円/本体5,400円
A5判・上製・366頁
ISBN978-4-8158-1017-7 C3022
在庫有り
『本の雑誌』 [2023年7月号] から(評者:円城塔氏)
統計学を哲学する

大塚淳著『統計学を哲学する』が、『本の雑誌』(2023年7月号、本の雑誌社発行)で紹介されました。統計学は実験や臨床試験、社会調査だけでなく、ビッグデータ分析やAI開発でも不可欠である。ではなぜ統計は科学的な根拠になるのか? 帰納推論や因果推論の背後に存在する枠組みを浮き彫りにし、科学的認識論としてデータサイエンスを捉え直します。
大塚 淳 著
税込3,520円/本体3,200円
A5判・並製・248頁
ISBN978-4-8158-1003-0 C3010
在庫有り
「四国新聞」 [2023年6月11日付] から
殉教の日本
近世ヨーロッパにおける宣教のレトリック
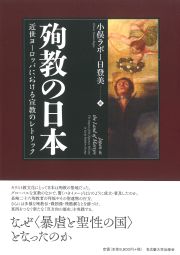
小俣ラポー日登美著『殉教の日本』が、「四国新聞」(2023年6月11日付)で紹介されました。キリスト教文化にとって、日本は〈暴虐と聖性の国〉だった。グローバルな宣教のなかで、驚くべきイメージはどのように成立・普及したのか。長崎二十六殉教者の列福やその聖遺物の行方、さらには多様な殉教伝・磔図像・残酷劇などを跡づけ、東西をつなぐ新たな「双方向の歴史」を実践します。
“…… 日本史では、キリスト教が西欧列強の侵略の先兵だったと解釈するのが一般的。西欧側が日本での宗教的受難を強調するのは、自分たちを歴史的強者と考える価値観があるとの指摘は興味深い。”(第9面)
小俣ラポー日登美 著
税込9,680円/本体8,800円
A5判・上製・600頁
ISBN978-4-8158-1119-8 C3022
在庫有り
『外交』 [第79号、2023年6月] から
アメリカの人種主義
カテゴリー/アイデンティティの形成と転換
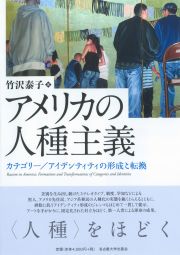
竹沢泰子著『アメリカの人種主義』が、『外交』(第79号、2023年6月、外務省発行)で紹介されました。差別を生み出し続けたステレオタイプ、制度、学知などによる黒人、アメリカ先住民、アジア系移民の人種化の実態を鋭くとらえるとともに、排除に抗うアイデンティティ形成のジレンマもはじめて一貫して提示、アートを手がかりに、固定化された対立をほどく、第一人者による渾身の成果。
“「黒人大統領」「アジア系移民」など、アメリカ社会を語る際に多用される「人種」カテゴリー。生物学的実体がないにもかかわらず、なぜ「人種」間で新型コロナによる入院患者数の大きな格差を生むまでになったのか ——。本書が実証するのは、広告や科学言説、社会制度などを通じて、ステレオタイプや差別が再生産される社会システムだ。人種主義を「ほどく」ためには何が必要なのか。個人の実践を踏まえて問いかける。”(p.157)
竹沢泰子 著
税込4,950円/本体4,500円
A5判・上製・516頁
ISBN978-4-8158-1118-1 C3022
在庫有り
『宗教研究』 [406号、2023年6月] から(評者:菊地智氏)
〈叫び〉の中世
キリスト教世界における救い・罪・霊性

後藤里菜著『〈叫び〉の中世』が、『宗教研究』(406号、2023年6月、日本宗教学会発行)で紹介されました。中世ヨーロッパは叫び声に満ちていた ——。修道士や「敬虔な女性たち」の内心の叫びから、異界探訪譚が語る罪人の悲鳴、さらには少年十字軍や鞭打ち苦行運動に伴う熱狂まで、キリスト教世界に響き渡る多様な〈声〉に耳を傾け、霊性史・感情史の新生面を切り拓く気鋭の力作。
後藤里菜 著
税込5,940円/本体5,400円
A5判・上製・364頁
ISBN978-4-8158-1040-5 C3022
在庫有り
『宗教研究』 [406号、2023年6月] から(評者:赤江達也氏)
宗教文化は誰のものか
大本弾圧事件と戦後日本
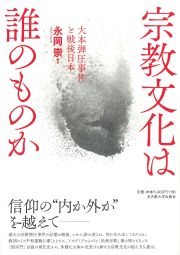
永岡崇著『宗教文化は誰のものか』が、『宗教研究』(406号、2023年6月、日本宗教学会発行)で紹介されました。信仰の “内か外か” を越えて ——。最大の宗教弾圧事件の記憶は戦後、いかに読み直され、何を生み出してきたのか。教団による平和運動を導くとともに、アカデミアにおける「民衆宗教」像の核ともなった「邪宗門」言説の現代史から、多様な主体が交差する新たな宗教文化の捉え方を提示。
“本書は、日本近代宗教史の新たな可能性を切りひらく重要な書物である。…… 教団という枠組みを越えて広がる「宗教文化」をどのように記述していくのか。本書の魅力的な歴史記述は、その課題に対する優れた応答である。大本の研究として重要なものであることはもちろんだが、それと同時に、宗教研究(宗教文化研究)におけるひとつの到達点として読まれるべき著作である。……”(p.156)
永岡 崇 著
税込5,940円/本体5,400円
A5判・上製・352頁
ISBN978-4-8158-1005-4 C3014
在庫有り
『週刊読書人』 [2023年6月9日号、第3492号] から(評者:仲正昌樹氏)
消え去る立法者
フランス啓蒙における政治と歴史

王寺賢太著『消え去る立法者』が、『週刊読書人』(2023年6月9日号、第3492号、読書人発行)で紹介されました。かつてこんなふうに読まれたことがあっただろうか ——。モンテスキューとルソー、そしてディドロへ。彼らが格闘し、解き明かし、残した問題とは何か。新たな共同体の創設という課題に直面し、法の根拠を問い直す重層的なテクストを読み抜き、「啓蒙」をクリシェから解き放った、気鋭の力作。
王寺賢太 著
税込6,930円/本体6,300円
A5判・上製・532頁
ISBN978-4-8158-1120-4 C3010
在庫有り
「朝日新聞be on Saturday」 [2023年6月10日付] から
パチンコ産業史
周縁経済から巨大市場へ
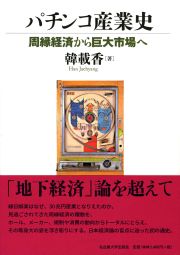
韓載香著『パチンコ産業史』が、「朝日新聞be on Saturday」(2023年6月10日付)の「はじまりを歩く」で紹介されました。戦前以来の縁日娯楽はなぜ、30兆円産業となりえたのか。見過ごされてきた周縁経済の躍動を、ホール、メーカー、規制の動向からダイナミックに捉え、「地下経済」論を超えた等身大の姿を浮き彫りにする。産業が存続可能となる条件を新たな視点で照射し、日本経済論の盲点に迫った初の通史。
韓 載香 著
税込5,940円/本体5,400円
A5判・上製・436頁
ISBN978-4-8158-0898-3 C3033
在庫有り
『週刊読書人』 [2023年4月7日号、第3484号] から(評者:藤谷悠氏)
「ひきこもり」と「ごみ屋敷」
国境と世代をこえて

古橋忠晃著『「ひきこもり」と「ごみ屋敷」』が、『週刊読書人』(2023年4月7日号、第3484号、読書人発行)で紹介されました。日本だけではない。若者だけではない。—— 共通性と違いに目を向けることで、初めて見えてくる処方箋。著者自身の国内外での臨床経験と、精神医学の知見を踏まえつつ、当事者と向きあい、社会に問いかける、「ひきこもり」「ごみ屋敷」問題を根本から考え直す洞察の書。
古橋忠晃 著
税込3,520円/本体3,200円
四六判・上製・284頁
ISBN978-4-8158-1113-6 C3036
在庫有り
『史学雑誌』 [2023年4月号、第132編第4号] から(評者:大田由紀夫氏)
東アジア国際通貨と中世日本
宋銭と為替からみた経済史
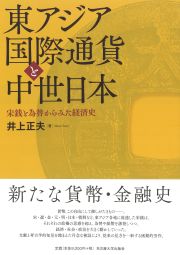
井上正夫著『東アジア国際通貨と中世日本』が、『史学雑誌』(2023年4月号、第132編第4号、史学会発行)で紹介されました。貨幣、この自由にして御しがたきもの ——。宋・遼・金・元・明・日本・朝鮮など、東アジア各地に流通した宋銭は、それぞれの政権の思惑を超え、為替や紙幣を誘発しつつ、経済・社会・政治を大きく動かしていった。文献と考古学的知見を踏まえた丹念な検証により、従来の見方を一新する画期的な貨幣・金融史。
“…… 本書の特徴は、中国とその周辺地域(遼・朝鮮など)では10世紀以降の、日本ならば古代・中世の貨幣史を考察し、議論が幅広い時代・地域・題材におよぶことである。そして、銭貨流通・金融制度に関するさまざまな先行研究の議論をよく吟味した上で、実証と理論の両面での整合的理解のあくなき追究に努め、その結果として東アジア貨幣史をめぐる豊富な知見を提供している。本書の意義として、ひとまずつぎの3点があげられる。
1つめは、東アジアで流通した銅銭に関して多くの事柄を明らかにした点である。…… 2つめは、銭貨流通を基礎として中国・日本で登場する金融制度(為替・紙幣)の発達やしくみを実証的・理論的に解明した点である。…… そして3つめは、中世日本に関してだが、為替制度の考察結果に基づき銅銭流通と金融制度の展開を有機的に結びつけた貨幣史像を構築している点である。……”(p.49)
井上正夫 著
税込8,800円/本体8,000円
A5判・上製・584頁
ISBN978-4-8158-1061-0 C3033
在庫有り
『日本医史学雑誌』 [第69巻第1号、2023年3月] から(評者:渡部幹夫氏)
ツベルクリン騒動
明治日本の医と情報
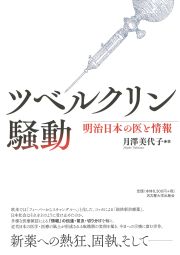
月澤美代子著『ツベルクリン騒動』が、『日本医史学雑誌』(第69巻第1号、2023年3月、日本医史学会発行)で紹介されました。欧米では「フィーバーからスキャンダルへ」と化した、コッホによる「結核新治療薬」。日本社会はそれをどのように受け止めたのか。多様な医療雑誌による「情報」の伝達・普及・切り分けを軸に、近代日本の医学・医療の風土が形成される転換期の実相を描き、今日への示唆に富む労作。
“…… 評者は著者の「情報」の伝達・普及・切り分けの試みを、明治の結核に対する医学界・社会・行政の一コマについての大変な労作として読ませていただいた。…… 日本の明治における「ツベルクリン騒動」の記録として、これだけ多くの資料をまとめた努力に敬服するとともに、近代日本医学史の新しい観かたを教えてくれたことに感謝する。”(p.130)
月澤美代子 著
税込6,930円/本体6,300円
A5判・上製・504頁
ISBN978-4-8158-1101-3 C3021
在庫有り
『図書新聞』 [2023年6月10日号、第3594号] から(評者:水溜真由美氏)
戦後表現
Japanese Literature after 1945

坪井秀人著『戦後表現』が、『図書新聞』(2023年6月10日号、第3594号、武久出版発行)で紹介されました。アジア太平洋戦争から冷戦、昭和の終わり、湾岸・イラク戦争、ポスト3・11まで、戦争をめぐる言葉がすくい上げてきたもの、底に沈めてきたものを、詩・小説・批評を中心に精緻に読解。経験や記憶に刻まれた〈傷跡〉としての表現の重層性から、〈戦後〉概念を再審にかけます。
“…… 本書の中で特に印象に残った章の1つは第Ⅴ部第4章「過ぎ去っていく過去 —— 湾岸戦争詩論争まで」であった。この章において著者は、湾岸戦争詩論争を1950年代半ばの『死の灰詩集』論争と1982年の文学者の反核声明をめぐる論争の反復として位置づける。このうち『死の灰詩集』論争では、アメリカの水爆実験に起因する第五福竜丸の被爆に抗議するために編まれた『死の灰詩集』に対して、鮎川信夫が、『死の灰詩集』の書き手の多くが戦中に愛国詩を書いていた事実を喝破して詩人の戦争責任を問題化した。著者はこの鮎川の批判を想起しつつ、「政治的な大状況への応答を依頼されて詩を書く」ことの問題を、「詩人たちの表現の自立性をねじ曲げてしまうこと」であり、「便乗的な時局詩の汚濁に詩人がまみれてしまうこと」であると論じる。もっともこうした批判は湾岸戦争詩論争の時点では目新しいものではなく、湾岸戦争詩論争は「最初からゲーム・オーヴァー」だった。
他方で著者は、出来事を情報としてしか知らない詩人が書いている点に、戦中の愛国詩から湾岸戦争詩に至る戦争詩の共通点を認める。湾岸戦争は「メディア・ウォー」と呼ばれたが、今日においては、インターネット空間の中であらゆる出来事がヴァーチャル化している。文学による「政治的な大状況」への介入はますます困難になっていると言えよう。著者は、「出来事はデータと見なされてしまい、データとデータの間の有機的な時間の流れが寸断されてしまう。そしてデータはデータであることにおいて、いつでも消去可能なのだ」と述べ、今日における歴史の解体現象と「忘却の病」の進行に対する強い焦りを表明する。
こうした事態に対処するために必要なのは、出来事と出来事の結びつきや出来事の背後にある歴史的な文脈について開かれた場で語り、他者と共有する姿勢であろう。本書が対象としている歴史を紡いでいくための語りの力こそが求められている。”(第3面)
坪井秀人 著
税込6,930円/本体6,300円
A5判・上製・616頁
ISBN978-4-8158-1116-7 C3095
在庫有り
「読売新聞」 [2023年5月28日付] から(評者:遠藤乾氏)
消え去る立法者
フランス啓蒙における政治と歴史

王寺賢太著『消え去る立法者』が、「読売新聞」(2023年5月28日付)で紹介されました。かつてこんなふうに読まれたことがあっただろうか ——。モンテスキューとルソー、そしてディドロへ。彼らが格闘し、解き明かし、残した問題とは何か。新たな共同体の創設という課題に直面し、法の根拠を問い直す重層的なテクストを読み抜き、「啓蒙」をクリシェから解き放った、気鋭の力作。
“ばらばらな個人から社会はどうできるのか。政治はいつ現れ、国家や政府、法律はどのような歴史のなかで成立するのか。そんな根本的な問いに政治思想史は答えてきた。なかでも、モンテスキューやルソーといった18世紀フランスの啓蒙主義者は、近代がはやくも揺らぐなか、先行するホッブズと格闘しながら、そうした問いに取り組んだ。
本書は、その思索の湖や概念の森に深く分けいる。その際、プラトン以来論争の的であった「立法者」——「正統な政治共同体の(再)創設者」—— のあり方を手がかりに、語りつくされたかに見える古典に斬新な切りこみをいれ、現代に生きるわれわれにその意味を突きつける。……
ルソーがモンテスキューを転倒させ、歴史を過去からの制約としてでなく、潜在的な人民主権が顕在化しうる未来に投射しているのを見てとるとき、いまある政治や社会をいつでも転覆しうる可能性がそこに留保されよう。”(第13面)
王寺賢太 著
税込6,930円/本体6,300円
A5判・上製・532頁
ISBN978-4-8158-1120-4 C3010
在庫有り
「考える人」 [新潮社ウェブマガジン、リレー書評「たいせつな本 —— とっておきの10冊」、2023年5月19日] から
明代とは何か
「危機」の世界史と東アジア

岡本隆司著『明代とは何か』が、「考える人」(新潮社ウェブマガジン、2023年5月19日)の「たいせつな本 —— とっておきの10冊」で紹介されました。現代中国の原型をかたちづくるとともに、東アジア史の転機ともなった明代。世界的危機の狭間で展開した財政経済や社会集団のありようを、室町期や大航海時代との連動もふまえて彩り豊かに描くとともに、民間から朝廷まで全体を貫く構造を鋭くとらえ、新たな時代像を提示します。
岡本隆司 著
税込4,950円/本体4,500円
A5判・上製・324頁
ISBN978-4-8158-1086-3 C3022
在庫有り
『歴史学研究』 [2023年6月号、第1036号] から(評者:石野一晴氏)
関羽と霊異伝説
清朝期のユーラシア世界と帝国版図
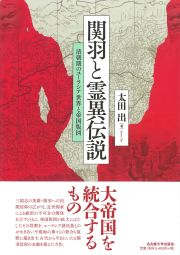
太田出著『関羽と霊異伝説』が、『歴史学研究』(2023年6月号、第1036号、歴史学研究会編)で紹介されました。三国志の英雄はなぜ中国を代表する神となったのか。民間信仰の広がりと近世国家による統治の不可分の関係を示すとともに、帝国版図の拡大にはたしたその役割を、ユーラシア諸民族とのせめぎあいや現地の神々との習合も視野に描き出します。古代から今日にいたる関羽信仰の全貌を捉えた力作。
“…… 本書は、本邦の歴史学分野における最も優れた関羽信仰研究と言える。宗教研究が取り上げない檔案史料、とりわけ軍事関係の記録を紐解き清朝の関帝信仰を解明しようとする試みはこれまで存在しなかった。地方志などの史料を網羅的に博捜し、具体的史料を多数提示することに成功しているのは、ひとえに著者の並々ならぬ熱意の賜物にほかならない。それらの史料が平明な現代語訳によって提示されることで、関帝信仰の具体相が読者の前に生き生きと立ち現れてくる。
これらの多様な史料の分析から、中国近世において宗教が大きな影響力を持っていたこと、王朝が宗教を通じて民衆を統治しようとしていたことなど、中国史を理解する上で重要な視点を『三国志』で有名な関羽という題材を通じて再確認する意義は大きい。さらに議論を漢人の世界に止めるのではなく、ユーラシア大陸全体まで広げるスケールの大きさは従来の研究にはまったく見られなかったものである。今後、清朝の国家と宗教をめぐる問題を論ずる上で、避けて通れない研究となることは間違いない。……”(p.70)
太田 出 著
税込5,940円/本体5,400円
A5判・上製・324頁
ISBN978-4-8158-0961-4 C3022
在庫有り
『図書新聞』 [2023年5月27日号、第3592号] から(評者:松田美枝氏)
「ひきこもり」と「ごみ屋敷」
国境と世代をこえて

古橋忠晃著『「ひきこもり」と「ごみ屋敷」』が、『図書新聞』(2023年5月27日号、第3592号、武久出版発行)で紹介されました。日本だけではない。若者だけではない。—— 共通性と違いに目を向けることで、初めて見えてくる処方箋。著者自身の国内外での臨床経験と、精神医学の知見を踏まえつつ、当事者と向きあい、社会に問いかける、「ひきこもり」「ごみ屋敷」問題を根本から考え直す洞察の書。
“…… 本書全体を通して、特に印象に残るのは、「ひきこもり」(および「ごみ屋敷」)は、空間的な問題ではなく社会関係の問題であると、一貫して述べられている点である。コロナ禍で自宅にこもっていたとしても、それだけでは「ひきこもり」であることにはならない。家の中が散らかっているという事実だけで、「ごみ屋敷」ということにはならないからである。そうではなく、社会的に望ましいとされるあり方や、それを正しいと考える他者からの圧力を巡って、「主体」が自らを何処にどのように位置付けるのか、ということが問題になっているのである。そのように考えを整理してみると、支援者である読者の日常の臨床や、家族である読者の日々の関わりにおいて、少し心の余裕をもって、本人と関われるのではないだろうか。”(第3面)
古橋忠晃 著
税込3,520円/本体3,200円
四六判・上製・284頁
ISBN978-4-8158-1113-6 C3036
在庫有り
『図書新聞』 [2023年5月27日号、第3592号] から(評者:西平等氏)
国際法を編む
国際連盟の法典化事業と日本

高橋力也著『国際法を編む』が、『図書新聞』(2023年5月27日号、第3592号、武久出版発行)で紹介されました。大国中心の法創造プロセスに風穴をあけ、初めて幅広い主体に国際法を開いた国際連盟の法典化事業。特に積極的な貢献をみせた日本を軸に、失敗とされたハーグ会議の意義を再評価、国益の追求にとどまらない法律家の実像を活写し、国際法の歴史を外交史的アプローチもふまえて描き直します。
“…… 困難にぶつかって、国際連盟の法典化作業は目立った成果を残すことができないまま終わる。しかし、著者は、しばしば「失敗」と呼ばれてきたそのような作業の中に、国際法の発展を促進する議論の蓄積を見出し、さらには、日本外交官や専門家がそこにおいて果たした積極的な役割を明らかにしようとする。…… 法典化作業における日本の役割を包括的に再検討した本書には、国際連盟と日本の関係を新たな側面から見直すという重要な意義がある。……”(第5面)
高橋力也 著
税込9,900円/本体9,000円
A5判・上製・546頁
ISBN978-4-8158-1111-2 C3032
在庫有り
『法制史研究』 [第72号、2023年3月] から(評者:嘉藤慎作氏)
奴隷貿易をこえて
西アフリカ・インド綿布・世界経済
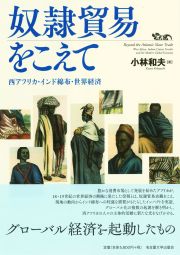
小林和夫著『奴隷貿易をこえて』が、『法制史研究』(第72号、2023年3月、法制史学会発行)で紹介されました。豊かな消費市場として発展を始めたアフリカが、18・19世紀の世界経済の興隆に果たした役割とは。奴隷貿易史観をこえ、現地の動向からインド綿布への旺盛な需要がもたらしたインパクトを実証、グローバル化の複数の起源を解き明かし、西アフリカの人々の主体的活動に新たな光をなげかけます。
“…… 本書の意義を3つ挙げたい。第一に、グローバル化の多元性についてヨーロッパを介した西アフリカと南アジアとの関係を事例として実証的に描き出したことである。…… 史料を用いた実証に加えて、背景にある連関を丁寧に読み解きつつ、他地域との比較もおこなうことで、実証的なグローバル・ヒストリー研究の1つの形を示したと言えるだろう。
第二に、ヨーロッパと西アフリカとの貿易におけるインド綿布の重要性に鑑みて、大西洋貿易論における問題点を指摘して、新しいモデルを提示した点である。……
本書が日本語で刊行されたことも意義深い。…… 西アフリカ経済史に加え、グローバル・ヒストリーについても先行研究を渉猟して本書を執筆しており、その点で本書は最新の成果を示す研究書でありながら、初学者にとって有用な手引としての役割も果たしうる。…… ”(pp.418-419)
小林和夫 著
税込6,380円/本体5,800円
A5判・上製・326頁
ISBN978-4-8158-1037-5 C3022
在庫有り
『図書新聞』 [2023年5月20日号、第3591号] から(評者:古家弘幸氏)
イギリス思想家書簡集 アダム・スミス

篠原久・只腰親和・野原慎司訳『イギリス思想家書簡集 アダム・スミス』(シリーズ監修者 田中秀夫・坂本達哉)が、『図書新聞』(2023年5月20日号、第3591号、武久出版発行)で紹介されました。親密圏と公共圏のあいだで、知的コミュニケーションの場として決定的位置をしめた手紙。知られざる論点、新たなアイディアが書物とは異なるかたちで問いかけられ表明され、人々を動かしていく。『国富論』など主著には現れない見解からヒュームとの交友まで、精彩に富むスミス書簡の初の全訳。
篠原 久・只腰親和・野原慎司 訳
(シリーズ監修者 田中秀夫・坂本達哉)
税込6,930円/本体6,300円
A5判・上製・502頁
ISBN978-4-8158-1107-5 C3010
在庫有り
『ドイツ研究』 [第57号、2023年3月] から(評者:藤原辰史氏)
政治的暴力の共和国
ワイマル時代における街頭・酒場とナチズム
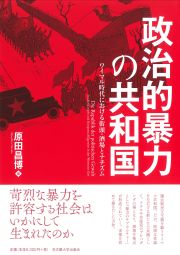
原田昌博著『政治的暴力の共和国』が、『ドイツ研究』(第57号、2023年3月、日本ドイツ学会発行)で紹介されました。苛烈な暴力を許容する社会はいかにして生まれたのか ——。議会制民主主義を謳うワイマル共和国。だが、街頭は世論を左右する新たな公共圏として、ナチスや共産党のプロパガンダの場となり、酒場を拠点とした「暴力のサブカルチャー」が形成されていく。実像を初めて描きだした力作。
“……『政治的暴力の共和国』と題されたこの書物の中で、著者は、政治的暴力に怯えていた人びとではなく、それに魅せられていた人びとに着目せよと読者を誘う。私なりにいささか過剰に読み込むならば、多分本書は、言葉の代わりに放たれる暴力のスペクタクルに、その行為者として、あるいは、受け手として魅せられるかもしれない(あるいは、傍観し続けるかもしれない)「私たち」の心の奥底を掘り起こし、その上で政治とは何かを改めて考えよ、というタフな問いをつきつけている。政治概念そのものを問い直さずにはいられなくなるのが、本書の魅力である。
実際、結論部分で著者は、「民主主義を標榜するワイマル憲法をもつ社会であっても、暴力が忌避されず、むしろ一部の(決して少なからぬ)者に「魅力」すら与えていた」ことを重視し、「暴力をためらわない非言論的・非議会主義的な政党であると知りながら、人びとはナチスに投票したのであり、共産党も含めて暴力を隠すことのない政党が実際に暴力を行使する中で選挙での得票を増加させ、逆に暴力に対して消極的な政党の得票が減少した」事実を直視するように読者を誘っている(297頁)。
政治の野蛮化が進む現代社会において、このスリリングでチャレンジングな研究の成果が、各所の文書館に収められた警察・検察関連資料の精緻な分析をともなって刊行されたことを、私は、ドイツ史を研究する人間だけではなく、政治に関心のある全ての人びとにとってきわめて意義のあることだと考える。……”(p.40)
原田昌博 著
税込6,930円/本体6,300円
A5判・上製・432頁
ISBN978-4-8158-1039-9 C3022
在庫有り
『地図情報』 [第43巻第1号、2023年5月] から(評者:川村博忠氏)
絵図の史学
「国土」・海洋認識と近世社会
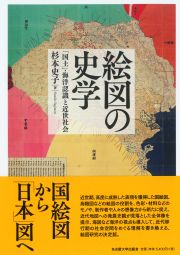
杉本史子著『絵図の史学』が、『地図情報』(第43巻第1号、2023年5月、地図情報センター発行)で紹介されました。近世期、高度に成熟した表現を獲得した国絵図、鳥瞰図などの絵図の役割を、色彩・材料などのモノや、制作者や人々の想像力から新たに捉え、近代地図への発展史観が見落とした全体像を提示、海図など海洋の視点も導入して、近代移行期の社会空間をめぐる理解を書き換える、絵図研究の決定版。
“…… 本書は近世から近代移行期まで、わが国での地図作成の流れを政治と社会との関連でとらえているが、とりわけ近代移行期の海洋認識による国土理解の新展開を詳しく解説している。本書では最後にまとめて掲載する脚注の詳細さが並はずれている。…… 歴史地理学の研究を試みようとするものにとっては、手元に備えておくべき必携の書である。”(p.34)
杉本史子 著
税込5,940円/本体5,400円
A5判・上製・440頁
ISBN978-4-8158-1062-7 C3021
在庫有り
『日本歴史』 [2023年5月号、第900号] から(評者:落合功氏)
塩と帝国
近代日本の市場・専売・植民地

前田廉孝著『塩と帝国』が、『日本歴史』(2023年5月号、第900号、日本歴史学会編)で紹介されました。帝国日本の経済と生命を支えた一次産品、塩の生産・流通・消費の動態をトータルに解明、植民地塩の内地への浸透プロセスを専売や瀬戸内塩業も視野にとらえて、忘れられた塩の経済圏の全体像を示すとともに、戦後へとつながる食料、資源の対外依存構造のルーツを描き出します。
“…… 従来の近代塩業史研究は国内塩業だけで議論されることが多かった。この点、本書では、台湾塩、関東州塩など植民地塩の果たした役割が大きいことを明らかにし、それは、近代の経済構造そのものであることを示している。
この点で、近代経済史を考えるとき、植民地経済の問題を国内経済と相対的にとらえてきたが、本書では経済圏として一体的に理解しようとしたことに本書の積極的な評価となるだろう。……”(p.141)
前田廉孝 著
税込8,800円/本体8,000円
A5判・上製・484頁
ISBN978-4-8158-1055-9 C3033
在庫有り
『歴史学研究』 [2023年5月号、第1035号] から(評者:長田浩彰氏)
政治的暴力の共和国
ワイマル時代における街頭・酒場とナチズム
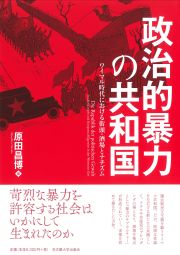
原田昌博著『政治的暴力の共和国』が、『歴史学研究』(2023年5月号、第1035号、歴史学研究会編)で紹介されました。苛烈な暴力を許容する社会はいかにして生まれたのか ——。議会制民主主義を謳うワイマル共和国。だが、街頭は世論を左右する新たな公共圏として、ナチスや共産党のプロパガンダの場となり、酒場を拠点とした「暴力のサブカルチャー」が形成されていく。実像を初めて描きだした力作。
原田昌博 著
税込6,930円/本体6,300円
A5判・上製・432頁
ISBN978-4-8158-1039-9 C3022
在庫有り
『アートコレクターズ』 [2023年5月号、著者インタビュー] から
共和国の美術
フランス美術史編纂と保守/学芸員の時代
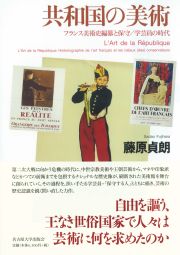
『共和国の美術』(藤原貞朗著)の著者インタビューが、『アートコレクターズ』(2023年5月号、生活の友社発行)に掲載されました。王なき世俗国家で人々は芸術に何を求めたのか。戦争に向かう危機の時代に、中世宗教美術や王朝芸術から、かつての前衛までを包摂するナショナルな歴史像が、刷新された美術館を舞台に創られていく。その過程を、担い手たる学芸員=「保守する人」とともに描き、芸術の歴史性を問い直します。
“—— 現在でも影響力を持つ当時の活動がなぜ研究の俎上に載らないのでしょうか。
第二次大戦後に自由主義陣営となる上で、保守的なフランス美術史が黒歴史だったからです。事実当時の学芸員の中にはナチスの芸術政策を支持した人も少数ながらいますし、保守的な美術史観の構造もかなり似通っていました。そのため、自由フランスが真のフランスだと自称するためには、当時の美術史観を直ちに捨て去る必要があったのです。
しかし、当時作られた美術史やルーブル美術館の展示方法などは基本的に継承されています。結果として保守的な政治思想が忘却され形だけが残っている歪な状態が現在です。研究でもこの分野は真空地帯になっており、文字通り何もなかったかのように見做されていますが、そのような状況こそが最も恐ろしいのではないでしょうか。
確かに、美術家においても批評家においてもこの時期のフランスには際立った天才がいませんでした。この時期の美術家個人の研究は盛んですが、より大きな全体意思を相手にすると、研究のハードルはかなり上がります。だからこそ、本書では作家や批評家の思想を追うのではなく、様々な人物の具体的な行動を歴史の主要なファクターにすることで、自ずと浮かび上がってくる時代の空気を捉えようとしました。……”(p.137)
藤原貞朗 著
税込6,930円/本体6,300円
A5判・上製・454頁
ISBN978-4-8158-1110-5 C3071
在庫有り
『大原社会問題研究所雑誌』 [第775号、2023年5月号] から(評者:ジャネット・ハンター氏)
日本綿業史
徳川期から日中開戦まで
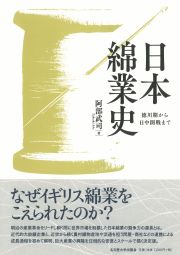
阿部武司著『日本綿業史』が、『大原社会問題研究所雑誌』(第775号、2023年5月号、法政大学大原社会問題研究所発行)で紹介されました。明治の産業革命をリードし瞬く間に世界市場を制覇した日本綿紡績・織物業の競争力の源泉とは。近代的大紡績企業と、近世から続く農村織物産地や流通を担う問屋・商社などの連携による成長過程を初めて解明、衰退に向かう戦後も視野に、巨大産業の興隆を圧倒的な密度とスケールで描く決定版。
“明治初期から1930年代後半にかけての日本の綿業について、阿部武司教授ほど包括的な歴史を書ける学者はいないと思われるが、本書はその期待を裏切らない。本書は、長年にわたる先行研究と著作、関連文献の総合的な知識、そして熟考に基づき、1930年代に日本の伝統的な綿業が世界一の輸出国にまで発展した経緯について理解を深めようとするすべての読者にとって「必読書」となることだろう。本書は、このテーマに対して革新的なアプローチをとっている。特に、これまでの研究の多くが、日本の近代的な大規模紡績会社の成長と、より伝統的な織物産地の成長のどちらかに焦点を当てる傾向があったのに対し、この分析では、両方の考察を組み合わせることにより、綿織物の製造と販売に関わる生産と企業の全範囲を探求することができるようになっている。その結果、日本経営史のみならず、世界経済における日本綿業の意義や、日本の工業化の全体的な過程について、新たな洞察を得ることができる。また、労働集約的な工業化の重要性や、日本の発展における近代産業と「在来」産業の両企業の意義など、現在進行中の議論に新たな視点から関与することができるのである。……”(p.73)
阿部武司 著
税込7,920円/本体7,200円
A5判・上製・692頁
ISBN978-4-8158-1059-7 C3033
在庫有り
『日伊文化研究』 [第61号、2023年3月] から(評者:飯田巳貴氏)
近世東地中海の形成
マムルーク朝・オスマン帝国とヴェネツィア人

堀井優著『近世東地中海の形成』が、『日伊文化研究』(第61号、2023年3月、日伊協会発行)で紹介されました。古くから東西交易の要衝として栄えた「レヴァント」。中世から近世への転換のなか、イスラーム国家とヨーロッパ商人の「共生」を支えてきた秩序の行方は? オスマン条約体制や海港都市アレクサンドリアのありようから、異文化接触の実像を明らかにするとともに、東アジアに及ぶ「治外法権」の淵源をも示した力作。
“…… 本書の特徴はおよそ4つに大別できよう。第一に、従来専らカピチュレーション(商業特権、治外法権)の問題として扱われてきたオスマン帝国君主から友好関係にある西欧諸国に与えられた条約が、オスマン条約体制のなかで整理し直されている事である。…… 第二に、「オスマン条約体制」すなわちアフドナーメの多様な規定と関連する原理原則、法令、慣習、制度、運用の仕組みが解説され、続いて「規範構造」すなわち条約文書に記された規定そのものと、個別具体的な規定に内在する原理原則の実態とその変遷が、アフドナーメ本文にアラビア語・イタリア語史料の分析も加えて検討されている事である。……第三に、条約の規範が現実に呼応して継続又は変容する過程が具体的に検討された事である。…… 最後に特記すべきは、主要一次史料がアラビア語、オスマン語、イタリア語(ヴェネツィア方言)等多言語にわたる事である。…… 一人の研究者が国家や地域ごとに異なる一次史料や文書史料の体系を熟知し多言語の史料を読みこなす事は容易ではない。管見の限り、この点でも堀井氏は国内外の研究者のなかで傑出している。本書は地中海および周辺地域の歴史、さらに地中海世界に限らず国際条約体制の歴史に関心を持つ者にとっても必読の書である。”(p.89)
堀井 優 著
税込5,940円/本体5,400円
A5判・上製・240頁
ISBN978-4-8158-1053-5 C3022
在庫有り
「朝日新聞」 [2023年4月22日付] から(評者:椹木野衣氏)
共和国の美術
フランス美術史編纂と保守/学芸員の時代
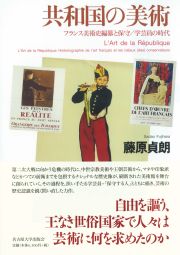
藤原貞朗著『共和国の美術』が、「朝日新聞」(2023年4月22日付)で紹介されました。王なき世俗国家で人々は芸術に何を求めたのか。戦争に向かう危機の時代に、中世宗教美術や王朝芸術から、かつての前衛までを包摂するナショナルな歴史像が、刷新された美術館を舞台に創られていく。その過程を、担い手たる学芸員=「保守する人」とともに描き、芸術の歴史性を問い直します。
藤原貞朗 著
税込6,930円/本体6,300円
A5判・上製・454頁
ISBN978-4-8158-1110-5 C3071
在庫有り
「朝日新聞」 [2023年4月22日付] から(評者:三牧聖子氏)
消え去る立法者
フランス啓蒙における政治と歴史

王寺賢太著『消え去る立法者』が、「朝日新聞」(2023年4月22日付)で紹介されました。かつてこんなふうに読まれたことがあっただろうか ——。モンテスキューとルソー、そしてディドロへ。彼らが格闘し、解き明かし、残した問題とは何か。新たな共同体の創設という課題に直面し、法の根拠を問い直す重層的なテクストを読み抜き、「啓蒙」をクリシェから解き放った、気鋭の力作。
王寺賢太 著
税込6,930円/本体6,300円
A5判・上製・532頁
ISBN978-4-8158-1120-4 C3010
在庫有り
『史学雑誌』 [2023年3月号、第132編第3号] から(評者:大黒俊二氏)
〈叫び〉の中世
キリスト教世界における救い・罪・霊性

後藤里菜著『〈叫び〉の中世』が、『史学雑誌』(2023年3月号、第132編第3号、史学会発行)で紹介されました。中世ヨーロッパは叫び声に満ちていた ——。修道士や「敬虔な女性たち」の内心の叫びから、異界探訪譚が語る罪人の悲鳴、さらには少年十字軍や鞭打ち苦行運動に伴う熱狂まで、キリスト教世界に響き渡る多様な〈声〉に耳を傾け、霊性史・感情史の新生面を切り拓く気鋭の力作。
“『〈叫び〉の中世』というタイトルは多くの読者の意表を突き戸惑わせるだろう ——〈叫び〉のような衝動的でほとんど原始的ともいえる声にそもそも歴史はあるのか、仮にあるとして西洋中世に固有の〈叫び〉を見出しうるのか、と。当然予想されるこの種の疑問に対して著者は、西洋中世の〈叫び〉を〈霊性〉の変化の中で観察することによって一つの答えを出そうとしている。本書においては〈霊性〉が〈叫び〉とともにもう一つのキーワードである。…… 〈霊性〉そのものは西洋中世研究においては聖人崇敬、修道制、神秘主義などの研究をとおして古典的なテーマといってよいが、それを〈叫び〉の観点から捉え直したところに本書のユニークさがある。本書において〈叫び〉と〈霊性〉は重なり合いまた対立するものとして提示されており、そのありさまを11世紀から15世紀にかけて追うことで『〈叫び〉の中世』が具体的な姿を現してくる。……”(pp.88-89)
後藤里菜 著
税込5,940円/本体5,400円
A5判・上製・364頁
ISBN978-4-8158-1040-5 C3022
在庫有り
「読売新聞」 [2023年4月16日付] から(評者:小泉悠氏)
ニュースピークからサイバースピークへ
ソ連における科学・政治・言語

スラーヴァ・ゲローヴィチ著『ニュースピークからサイバースピークへ』(大黒岳彦訳/金山浩司校閲・解説)が、「読売新聞」(2023年4月16日付)で紹介されました。統制的国家において、科学はいかにふるまうのか? 空疎なイデオロギー話法を乗り越える、厳密で普遍的な科学言語として期待されたサイバネティックス。この「自由の道具」が、数学・生物学・生理学・言語学などソ連科学界を席巻した末に、社会の科学的管理をめざして体制化していく道程をヴィヴィッドに描きだします。それは彼方の世界か、あるいは我らの鏡か?
“…… 科学史という一見地味なテーマでありながら、このアクロバティックな展開には興奮させられた。…… 翻訳も読みやすい文体であり、本書を専門書としてだけでなく、読み物としても優れたものとしている。”(第12面)
スラーヴァ・ゲローヴィチ 著
大黒岳彦 訳/金山浩司 校閲・解説
税込6,930円/本体6,300円
A5判・上製・358頁
ISBN978-4-8158-1115-0 C3022
在庫有り
「毎日新聞」 [2023年4月15日付] から(評者:岩間陽子氏)
オスマン帝国の世界秩序と外交
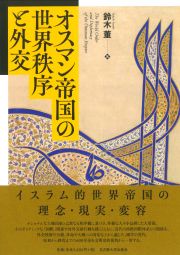
鈴木董著『オスマン帝国の世界秩序と外交』が、「毎日新聞」(2023年4月15日付)で紹介されました。イスラム的世界帝国の理念・現実・変容 ——。ナショナルな主権国家とは異なる秩序観に基づき、多様な人々を包摂した大帝国。そのダイナミックな「国際」関係や対外交渉行動を描くとともに、近代の西欧国際体系との関係を、外交使節や公館、革命や大戦への対応などから論じた、碩学の労作。原初から終焉までの600年余を文明史的視角から一望します。
鈴木 董 著
税込5,940円/本体5,400円
A5判・上製・324頁
ISBN978-4-8158-1117-4 C3022
在庫有り
『週刊読書人』 [2023年4月14日号、第3485号] から(評者:本内直樹氏)
失業を埋めもどす
ドイツ社会都市・社会国家の模索
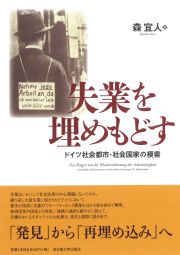
森宜人著『失業を埋めもどす』が、『週刊読書人』(2023年4月14日号、第3485号、読書人発行)で紹介されました。失業はいかにして発見され、社会政策の中心課題になったのか。繰り返し大量失業に悩まされたドイツにおいて、都市が国家に先駆けてセーフティネット構築をはかる姿を初めて解明、慈善団体や国家との対抗/連携の過程も鮮やかに捉えて、労働をめぐるモダニティの大転換を、現代も視野に描き出します。
“…… 周知のように、ドイツは19世紀末、世界で初の社会保険を導入した国である。イギリスもこれに倣い1911年に国民保険法(失業保険・健康保険)を制定した。しかし国家レベルの失業保険の点ではドイツはイギリスより十数年導入が遅れた。ところが著者はドイツの歴史的経験を辿る本書の中で、国家に先んじた失業者救済の「都市の先駆性」を強調する。
ドイツは1927年に国家の失業保険を導入したが、直後の世界恐慌で「破綻」した。これによる大量失業者の存在がナチスの台頭の一因を形成し、それまでの施策は失敗の烙印を押されてきた。ところが著者はこの通説に都市史の観点から新たな事実を発見し、これまでの議論に再検討を迫っている。その意味で、本書は従来の社会政策史研究の成果を吸収しつつも、都市史の側から新たな問題提起を試みた意欲作といえよう。……”(第7面)
森 宜人 著
税込7,480円/本体6,800円
A5判・上製・396頁
ISBN978-4-8158-1103-7 C3022
在庫有り
『中央公論』 [2023年5月号、「新刊この一冊」] から(評者:栗原悠氏)
変革する文体
もう一つの明治文学史

木村洋著『変革する文体』が、『中央公論』(2023年5月号、中央公論新社発行)の「新刊この一冊」で紹介されました。新たな文体は新たな社会をつくる ——。小説中心主義を脱し、政論・史論から翻訳・哲学まで、徳富蘇峰を起点にして近代の「文」の歩みを辿りなおし、新興の洋文脈と在来の和文脈・漢文脈の交錯から、それまでにない人間・社会像や討議空間が形づくられる道程をつぶさに描いた意欲作。
“…… 蘇峰を切り口とした一連の議論は、文学が現実社会を動かす政治や事業から隔絶されたところで人生観や個人の内面への思考を静かに深めていったとする史観を問い直し、さらに政治と文学とを画然と描き分け、前者に力点を置いて後者を顧みない歴史記述のありよう自体に再考を迫るものだ。それはさながら新しい星座を一から作りあげていくような、きわめてアクチュアルな試行と言えるだろう。
そしておそらくはそうしたドラスティックな認識の変更なしには、たとえばそれぞれ反自然主義の旗手と黎明期の自然主義の代表作家と目され、あまつさえ当人同士も批判し合っていた鏡花と国木田独歩を結びつける線が浮かび上がってくることもなかったに違いない。あるいは両者は蘇峰が持ち込んだユゴーへの熱を介して自らの小説に「深い思索」を描き込もうとした点で共振していたのだ。
本書を読み終えた時、読者はこれまでの文学史観によっては気づくことができなかったいくつもの論点が見えてくるだろう。” (p.195)
木村 洋 著
税込6,930円/本体6,300円
A5判・上製・358頁
ISBN978-4-8158-1108-2 C3095
在庫有り
『週刊社会保障』 [2023年2月27日号、第3208号] から(評者:川久保寛氏)
失業を埋めもどす
ドイツ社会都市・社会国家の模索
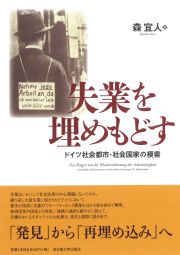
森宜人著『失業を埋めもどす』が、『週刊社会保障』(2023年2月27日号、第3208号、法研発行)で紹介されました。失業はいかにして発見され、社会政策の中心課題になったのか。繰り返し大量失業に悩まされたドイツにおいて、都市が国家に先駆けてセーフティネット構築をはかる姿を初めて解明、慈善団体や国家との対抗/連携の過程も鮮やかに捉えて、労働をめぐるモダニティの大転換を、現代も視野に描き出します。
“…… 失業や給付を切り口に、私たちを取り巻く制度・社会を考えさせる良書である。政策が正しさではなく「力」で決まるとしても、ドイツの議論と苦闘は、私たちに多くの示唆を与えてくれる。……
これまで、事前に拠出を必要とする社会保険と、拠出を必要としない扶助は、基本構造が異なることを前提に多くの議論が交わされてきたが、本書を読むと、失業をめぐる保険と扶助には当てはまらない部分が多いことに気づかされる。詳細な制度史および議論の研究から、私たちが学ぶべきことはまだある。
最後に、本書タイトルにある「埋めもどす」は絶妙な表現である。緻密な分析を通じて「埋めもどす」を見い出した筆者の論理を読み取っていただきたい。”(p.33)
森 宜人 著
税込7,480円/本体6,800円
A5判・上製・396頁
ISBN978-4-8158-1103-7 C3022
在庫有り
「朝日新聞」 [2023年4月8日付] から(評者:藤田結子氏)
アメリカの人種主義
カテゴリー/アイデンティティの形成と転換
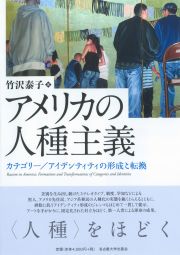
竹沢泰子著『アメリカの人種主義』が、「朝日新聞」(2023年4月8日付)で紹介されました。差別を生み出し続けたステレオタイプ、制度、学知などによる黒人、アメリカ先住民、アジア系移民の人種化の実態を鋭くとらえるとともに、排除に抗うアイデンティティ形成のジレンマもはじめて一貫して提示、アートを手がかりに、固定化された対立をほどく、第一人者による渾身の成果。
竹沢泰子 著
税込4,950円/本体4,500円
A5判・上製・516頁
ISBN978-4-8158-1118-1 C3022
在庫有り
「東京新聞・中日新聞」 [2023年4月9日付] から(評者:矢部武氏)
アメリカの人種主義
カテゴリー/アイデンティティの形成と転換
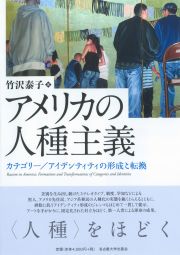
竹沢泰子著『アメリカの人種主義』が、「東京新聞・中日新聞」(2023年4月9日付)で紹介されました。差別を生み出し続けたステレオタイプ、制度、学知などによる黒人、アメリカ先住民、アジア系移民の人種化の実態を鋭くとらえるとともに、排除に抗うアイデンティティ形成のジレンマもはじめて一貫して提示、アートを手がかりに、固定化された対立をほどく、第一人者による渾身の成果。
竹沢泰子 著
税込4,950円/本体4,500円
A5判・上製・516頁
ISBN978-4-8158-1118-1 C3022
在庫有り
『図書新聞』 [2023年4月15日号、第3587号] から(評者:稲賀繁美氏)
共和国の美術
フランス美術史編纂と保守/学芸員の時代
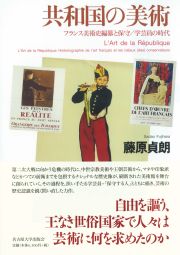
藤原貞朗著『共和国の美術』が、『図書新聞』(2023年4月15日号、第3587号、武久出版発行)で紹介されました。王なき世俗国家で人々は芸術に何を求めたのか。戦争に向かう危機の時代に、中世宗教美術や王朝芸術から、かつての前衛までを包摂するナショナルな歴史像が、刷新された美術館を舞台に創られていく。その過程を、担い手たる学芸員=「保守する人」とともに描き、芸術の歴史性を問い直します。
“…… 畏怖すべきは、従来の内外の研究で盲点として見過ごされてきた事績に思わぬ照明を当て、美術行政の地形図に鮮明な輪郭と陰影を刻む着眼の才だろう。縦軸は conservateurs つまり直訳すれば「保守役職者」たる美術館員の世代交代と遍歴、横軸は彼らが現場組織責任者となった各種展覧会、その入れ物たる美術館運営の建付けや(問題山積の)ルーヴルを含む展示会場変更の時事問題。いわばコロンブスの卵だが、この経緯を繊細執拗に究める著者の慧眼は侮れない。……
本書の鮮烈にして、時に辛辣かつ皮肉も憚らぬ「症例」腑分け手裁きの妙技には、読者各位の目で直接触れて頂くのが相応しかろう。(日本の大学受験定番の)既成の事実の集積としての暗記物の「歴史」ではなく、(帯の言葉を借りるならば)「自由を謳う王なき世俗国家で人々は芸術に何を求めたのか」、その生成の現場、過去への遡及による時代錯誤を胚胎した「歴史編纂」の錯綜する実相が、功罪ともども頁毎に立ち現れる。その戦慄を読者は本書を通じて、「史上初体験」することになるからだ。
本書は母国側での近年の博士論文の遺漏や解釈の浅慮にも逐一批判を加えつつ、犀利かつ大胆な議論を周到な筋立てで進めてゆく。実証的な裏付けを梃子に、軽薄な常識の空白を埋め、通説を塗り替える芸術社会学の手腕において、ピエール・ブルデューの『芸術の規則』をも凌駕する。……”(第8面)
藤原貞朗 著
税込6,930円/本体6,300円
A5判・上製・454頁
ISBN978-4-8158-1110-5 C3071
在庫有り
『史林』 [第105巻第6号、2022年11月] から(評者:彭皓氏)
明代とは何か
「危機」の世界史と東アジア

岡本隆司著『明代とは何か』が、『史林』(第105巻第6号、2022年11月、史学研究会発行)で紹介されました。現代中国の原型をかたちづくるとともに、東アジア史の転機ともなった明代。世界的危機の狭間で展開した財政経済や社会集団のありようを、室町期や大航海時代との連動もふまえて彩り豊かに描くとともに、民間から朝廷まで全体を貫く構造を鋭くとらえ、新たな時代像を提示します。
“…… 著者は明代における民間社会の複雑な大転換の主脈、つまり銀をめぐる交易ブームを巨視的にとらえつつ、明の政治体制に対しても、表層的政治争いにとどまらず、その構造の深部に踏み込み、硬直した政治面と激動した経済・社会面が乖離しているという明代の歴史像を巧みに描き出した。……”(pp.93)
岡本隆司 著
税込4,950円/本体4,500円
A5判・上製・324頁
ISBN978-4-8158-1086-3 C3022
在庫有り
『史林』 [第105巻第6号、2022年11月] から(評者:塩出浩之氏)
共帝国のフロンティアをもとめて
日本人の環太平洋移動と入植者植民地主義
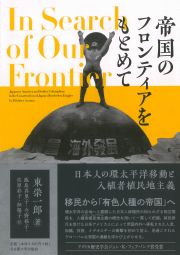
東栄一郎著『帝国のフロンティアをもとめて』(飯島真里子・今野裕子・佐原彩子・佃陽子訳)が、『史林』(第105巻第6号、2022年11月、史学研究会発行)で紹介されました。環太平洋の各地へと展開した日本人移植民の知られざる相互関係を、入植者植民地主義の概念を用いて一貫して把握。移民排斥を受けた日系アメリカ人によって帝国内外へ移転された人流、知識、技術、イデオロギーの衝撃を初めて捉え、見過ごされたグローバルな帝国の連鎖を浮かび上がらせます。
“…… 移民史研究の文脈からみた本書の大きな達成は、外国への日本人移民と植民地への日本人移民とが密接につながっていたことをアメリカの側から論証した点にある。…… 移民先である外国(アメリカ)から植民地や別の外国(中南米諸国)への再移民という人流の存在を通じて、外国への移民と植民地への移民が切り離せない現象だったことをさらに明確に示したのである。評者自身も「移民」と「植民」の連続性や比較可能性を指摘してきた研究者として、本書の主張には共感するところが大きい。
中でも重要なのは、本書が日本人による再移民の大きな要因をアメリカの人種主義や排日政策に見出し、再移民は日本の国家主権による保護を受けられる植民地や、人種的楽園と目されたブラジルへ向かったと指摘した点である。…… 本書が示すのは、アメリカに入国できずに中南米諸国や植民地を選んだ人々と異なり、いったんアメリカに入国した日本人の中にも再移民によって新たな経済的機会を求める人々がいたという事実である。……”(pp.107-108)
東 栄一郎 著
飯島真里子・今野裕子・佐原彩子・佃 陽子 訳
税込5,940円/本体5,400円
A5判・上製・430頁
ISBN978-4-8158-1092-4 C3021
在庫有り
「毎日新聞」 [2023年4月1日付、書評欄] から(評者:本村凌二氏)
殉教の日本
近世ヨーロッパにおける宣教のレトリック
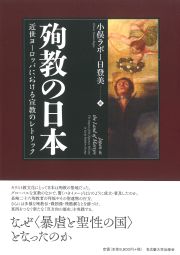
小俣ラポー日登美著『殉教の日本』が、「毎日新聞」(2023年4月1日号)書評欄で紹介されました。キリスト教文化にとって、日本は〈暴虐と聖性の国〉だった。グローバルな宣教のなかで、驚くべきイメージはどのように成立・普及したのか。長崎二十六殉教者の列福やその聖遺物の行方、さらには多様な殉教伝・磔図像・残酷劇などを跡づけ、東西をつなぐ新たな「双方向の歴史」を実践します。
“…… 近世における殉教の記述は日本に限られるわけではない。北米・中南米をはじめ布教活動がなされた地でも報告されているという。ところが、日本の殉教のみが、文書・図像・演劇などを通して広く伝えられ、ついには「大きな物語」として成立したという。そうであれば、布教政策や禁令活動の通史ではなく、教会関係者の記録を「逆なでに」読み、「起こったこと」が歴史化された文脈を解き明かすことが本書の焦点となる。……
…… 多様な殉教伝・磔刑図像・残酷劇を通じて、きわめて独特な日本像が創出された。そのプロセスを解明しつつ、キリスト教史における宣教のレトリックを問い直す作業は、東西の歴史をつなぐ試みとして、ことさら注目されてよいだろう。”(第11面)
小俣ラポー日登美 著
税込9,680円/本体8,800円
A5判・上製・600頁
ISBN978-4-8158-1119-8 C3022
在庫有り
「日本経済新聞」 [2023年4月1日付、読書欄] から(評者:斎藤環氏)
「ひきこもり」と「ごみ屋敷」
国境と世代をこえて

古橋忠晃著『「ひきこもり」と「ごみ屋敷」』が、「日本経済新聞」(2023年4月1日号)読書欄で紹介されました。日本だけではない。若者だけではない。—— 共通性と違いに目を向けることで、初めて見えてくる処方箋。著者自身の国内外での臨床経験と、精神医学の知見を踏まえつつ、当事者と向きあい、社会に問いかける、「ひきこもり」「ごみ屋敷」問題を根本から考え直す洞察の書。
“…… フランスにおけるひきこもりの認識や当事者への訪問記録は、きわめて貴重なものである。現在も海外のひきこもり情報は、『世界のひきこもり』(ぼそっと池井多著、寿郎社)など少数の例外を除いてはきわめて限られており、日本のひきこもり当事者との違いについての記述などは非常に興味深い。
著者によれば、フランスのひきこもりは自律的で、自ら進んでひきこもっているように見える人が多いとのこと。自律的に社会から逸脱するという点で、ひきこもりと「ごみ屋敷」が共通するという視点には意表を突かれた。ごみ屋敷の住人はディオゲネス症候群と診断されるが、ここから哲学者ディオゲネスの自給自足概念を経て、「私」が「私の外部」と接続した状態としての「自律」に至る考察はきわめて刺激的である。……”(第34面)
古橋忠晃 著
税込3,520円/本体3,200円
四六判・上製・284頁
ISBN978-4-8158-1113-6 C3036
在庫有り
「日本経済新聞」 [2023年4月1日付、読書欄「半歩遅れの読書術」] から(評者:三浦篤氏)
桃源の水脈
東アジア詩画の比較文化史
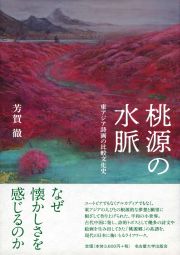
芳賀徹著『桃源の水脈』が、「日本経済新聞」(2023年4月1日号)読書欄の「半歩遅れの読書術」で紹介されました。なぜ懐かしさを感じるのか ——。ユートピアでもなくアルカディアでもなく、東アジアの人びとの根源的な夢想と願望に根ざして作り上げられた、平和の小世界。古代中国に発し、詩的トポスとして幾多の詩文や絵画を生み出してきた「桃源郷」の系譜を、現代の日本に掬いとるライフワーク。
“…… 根源的な郷愁や懐かしさがにじむ詩画の魅力を浮き彫りにする熱量と文章が素晴らしい。苛酷な現実、慌ただしい日常の中で忘れがちな、大切なものを思い起こさせてくれる。まさに文学や絵画の功徳はそこにあろう。……
今我々に何より必要なのは、健康で朗らかな生活、互に理解し合う平穏な社会であろう。『桃源の水脈』は、コロナ・ウィルスの蔓延とウクライナ戦争勃発の前に逝かれた芳賀先生が残された道しるべのような気がする。異国の人々と交流し、異分野を結び合わせたその学者人生。私は美術史の側から、広く道を開き、文芸を響き合わせるのだという勇気をもらった。
桃花源の村里への憧れは我々の胸の奥にも潜んでいる。今頃、先生は彼の地で好々爺となり、幼児と戯れていらっしゃるに違いない。”(第34面)
芳賀 徹 著
税込3,960円/本体3,600円
四六判・上製・380頁
ISBN978-4-8158-0946-1 C3090
在庫有り
『図書新聞』 [2023年4月8日号、第3586号] から(評者:森周子氏)
失業を埋めもどす
ドイツ社会都市・社会国家の模索
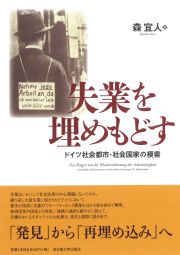
森宜人著『失業を埋めもどす』が、『図書新聞』(2023年4月8日号、第3586号、武久出版発行)で紹介されました。失業はいかにして発見され、社会政策の中心課題になったのか。繰り返し大量失業に悩まされたドイツにおいて、都市が国家に先駆けてセーフティネット構築をはかる姿を初めて解明、慈善団体や国家との対抗/連携の過程も鮮やかに捉えて、労働をめぐるモダニティの大転換を、現代も視野に描き出します。
“…… このようにして発見された失業が、失業対策という制度として社会に「再埋め込み」されていく際のライヒ(国家)の役割については、先行研究が数多く存在するが、本書は、都市の役割に着目し、詳細な分析を行っている点に独自性がある。主にハンブルク(一部ベルリン)の事例を用いて、失業の「再埋め込み」の仕方をめぐる都市とライヒのせめぎ合いを活写しており、福祉関連の給付に際して国家とそれ以外の主体の連携がどうあるべきかえを考える上で、有益な示唆を与える。また、都市が「社会的課題」の解決を目指そうとする、いわゆる「社会都市」と呼ばれる側面について、失業という、一見国家がその解決の主体とみなされそうな課題に焦点を当てて論じている。それにより、都市ガバナンスに焦点をあてた都市史研究の新たな側面をも開拓している。……”(第3面)
森 宜人 著
税込7,480円/本体6,800円
A5判・上製・396頁
ISBN978-4-8158-1103-7 C3022
在庫有り
『図書新聞』 [2023年4月8日号、第3586号] から(評者:中山弘明氏)
変革する文体
もう一つの明治文学史

木村洋著『変革する文体』が、『図書新聞』(2023年4月8日号、第3586号、武久出版発行)で紹介されました。新たな文体は新たな社会をつくる ——。小説中心主義を脱し、政論・史論から翻訳・哲学まで、徳富蘇峰を起点にして近代の「文」の歩みを辿りなおし、新興の洋文脈と在来の和文脈・漢文脈の交錯から、それまでにない人間・社会像や討議空間が形づくられる道程をつぶさに描いた意欲作。
“…… 本書の画期的な点は、なによりも「政治と文学」という、我々が二項対立的に認識している事態を根源的に問う戦略にあると言ってよいだろう。
「戦略」と書いたが、本書は極めて明晰かつ野心的な戦略性を持っている。それは「個人的な問題」が公的社会的問題を形成するという事態である。その基軸となるのが徳富蘇峰の言説である。Ⅰ部で蘇峰の言論人としての出発から、彼の新しい欧文直訳体の文体が精査され、その人物論の影響圏が追跡される。蘇峰という「哲学者、詩人、宗教家としての顔」を兼ね備えたハイブリッドな存在を基軸とすることにより、「政治と文学」が実は「地続き」の問題系であったという見取り図が、文体論的にすっきりと解き明かされていくことになる。考えてみれば、蘇峰は常に面妖な存在として君臨する一個の「謎」と言えるだろう。彼は常に戦争とともにあった。平民主義を唱えつつ、「帝国主義」の言説に鞍替えした事実だけでなく、戦時下に「詔書」の起草などにも関わり、『近世日本国民史』という膨大な「事業」を自ら進めた、きわめて政治的な存在である事実は誰もが知るところだ。本書はそのタブーに敢えて挑戦する。従って本書が示す「蘇峰と樋口一葉」「蘇峰と国木田独歩」という、文体的系譜の解明に、恐らく多くの読者は戸惑いを隠せぬはずだ。それは蘇峰が示した、旧来の「慷慨型の政治」に代わる「憐れみ型の政治」というい新しい言説が、「論述主体の内なる発熱」を読者に実感させ、「文学」がこうした「内的志向」の存在、「知識人」の型を生成したという構図である。「精神的開国」と言われた所以である。前著以来、著者が強調する「文学熱」の問題が、本書に至ってより鮮明になり「もう一つの明治文学史」を描き出すことに成功している。Ⅱ部では、俗語の問題、ユーゴー受容、志賀重昴『日本風景論』、田口卯吉『日本開化小史』などが、次々に論じられていく。著者は、文学研究がしばしば陥る「小説中心主義」を排し、「雑多な文の集合体」として広義の「文学」を定位し網羅的に探査する方法をとる。……”(第6面)
木村 洋 著
税込6,930円/本体6,300円
A5判・上製・358頁
ISBN978-4-8158-1108-2 C3095
在庫有り