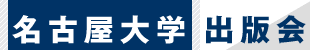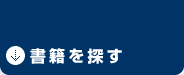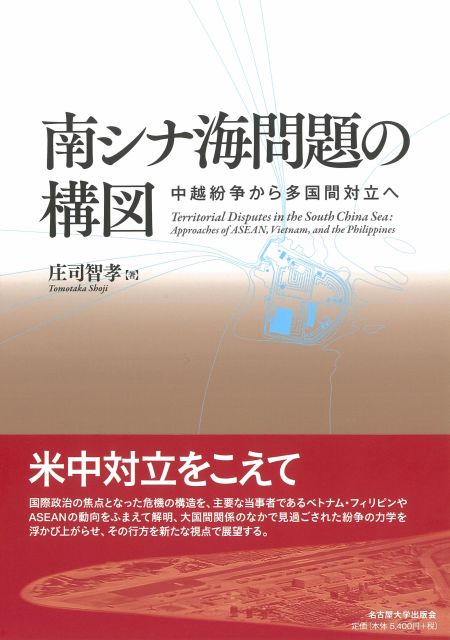内 容
中国の急速な台頭により国際政治の焦点となった危機の構造を、主要な当事者であるベトナム・フィリピンやASEANの動向をふまえて解明、非対称な大国と向きあう安全保障戦略をとらえ、米中対立の枠組みにはおさまらない紛争の力学を浮かび上がらせて、危機の行方を新たに展望する。
目 次
関連地図
略語一覧
序 章 南シナ海問題とは何か
—— ASEAN とベトナム・フィリピンの視点
1 問題の所在 —— 南シナ海問題の複雑さ
2 現代の安全保障課題としての南シナ海 —— 先行研究の視点から
3 ASEAN とベトナム・フィリピン —— 南シナ海問題への対応をめぐって
4 本書のアプローチ —— 安全保障の諸様相
5 本書の構成
第1章 南シナ海問題の発生(前史~1990年代半ば)
1 問題の前史 ——「無主」状態から領有権争いへ
2 領有権争いの本格化 —— 現在の構図の形成
3 ベトナムと南シナ海問題 —— 1980年代の展開を中心に
4 ASEAN と南シナ海問題
おわりに —— 南シナ海問題の構図の形成
第2章 南シナ海の「凪」(1990年代半ば~2000年代半ば)
—— 中国の「微笑外交」
1 ASEAN の楽観的展望 —— 対中関係の拡大深化と「行動宣言」の署名
2 ベトナム・中国関係の「凪」—— 領土国境問題の「部分的」解決
3 フィリピンの対中姿勢の軟化 —— 共同開発の模索
おわりに —— 南シナ海の短い凪
第3章 南シナ海問題の再燃(2000年代半ば~10年代半ば)
1 中国の南シナ海進出の再活発化 —— その態様と背景
2 米国の対応 —— 積極的関与と問題の構図の変容
3 ASEAN の対応 —— 内部矛盾と平和的解決の追求
おわりに —— 米国の登場と構図の変化
第4章 対中関係安定化の模索
—— ベトナムの対応(1)
1 脅威認識の高まりと「全方位安全保障協力」
2 オイルリグ事案の発生とその経過(2014年5~7月)
3 リグ事案の含意 —— 中国への「政治的信頼」の喪失と新たな方策
おわりに —— ベトナムの「幻滅」
第5章 対米安全保障協力の強化
—— ベトナムの対応(2)
1 協力の初期段階 —— きわめて漸進的な発展
2 協力の本格化 ——「3つの No」原則の論理と実践
3 オイルリグ事案後の協力の新展開
おわりに —— 対米安全保障協力のアクセルとブレーキ
第6章 ASEAN、ミドルパワー、そして自助努力
—— ベトナムの対応(3)
1 ASEAN の活用と限界 —— 域内ポリティクスと2国間協力の追求
2 ミドルパワーとの協力 —— 自助努力の補完
おわりに —— ベトナムが追求した「全方位性」
第7章 フィリピンの対応
—— アキノ政権の対決姿勢
1 アキノ政権初期の穏健対応
2 スカボロー事案の発生 —— 対決姿勢への転換
3 対応の3形態 —— 外交、同盟、国際法
おわりに —— 米国主導の地域秩序への信頼
第8章 南シナ海問題の変容(2010年代半ば~現在)
1 米中対立の激化 —— 南シナ海が軍事対立の焦点へ
2 比ドゥテルテ政権の南シナ海政策と ASEAN
3 ベトナムの対応 —— 全方位安全保障協力の拡大と深化
おわりに —— 米中対立と ASEAN の戦略的自律性
終 章 南シナ海問題の構図
—— 総括と展望
1 3つの時期区分 —— 2つの嵐と1つの凪
2 中越紛争から多国間対立へ —— 南シナ海問題の構図の変化
3 主要アクターの役割 —— ASEAN とベトナム・フィリピン
4 規範の効用と限界
5 南シナ海問題の展望 —— 複雑化と拡大の継続
注
参考文献
南シナ海問題に関する年表
あとがき
初出一覧
図表一覧
索 引
受 賞
書 評
『東南アジア研究』(第61巻第2号、2024年1月、評者:古田元夫氏)
『国際安全保障』(第51巻第1号、2023年6月、評者:福田保氏)
『アジア研究』(第69巻第1号、2023年1月、評者:黒杭良美氏)
関連書
『世界史のなかの東南アジア』(上下巻) 太田 淳・長田紀之 監訳