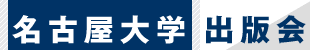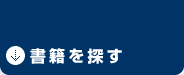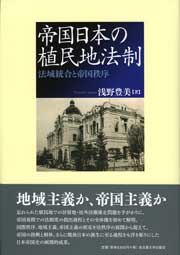内 容
忘れられた植民地での居留地・治外法権廃止問題を手がかりに、帝国規模での法制度の創出過程とその全体像を初めて解明、国際秩序、地域主義、帝国主義の相克を法秩序の展開から捉えて、帝国の勃興と解体、さらに戦後日本の誕生に至る過程をも浮き彫りにした日本帝国史の画期的成果。
目 次
序 論
1 帝国法制研究の意義とその研究史上の位置
2 帝国法制分析の方法論
3 近代日本の条約改正と法典編纂
4 居留地制度
5 植民地版条約改正と地域秩序 —— 本書の分析視角と全体構成
第Ⅰ編 台湾の領有と住民の地位
はじめに
第1章 台湾住民の国籍選択権と初期台湾法制
1 日清講和条約国籍選択条項の台湾法制上の位置
2 戸籍調査による全員登録原則
3 「清国人」単身者の強制送還と現行条約の台湾施行
4 停止条件説から解除条件説へ
5 「清国人」と「台湾本島人」の分離 —— 居留地境界の再登場
6 国籍問題から台湾法制へ
第2章 陸奥改正条約と初期台湾法制
1 条約改正と法典施行対象としての沖縄と台湾
2 東アジア国際関係の転換と台湾統治
3 原敬の新条約即時台湾施行論
4 デニソンのアプローチ —— 台湾への新条約施行と属人法制度論
5 カークードのアプローチ —— 新条約延期論と属人法反対論
6 属人・属地法体系の収斂可能性
—— 2つの漸進主義と渉外法制のあり方をめぐって
第3章 属人的法体系の成立過程
—— 明治31年律令第8号
1 寺尾亨の意見書
2 閣議要請と内閣の交替
3 台湾統治再編と第三次伊藤内閣 —— カークードと梅謙次郎
4 台湾への法典施行の模索過程と「法域」の誕生 —— 明治31年律令第8号
第4章 梅謙次郎と後藤新平
—— 初期台湾法制における法典と慣習
1 内閣法制局長官梅謙次郎の台湾法制構想
2 梅の慣習論
3 後藤新平の構想 —— 属人法制度から旧慣調査へ
おわりに
第Ⅱ編 保護下韓国の条約改正と帝国法制
—— 破綻した日韓の地域主義的結合
はじめに —— 忘れられたもう1つの条約改正
第1章 工業所有権をめぐる韓国条約改正モデルの誕生
1 韓国治外法権廃止問題の国際環境と工業所有権の法的性格
2 韓国版条約改正の主体 —— 日韓共同の自治構想
3 アメリカの東アジア進出と韓国条約改正構想
4 外務省のアプローチ —— 日韓工業所有権相互保護条約体制の模索
5 伊藤統監のアプローチ —— 交渉鈍化と順番の入替
6 外圧下の交渉促進と利用されたハーグ密使事件
7 国際関係における「指導・保護・監理」体制への韓国編入
第2章 在韓日本人と韓国土地法
1 外国人としての在韓日本人社会と韓国の条約改正
2 1907年以後の伊藤博文統監による治外法権廃止政策の展開
3 在韓日本人社会の社会経済的基盤と統監府による管理強化
4 在韓外国人課税政策と外国人土地家屋所有権承認政策の交錯
第3章 日米条約批准と工業所有権関連法令の制定過程
1 韓国工業所有権法の模索 —— 韓国法と日本裁判所、司法協同構想の破綻
2 アメリカへの韓国鉱業権認可を契機とした治外法権廃止反対勢力の結集
3 工業所有権法制から司法権委託への道
4 日本裁判所の設置から司法権委託へ
第4章 日米条約による部分的治外法権廃止モデルの挫折
1 倉富有三郎による日本裁判所設置構想と梅謙次郎の反論
2 韓国工業所有権分野の部分的治外法権廃止モデルの撤回
—— イギリスの反対
3 在韓日本人の韓国裁判所拒否
4 在韓日本人による急進的併合論の台頭
5 司法権委託の実現と「併合」の内実をめぐる攻防
6 立憲主義の拡大か天皇大権か —— 秋山雅之介意見書と現実の併合
7 明治憲法体制と帝国法制 —— 韓国編入の位相
おわりに —— 地域主義的結合と帝国的膨張
第Ⅲ編 帝国法制の構造と展開
はじめに
第1章 属人法の歴史的展開と帝国法制
1 共通法の基本的性格
2 属人主権と領域主権との調和 —— 外国人の権利と国際私法
3 「未開」社会との間での法律適用規則の模索と日本の条約改正
4 「法域」形成と法律適用規則の必要性
第2章 法規分類からみた帝国法制の全体構造と共通法の機能
1 法域と形式、そして内地延長
2 依用と内容、そして単位法律関係
第3章 属人的法令を中核とする帝国法制の構造
1 共通法による法域間の「連絡」
2 「適用」規則とヒトの地域への所属
3 刑事法領域における帝国大への拡大
第4章 共通法制定と「法域」の誕生
—— 帝国秩序と国際秩序の媒介としての「法域」
1 共通法制定の契機と制定過程
2 共通法の規定対象をめぐる論争
3 帝国秩序の不安定要素 —— ヒトの地域への所属をめぐる論争
第5章 国際関係における属人法と「外地」における属人法
1 「外地」に封印された属人法の帝国大への拡大
2 地域内属人法と属人主権原理としての治外法権制度
おわりに —— 帝国法制再編の2つのベクトル
第Ⅳ編 帝国秩序としての日満特殊関係と満洲国国籍法の挫折
はじめに —— 新しい国際標準としての民族自決原則と日満二重国籍
第1章 在満日本人の満洲国国籍取得と治外法権撤廃問題の起源
1 独立国家建設方針と居留外国人としての在満日本人
2 五族協和と満洲国の初期国籍法案
3 国籍法の行き詰まりから治外法権の廃止へ
第2章 満洲国における条約改正の展開
1 満洲国承認と漸進主義による治外法権撤廃論
2 治外法権撤廃の推進
3 治外法権撤廃の壁としての在満日本人社会と関東軍の構想
第3章 満洲国条約改正の実現と日満特殊関係の形成
1 近代日本と満洲国、2つの条約改正の交錯と枢密院
2 在満日本人の法的地位問題
3 在満漢人との融和問題
4 門戸開放原則と「第三国人」の法的地位問題
5 条約改正の方針 ——「日本人の満洲国」か「満洲人の満洲国」か
第4章 帝国法制の拡大としての日満特殊関係の法的内実
1 空洞化された満洲国司法権と行政権
2 満洲国民法と刑法の基本構造 —— 属人法と司法事務共助
3 弱い法域の形成 —— 民籍法と親属継承法の制定
おわりに
第Ⅴ編 大東亜広域秩序建設と日本帝国最後の再編
はじめに
第1章 帝国再編の政治的文脈
1 植民地帝国と総力戦 —— 帝国法制の偽善
2 民族解放政策と植民地としての朝鮮・台湾
3 内地延長の「実行」による帝国の国民国家化構想
第2章 帝国再編をめぐる官僚内政治プロセス
1 内務省によるもう1つの処遇改善
2 ヒトの地域間移動の構想と生活感情秩序
3 帝国議会と枢密顧問官伊澤多喜男
第3章 内地延長による脱植民地化の実行過程と終戦外交
1 偽善の制度化をめぐる政治過程
2 帝国法制再編の内実
3 終戦外交の文脈における信託統治と帝国の国民国家化
おわりに
第Ⅵ編 帝国から国際関係へ
—— 折りたたまれた帝国としての戦後日本
はじめに
第1章 戦後日本の国民再統合過程
—— 新たな価値と植民地の記憶
1 植民者から引揚者へ —— 戦争被害と平和の記憶
2 「文化国家」による戦後日本の復興と国際民主主義
3 異なる「文化」概念と国内冷戦
第2章 民主主義論争の中の引揚者と心理的脱植民地化
1 「日中提携」のための現地残留方針 —— 台湾からの引揚
2 異なる民主主義と日本人の葛藤 —— 大連からの引揚
3 引揚促進問題をめぐる「民主主義」論争
4 引揚者の「政治的性格」鮮明要求と在外同胞援護会の展開
第3章 賠償と在外財産をめぐる戦後日本外交の起源
1 侵略責任論争の国内的封印
2 賠償と講和後の平和的海外再進出
3 在外財産の清算をめぐる講和と国交正常化
おわりに —— 文明的正義と民族的正義の行方
結 論
注
あとがき
初出一覧
細目次
法令等索引
人名索引