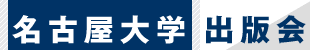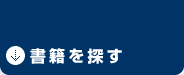内 容
360円レート成立の起源から、ニクソン・ショックによる固定相場制の崩壊まで、戦後復興・高度成長を可能にした対外金融構造を、日米の一次資料を駆使 して実証的・立体的に解明、戦後日本経済の国際的連関をこれまでにない水準で示し、ブレトン・ウッズ体制の理解にも新たな光を投げかける。好評の前著『日本の対外金融と金融政策』に続く、戦後経済への鋭い分析。
目 次
序 課題と方法
第1章 360円レートの成立
第1節 対外取引の全面禁止
1. 対外取引の全面管理と「貿易資金」の設置
1)対外取引の全面的停止
2)貿易の再開と「貿易資金」の設置
2. 管理貿易発足後の為替相場再開論
1)「進駐軍レート」の設定と1946年中の為替相場再開論
2)1947年前半の為替相場再開論
3)GHQ/SCAPの為替問題認識
4)「貿易資金」の赤字とSCAP勘定
第2節 複数レートの時代
1. 制限付民間貿易の再開と為替対策
1)GHQ/SCAP ESS「円為替委員会」の設置と日本側の対応
2)中間安定計画と実質複数レート
2. ヤング報告とGHQ/SCAPの反発
1)ヤング報告
2)「貿易資金」赤字の累増
第3節 単一為替レートの設定
1. 単一レート設定への旋回
1)GHQ/SCAP・日本側の複数レート作業と単一レート問題認識
2)NSC-13/2と「中間指令」
2. ドッジの来日と360円レートの決定
1)「9原則」の波紋
2)360円レートの決定
3. 外国為替管理委員会の設置と外貨資金の日本移管
1)外国為替管理委員会の設置
2)外貨管理の日本側移管
第4節 ドッジ改革後の占領政策と日米経済協力
1. ドッジ・ライン以後の対日援助問題
1)ドッジの対日援助観
2)アメリカ本国における対日援助政策をめぐる対立
2. 経済復興計画審議会の設置からエオス作業まで
1)経済復興計画審議会の設置
2)エオス作業
3. 朝鮮特需・日米経済協力・経済自立
1)朝鮮特需とドッジ
2)アメリカのアジア戦略と日米経済協力
第2章 360円レートの時代
第1節 外為・外貨規制と外貨管理
1. 外貨管理の対日移管とオープン勘定の保持運営
2. 外貨予算制度と外貨収支の推移
1)外国為替統計と外国為替予算制度
2)外貨収支の推移
3. 1950年代の外貨危機
1)1953年の外貨危機と外貨予算
2)1957年の外貨危機と外貨予算
3)1950年代の輸出入の動向
第2節 IMFコンサルテーションとOECD加盟
1. IMFコンサルテーション
1)IMF加盟と14条国コンサルテーション
2)1953-58年度の対日コンサルテーション
3)1959-61年度の対日コンサルテーション
4)1962-63年度の対日コンサルテーション
5)8条国コンサルテーション
2. OECD加盟
第3節 国際収支の黒字転換と資本自由化
1. 1960年代の国際収支と輸出入の推移
1)1960年代前半の国際収支と外貨準備
2)1960年代後半の国際収支
3)1960年代の輸出入の推移
2. 漸進的資本自由化
1)OECD加盟後の資本自由化問題
2)漸進的自由化と日米経済問題の発生
第3章 360円レートの終焉
第1節 外貨準備の急増と円切上げ回避政策
1. 国際通貨体制の動揺と外貨準備の急増
1)ブレトン・ウッズ体制の動揺
2)マルクの暫定フロート移行とアメリカの政策転換
3)国際収支の黒字基調と外貨準備の急増
2. 外貨準備増加抑制・短資流入規制政策の展開
1)外貨準備増加抑制政策の開始と強化
2)貿易金融と短資流入
3)短資流入規制
3. 円切上げ回避政策の固守
1)ドル・シフトと証券投資
2)為替管理の緩和と欧州為替投機の勃発
3)円対策8項目と円切上げ論議
第2節 ニクソン・ショックと国際調整の難航
1. ニクソン「新経済政策」とそのインパクト
1)ニクソン「新経済政策」の発表と為替投機
2)ショック直後のドル売りと為替管理の法制化
2. 国際通貨調整の難航
1)国際通貨調整の開始と円切上げ論の台頭
2)調整の難航 —— ワシントンG10会議からパリG10代理会議へ
3)調整への突破口 —— ローマG10
第3節 スミソニアン合意
1. フロート制への一次的移行と為替管理の強化
2. スミソニアン合意に向けて
1)スミソニアンに向けての日本の方針
2)スミソニアン合意の発表
3)外国為替資金特別会計と日本銀行の為替差損問題
第4節 フロート制への本格的移行
1. 円再切上げの回避
1)進まなかったドルの還流と為替管理の再強化
2)外貨準備の累増と諸外国からの対日批判
3)第2次円対策7項目
2. 続く通貨調整後の不安定
1)ポンドのフロート移行
2)IMFC20の発足とIMF総会
3)外貨貸し制度の発足と第3次円対策5項目
3. フロート制への全面的移行
1)ヨーロッパ通貨危機の再燃
2)円フロートへの決断とEC共同フロートへの移行
第5節 第1次石油危機と管理フロートへの移行
1. フロート制への対応と「265円レート」の為替政策
1)国際通貨制度改革論議とIMFC20の活動
2)「265円レート」の市場介入
2. 第1次石油危機の勃発と為替政策の転換
1)第1次石油危機の勃発と国際通貨面での対応
2)石油危機前後の国内為替市場と介入方針
3)石油危機からの脱出と円レートの安定
結 ブレトン・ウッズ体制とは何であったのか?
あとがき
参考文献
図表一覧
人名索引
事項索引
書 評
『歴史と経済』(第217号 2012年10月、評者:浅井良夫氏)