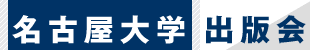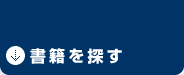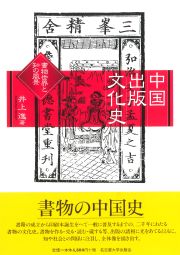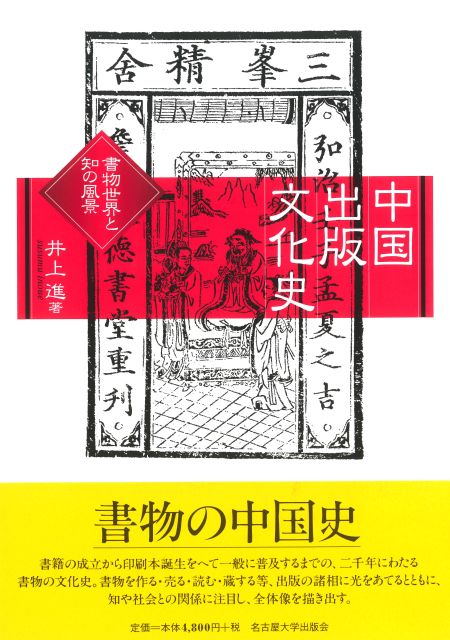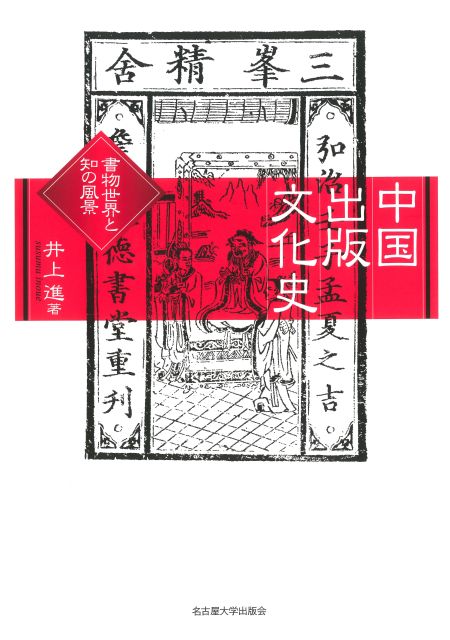内 容
春秋時代の書籍成立から印刷本の誕生をへて明末の書物普及までの、二千年にわたる書物の文化史。書物を作る・売る・読む・蔵する等、さまざまな相に光をあてるとともに、知のあり方はもちろん、帝国の政策やイデオロギーとの関係など、政治・社会との相互作用に注目し、全体像を描き出す。
目 次
はじめに
前 編
第1章 書籍の成立
書籍なるもの
著 書
蔵 書
読書の学
第2章 帝国の秩序と書籍
焚書坑儒
燼余の書
書は積もりて丘山のごとし
漢が経書を亡ぼした?
専門の学
『史記』と漢朝
第3章 帝国の黄昏
再建された帝国
蔵書の難
博く学ぶ
需要の高まり
二世紀の書物事情
第4章 自己主張する「文章」
新しい世界の主人公
著述による不朽
盗作、仮託
経史子集
玄儒文史
音楽、書物、酒
第5章 貴族の蔵書とその周辺
書を好む
晋代の蔵書
家々に文史あり
鈔 書
王羲之の大盤ぶるまい
洛陽の紙貴し
斉梁の紙事情
「ほんや」の出現へ
劉勰と顔之推
第6章 新旧の相克
科 挙
受験参考書
『唐韻』と『玉篇』
印本および書肆
世界の広さ
本 編
第7章 印本時代の幕開け
印刷術の本格的登場
板本大いに備われり
紙と坊刻本
建 本
読 者
蘇東坡と出版
第8章 士大夫と出版
進士の声誉
政治的出版
怪文書
自著の刊行
出版規制
坊刻規制
「板本大いに備わる」のはよいことか?
第9章 民間の「業者」たち
刻書、売書
書肆、書賈
臨安の陳氏
私 刻
士大夫の営利出版
第10章 特権としての書籍
官刻と営利
官刻を得るの難
国家出版書
宋代における印本
収書法
宋代の蔵書事情
第11章 朱子学の時代
出版の貧困
貧困の深化
玩物喪志
正 学
書 禍
第12章 出版の冬
出版への道
醵 金
経費など
出版の偏在
刊 工
元代の蔵書
明初の蔵書
刻本十三、鈔本十七
第13章 冬の終わり
『史記』再刊
風気の変化
正徳前後
刻書、印書
江南の都市
生 員
挙業書
第14章 書籍業界の新紀元
書 船
書肆の活動
江南の営利出版
明末の書肆と書賈
蔵書事情
儒と賈
翻版問題
「版権」成立に向けて
第15章 書価の周辺
一般新刊書の値段
商賈と書籍
繡像小説、画譜、印譜など
俗の雅
古 版
第16章 知のゆくえ
内面主義
聖人の学
心学の横流
知 識
経学と経世
出版の隆盛はよいことか?
第17章 異端、異論と出版
諸子を読む
墨 子
『漢書』芸文志
風気の形成
秦始皇
第18章 出版の利用をめぐって
批判・批評
非「学者」の「著作」
生員の「作家」
著述業者
俗の自己主張
通俗文学の認知
注
あとがき
図版出処一覧
索 引
書 評
『歴史と地理』(2006年5月号、第594号、評者:高津孝氏)
読売新聞(2002年12月22日付、特集「2002年 私のベスト3」、評者:氏家幹人氏)
『歴史と地理』(2002年11月号、第559号、評者:岡田健氏)
『學鐙』(2002年7月号、第99巻第7号、評者:井波律子氏)