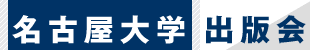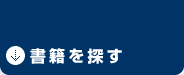『近代書史』推薦のことば:吉増剛造氏「来るべき筆蝕」
『近代書史』推薦のことば:
吉増剛造氏「来るべき筆蝕」
何処(いづこ)へ、かと、この書物は、携さえられて、はこばれて行き、……(ホラ、ここが、と、 ……書き跡を(怖ず怖ずと、あるいは、イエス・キリストが土に何かを一心に書いていたようにか、……)指でなぞってみる、……そんなページの光が、差す場面(シーン)と場所を、……)この書物が開かれ、緑か碧玉か黒いのかの目の奥が波頭のように かがやくときをわたくしは想像をする。ページの紙に触れずに、少し、宙に浮かんで、なぞる手が、あるいは来るべき筆蝕として、また、ときの筆蝕(タッチ)として、記憶の果実、核ともなるであろうことを、確信しつつ、わたくしは想像をする。
この、”来るべき筆蝕”をはこんで行くのは誰なのだろう。いづれも大冊の『中國書史』(は、2003年の3月、Beijing-北京に、……)『日本書史』(は、2001年11月26日、仏蘭西、Alsacė ColmarのGrünewaldのキリスト磔刑図をまえにして、心粛然としていたときにも、この大冊を抱えていたのだが、…… それを)はこんで行ったときのページのそよぎが、わたくしの想像を後押ししている。あるいは、もしかすると『中國書史』(50万字、京都大学学術 出版会)『日本書史』(70万字、名古屋大学出版会)、そしてこの『近代書史』(90万字、名古屋大学出版会)のほとんどのページに、丹念そして正確 無比に、挿図を、挿してくれたその手に、わたくしは自分のはこんで行く手を添えていたのかも知れなかった、……。
副島種臣、立原道造等とともに、『近代書史』白眉の一章河東碧梧桐において、石川九楊氏が、……(ほとんど、自らの「書」の折(おり)の、…… そのときのじつに繊細な心の曲折のはたらくときに似て、……というと当たるのだろう、……)「添う」という碧梧桐の手先に、注視を運んでいく個処 (本書、245頁-246頁)は、ここは、匂いたつような名品というのか、思いがけずも、白桃を口に銜んだことに、咄嗟に気がつく、麗しい章だ、……。 この「添う」「添える」があればもう「臨書」といわずにすむのかも知れず、……石川氏はとうとう「俳」をも掬うことにも成功したのだとわたくしは 呟く。
歌い添える、その手を添える。石川九楊氏の「筆蝕」も「二重言語」も、とうとう、その繊細に到達したのだとわたくしは頷く。