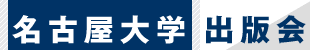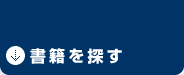『近代書史』:第36回「大佛次郎賞」選評
総評:「筆先と紙が織りなす究極のドラマ」
(宮代栄一 氏)
2段組みで700ページ超、重さ2.4キロという圧倒的ボリューム。文字の一点一画にまでこだわり続けた、新しい書の評論、表現史だ。……(中略)……
書家である石川さんにとって書とは、「学ぶべき対象」であると同時に「1次資料が書かれるまでの過程と、その状況さえもわかるという、いわば『0次資料』」なのだという。「一点一画、書字の微粒子的な律動までを観察していく。そうすると、筆先が紙に触れた時の力のやりとりまでが、その時そのままに、眼前によみがえるんです」
特色の一つがいわゆる書家以外の書が多数登場すること。夏目漱石、正岡子規、宮沢賢治、石川啄木。渋沢栄一もいれば、西田幾多郎もいる。「丸文字」や現代金釘流と石川さんが呼ぶ若者文字、中央省庁の看板文字を扱う章もある。……(中略)……
明治の元勲・副島種臣が残した筆跡や、高村光太郎のペン書きの草稿を読み解き、書かれた当時の感情や、書いている渦中の心理にまで踏み込んでいく章は圧巻。
「漢字」の書が中国の六朝の字をモデルに近代化を推し進める一方で、「平仮名」の書が、平安の「古典上代様」をモデルとして、漢字とは一線を引く形で再出発せざるを得なかった状況を考察した章など、現代書壇へとつながる分析も少なくない。
「書は筆先と紙との接触・離脱が織りなす究極のドラマであり、そこには作者の生々しい声が保存されている。その魅力をこれからも伝えていきたい」と石川さん。……(中略)……
70冊近い編著書の執筆で培われた表現力と、自身をも客観化してしまう分析力——。それこそが、この人のすごみなのだろう。
池内了氏の選評:「全体を普遍的に把握」
書については全く素人で、「書は人格なり」との風潮に反発を覚えていた私であったが、この本を読んでいるうちに書の世界の奥深さと拡がりに感じ入り、知らず知らず引き込まれてしまった。
著者の方法は分析的であると同時に統合的である。一つの字の起筆・走筆・終筆と続く流れのなかでの筆触・筆尖・筆鋒を転折・脱力・ゆれ・ひねり・減衰などとして詳細に分析するとともに、例えば西田幾多郎の書の特徴を①垂直筆②速度感③表現の変化④筆圧感というように、全体を普遍的に把握しようとしているからだ。著者は、近づいて一点一画を見つめるとともに離れてその全容を眺め、二つの視線を重ね合わせる。そして、そこで得た感懐を多様な言葉を駆使して的確に表現する。その意味では、実に科学的な書論とも言える。……
川本三郎氏の選評:「美の本質に熱く迫る」
書の世界とはこんなにも深いものだったのか。
近代の書のすべてを語り尽くそうとする大著、巨大な本だが、量もさることながら何よりも圧倒されるのは、書の美を究めたいという石川九楊さんの熱気だ。
これほど熱い研究書はそうはない。書の美を追究する。なぜある字は美しいと感じ、ある字は美しくないと感じるのか。石川九楊さんは美の本質に迫ろうとしている。……(中略)……とくにオリジナリティーにあふれた副島種臣や中村不折の書を論じるところは熱がこもっている。……(中略)……
吉本隆明が良寛について語った、書はその人の思想と深く関わる本質的なものだという言葉が全体の大きなモチーフになっている。
最後に石川九楊さん自身の書が紹介されているが、その自由奔放な書には「これが書か」と仰天させられる。
髙樹のぶ子氏の選評:「新しい世界見えてきた」
思いがけない方向から不意打ちをくらった。書は「美学」ではなく「文学」であり、「造形」ではなく「言葉」である。目から鱗が落ちた。鱗が落ちた目に、新しい世界が見えてきた。書をする筆の先が書家そのものになり、精神と肉体になり、言葉を語る声になり、さらには人生になっていく。……(中略)……
「書」が「言葉」だと知ることで、書かれたものがたちまち人格と人生を持つこの魔術的な革新は、実は創造と想像の力に負っている。白紙に黒く残された文字の化石から、書家の人生と人格を再生させるには、言葉をよすがとする強力なフィクション構成力が必要で、もっとも古めかしく見える作業の裏でフル稼働する、小説家と同質な才能が、書に無知な人間をも惹きつけてやまない。
山折哲雄氏の選評:「尋常ならぬ自信と覇気」
石川九楊氏は、こんど『近代書史』を仕上げ、『中國書史』『日本書史』とつづく三部作を完成させた。文字通り刻苦精励のたまものである。これらの仕事は「書」という問題をひっさげて、東アジアに広がる漢字文化圏の全体を睥睨する勢いを示している。その自信と覇気は尋常なものではない。……(中略)……書の歴史の流れを俯瞰しつつ、明治以後のわが国の書が「近代」といかに格闘し、どこに表現の可能性を求めてきたのかを、柔軟な筆致で詳述している。
冒頭に良寛の書をもってきて序論を展開しているのも秀逸であるが、最後に石川氏自身の書を掲げて創作の秘密を解き明かしているところには驚かされる。なぜなら「歎異抄」や「源氏物語」54帖の世界が、迷路のごとき水平線や垂直線に化身する自在の筆蹟をそこでみせつけられるからである。