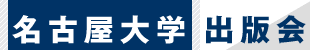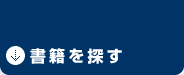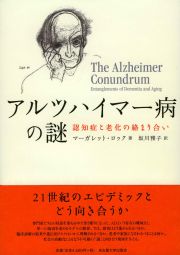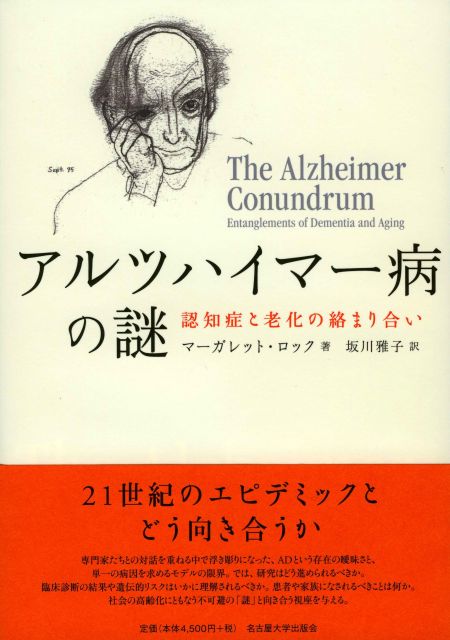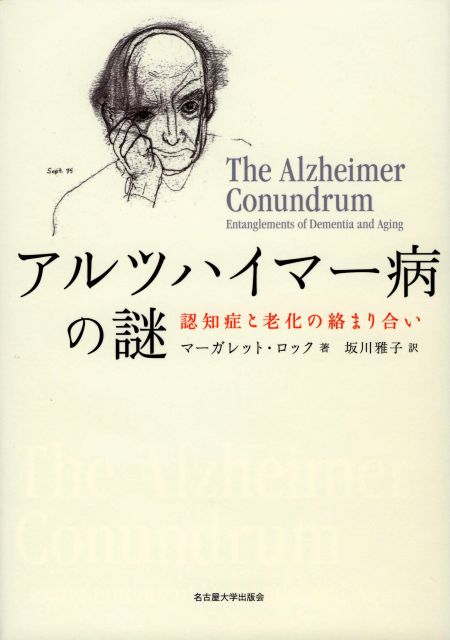内 容
専門家たちとの対話を重ねる中で浮き彫りになった、ADという存在の曖昧さと、単一の病因を求めるモデルの限界。では、研究はどう進められるべきか。臨床診断の結果や遺伝的リスクはいかに理解されるべきか。患者や家族になされるべきことは何か。社会の高齢化にともなう不可避の難問と向き合う視座を与える。
【ALL REVIEWS】『こころと文化』書評(17巻2号、2018年9月、評者:江口重幸氏)
著者紹介
マーガレット・ロック
(Margaret Lock)
1936年、英国ケント州生まれ。医療人類学の第一人者であり、日本と北米をおもなフィールドとして長年にわたり精力的に研究を行なってきた。キラム賞、ステイリー賞など受賞も多数。マギル大学医療社会学部・文化人類学部教授、カナダ・ロイヤル・ソサエティ会員。邦訳された著書に、『都市計画と東洋医学』(中川米造訳、1990年)、『脳死と臓器移植の医療人類学』(坂川雅子訳、2004年)、『更年期』(江口重幸・北中淳子・山村宜子訳、2005年)などがある。
目 次
はじめに
21世紀のエピデミック
老化する脳の概念化 —— 基本的問題
テクノフェノメノンと現実
治療から予防へ
確率の帝国主義
アルツハイマー病リスクの政治的側面
医療化と脱汚名化
老化に対するグローバルな反応
現代における寿命の伸び
思考様式
データの収集に関する説明ならびに各章の概要
第1章 アルツハイマー病の構築
老化は病気なのか
「身体派」と「心理派」
老 衰
アミロイド斑と神経原線維変化に魅了されて
アルツハイマー病という考えの一時的衰退
医療の対象としての老化
政治的問題としてのアルツハイマー病
「正常」という概念の変遷
正常はいつ病理になるのか
臨床上の拡散的シンドローム
連続的変化としての老化
第2章 アルツハイマー病の基準化を目指して
アルツハイマー病の診断の基準化
黄金基準としての神経病理学
アミロイドマフィアと、アルツハイマー病の支配的パラダイム
抗アミロイド療法
予防への動き —— 新しい辞書を
第3章 アルツハイマー病予防への道
軽度認知障害の範囲を定める
アルツハイマー病研究における新しいアプローチに対して世間の関心をかき立てる
アルツハイマー病の定義を修正する
第4章 体内に潜むリスクの顕在化
新しい提言に対する一般からの批判
臨床・病理の新しいアプローチに向かって
抜本的改革への努力
将来の予測
生体内のアミロイド
新しい骨相学
アミロイド再考
全員の神経画像診断に向けて
神経化学的自己
同じ基準で測れないものを結びつける
第5章 アルツハイマー病遺伝子
—— 予告と予防のバイオマーカー
優性遺伝するアルツハイマー病
パイサ変異体
治験の準備
研究結果を広く役立てる
早発性ADに関する遺伝子検査
とらえどころのない感受性遺伝子
ヒトのアポE —— どの型が最初に現れたのか
アポE4と神経変性
第6章 ゲノムワイド関連解析
—— バックトゥザフューチャー
GWAS が引き起こした問題
GWAS の可能性を高める
第7章 具現化した前兆とともに生きる
遺伝的側面から身体を考える
アポE遺伝子検査
リヴィール・プロジェクトを概念化する
遺伝子型を思い出す
推定されるリスクを伝える
アルツハイマー病のリスクを熟知させる
アルツハイマー病の原因をどう考えるか
知られざる遺伝子型
アルツハイマー病に関する情報源
第8章 いつ訪れるかわからないチャンス、そして運命の奪還
世界規模の呼びかけ
アミロイド仮説にとどめを刺す
遺伝的決定論のドグマを超えて
エピジェネティクス —— 地平線の拡大
騒々しい混乱
将来は変えられるか
エピゲノミクスと個々人の生活経験
第9章 解決しがたい問題に取り組む
因果関係に関する意見の対立
脳を文脈化する
アルツハイマー病は正常な老化と連続したものなのか
埋め込まれた肉体
おわりに
心を映し出す肖像画
謝 辞
訳者あとがき
注
参考文献
図表一覧
索 引
書 評
『こころと文化』(第17巻第2号、2018年9月、評者:江口重幸氏)
『日経サイエンス』(第48巻第6号、2018年6月号、評者:丸山敬氏)
『週刊読書人』(第3237号、2018年5月4日付、評者:北中淳子氏)
関連書
『高齢者の痛みケア』 イボンヌ・ダーシィ 著/波多野 敬・熊谷幸治郎 監訳/山口佳子 訳
『精神医学の科学哲学』 レイチェル・クーパー 著/伊勢田哲治・村井俊哉 監訳/植野仙経・中尾 央・川島啓嗣・菅原裕輝 訳