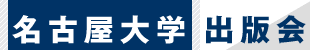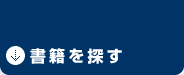「はしがき」 (高島正憲著 『経済成長の日本史』)
高島正憲著 『経済成長の日本史』
「はしがき」 から
「天地は広いというけれども、わたしには狭くなったのだろうか。太陽や月は明るいというが、わたしのためには照ってくれないのだろうか。ひとは皆こうなのか、それともわたしだけこうなのだろうか。人として生まれて、人並みに働いているのに、綿も入っていない粗末な、海藻のように裂けてぼろぼろになった衣を肩にかけ、つぶれかかったような、倒れかかったような家のなかに、地面にじかに藁をしいて、父と母は頭の方に、妻と子は足の方に自分を囲むようにして、悲しみ嘆いている。かまどには火の気もなく、米を蒸す器には蜘蛛の巣がかかってしまい、飯をたくことも忘れはててしまった。ぬえ鳥のように、かぼそい力ない声で苦しみうめいていると、ひどく短いものの端をさらに切りつめるかのように、鞭をもった里長の声が寝床にまで聞こえてくる。こんなにもつらく、苦しいものなのだろうか、世のなかというものは。この世はつらく、消えてしまいたいと思うけれども、わたしは鳥ではないから、どこかに飛び去っていくこともできない。」 (山上憶良「貧窮問答歌」)*
いまから1300年ほど前に律令国家の官人で歌人でもあった山上憶良が詠んだ 「貧窮問答歌」 には、破れた布服を着て狭い住居に暮らし、飯を炊く方法も忘れるほどに困窮した農民の姿が描かれている。この写実的な歌は、どれほどまで古代の人びとの暮らしの実態を反映しているのだろうか。その一方で、小野老が 「あをによし奈良の都は咲く花の薫ふがごとく今盛りなり」** と詠んだように、中央集権化を目指した律令国家によって建設された奈良の平城京では、王朝国家は本当に繁栄をきわめていたのだろうか。どうしようもないほどに貧しく描かれた私たちの祖先の大部分の人びとは、そして栄華をきわめた古代の貴族たちは、そしてその子孫たちは、その後、何らかの生産手段をもって営みを維持し、ときには破綻しながらも、時代をのりこえて現在の我々へと歴史を受けついできた。その間、いったいどのような生活の浮き沈みがあったのだろうか。
この問いを経済学の関心に引きつけるなら、古代から庶民はどの程度の生活水準だったのか、そして、列島日本はどのくらいの経済規模だったのか、という関心となる。それは現在であれば、平均年収や生産にかんする統計や経済的指標といった具体的な数値によって知ることができる。だが、それを奈良時代にまでさかのぼって知ろうとしたとき、資料的な限界という大きな壁が立ちはだかる。そのような場合、特定地域の資料から算出した値を代表値として扱うか、何らかの仮定を設定した統計的加工、すなわち 「推計」 という作業をしなければならない。こうした歴史への接近法は、歴史の数量化ともいえるが、歴史学ではさほどメジャーな分野とはいいがたく、ときには、数量化によって描かれた歴史像はまったく信頼できないものとして否定されたり、フィクションだと揶揄されたりもする。
だが、数量化された歴史とは本当に意味のないものだろうか。これまで、歴史学・経済史学によって、前近代日本の経済成長にかんする研究がなされ、さまざまなことが明らかになってきたが、それがこと長期のマクロ経済の成長となると、関連する議論は乏しく、ぼんやりとしかイメージできないのが現状であろう。たしかに、これまでにも前近代日本の人口や生産を数量的にはかろうとする研究は存在したが、それらは歴史の一時点、もしくは人口などの特定の系列を計測したものであった。結局のところ、私たちは前近代日本のマクロ経済の成長については具体的な数量をもって説明される歴史像をもっていないのである。
こうした課題に挑戦するために本書が採用したのが、超長期の経済成長の分析である。具体的には、奈良時代から明治期初頭までを、1人あたりGDP (国内総生産) という歴史を縦につらぬく1本の串をもちいて観察することにより、前近代日本の経済成長を明らかにしようとする試みである。歴史学研究は時間のフローをあつかうものであるが、そのためには、ある時代とその前後の時代との間に存在する相違を比較分析するための共通の基本概念の枠組みをもちいたアプローチが必要になる***。本書であつかう超長期の推計は、それぞれ違った時代の歴史的資料からえられた経済的諸変数を同質化し、歴史的過程と再結合させて、それを経済学的な接近方法で分析する定量的な枠組みにたっている。たとえば、中世という事実上 「国家」 の枠組みがなく、複数の分権的な勢力による統治によって列島が形成されていた時代を、あえてGDPという 「国内」 総生産の指標をもちいて、列島日本の長期の経済成長という枠組みのなかでとらえたのも、こうした考え方によるものである。また、GDPというマクロ経済の各国共通の指標をもちいることによって列島日本の経済成長の歴史を (直接の政治・経済・文化などの交流の有無にかかわらず) 他国と比較するからこそ、地域が異なる国と国との間の経済成長の推移の違いが可視化され、そこにそれぞれの国の発展経路の違いをみつけることができるのではないだろうか。
本書は、古代における律令国家の中央集権化の試みとその崩壊から、自由な中世社会における市場経済の萌芽、そして戦国期から織豊政権の全国統一を経て、徳川幕府による列島支配と市場経済への移行、開国から明治維新という近代化へ向けた長い経済成長の道のりを、超長期GDPの推計からみるものである。本書では可能なかぎり伝統的な経済史学の作法にしたがって、利用した文献を明示し、推計の方法について詳細に説明するようにこころがけた。なぜなら、本書がとった経済史の方法は定量的研究の傾向が強く、結果に対して他者による追試と批判的検討の可能性をもたせなければならないからである。批判が新たな問題関心を生み、そこから発展的な議論が進むのなら、それでよい (役割を果たした) と私は思う。もし、本書が提示した日本の経済成長のかたちが、経済学・歴史学・経済史学、それらの各時代・各分野の研究の発展に少しでも寄与することができれば、筆者にとってこのうえない喜びである。
*『万葉集』 巻5–892/893。原文漢文。口語訳の作成にあたっては、佐竹昭広・山田英雄・工藤力男・大谷雅夫・山崎福之校注 『万葉集1 (新日本古典文学大系1)』 (岩波書店、1999年、502–504頁)、小島憲之・木下正俊・東野治之校注 『万葉集2 (新編日本古典文学全集7)』 (小学館、1995年、70–72頁) を参照した。
**『万葉集』 巻3–32。原文漢文 (佐竹ほか校注 『万葉集1』、231–232頁)。
*** 新保博 「数量経済史の人間化」 (『三田学会雑誌』 第75巻第5号、1982年、17–26頁) を参照した。